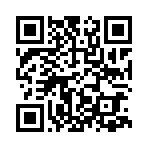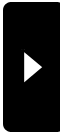2008年06月30日
蛍の舞う堰(せぎ)
我が家の前の堰(せぎ)に蛍が舞い始めています。
堰(せぎ)は、戸隠山麓を水源とする鳥居川から水を引き
農業用水として利用されています。
いまは、コンクリートで固められた部分が多くなりましたが、
昔は、石を積んで壁とし、よく石と石の間からヘビが顔を出したり
川の中の石のくぼみに、手を入れて、銀フナを捕まえたりと
田舎の自然そのものといった「堰(せぎ)」でした。
タニシもいましたから、蛍の幼虫の「カワゲラ」もたくさんいました。
紫陽花の咲く頃になると、蛍がまさに「乱舞」したものです。
防犯上の理由もありますし、用水としての本来の機能もあることから
その後改築され、かなりの部分が、コンクリートで固めれれるようになりました。
もちろんコンクリートで固められた、川底と用水の壁からは
ヘビも突然顔を出さなくなりましたし、
手を突っ込める程の石の隙間もなくなりました。
機能面から言うと、用水本来の機能も有し
扱いやすくなったのではないかと思います。
でもその分、蛍の姿が見えなくなりました。
我が家の周辺は、どうしてかコンクリート化されず
昔のままの部分がかなり残っています。
川底を見つめると、様々な生物を見つけることが出来ます。
蛍の幼虫「カワゲラ」もその中の一つです。
川にスコップを入れておくと、カワゲラがビッシリとくっついています。
そんな奇麗な虫ではなく、これが蛍の幼虫??と思うほどですが、
比較的デリケートな虫で、コンクリートで固められた用水には
全くいません。
よきにつけ悪しきにつけ、既にコンクリートで塗り固められた用水が
ほとんどの昨今となってきました。
少しでも、このままの姿を残して欲しいと思います。
これは、決して、「懐古趣味」でも「郷愁」ではありません。
「残すべき自然は、残す。」
コンクリートでこれ以上、塗り固め、田舎の風景を近代化しても
話題の食糧自給率は決して上がりますまいと思う昨今です。
自然にやさしく、自然と共に
それが本来の姿だと思います。
苗が大きくなり始めた稲田。
田んぼには、今おたまじゃくしがウヨウヨしています。
夜はうるさいくらいのかえるの合唱。
BGMにこんな「かえるの合唱」はいかがでしょうか。

終日の雨で、翼をぬらしたツバメが、羽を乾かす。

手前がネコヤナギの木。左が紫陽花の木。
その間を、石の積み重ねられた堰が流れます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 信州の地物野菜を美味しく食べよう・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
堰(せぎ)は、戸隠山麓を水源とする鳥居川から水を引き
農業用水として利用されています。
いまは、コンクリートで固められた部分が多くなりましたが、
昔は、石を積んで壁とし、よく石と石の間からヘビが顔を出したり
川の中の石のくぼみに、手を入れて、銀フナを捕まえたりと
田舎の自然そのものといった「堰(せぎ)」でした。
タニシもいましたから、蛍の幼虫の「カワゲラ」もたくさんいました。
紫陽花の咲く頃になると、蛍がまさに「乱舞」したものです。
防犯上の理由もありますし、用水としての本来の機能もあることから
その後改築され、かなりの部分が、コンクリートで固めれれるようになりました。
もちろんコンクリートで固められた、川底と用水の壁からは
ヘビも突然顔を出さなくなりましたし、
手を突っ込める程の石の隙間もなくなりました。
機能面から言うと、用水本来の機能も有し
扱いやすくなったのではないかと思います。
でもその分、蛍の姿が見えなくなりました。
我が家の周辺は、どうしてかコンクリート化されず
昔のままの部分がかなり残っています。
川底を見つめると、様々な生物を見つけることが出来ます。
蛍の幼虫「カワゲラ」もその中の一つです。
川にスコップを入れておくと、カワゲラがビッシリとくっついています。
そんな奇麗な虫ではなく、これが蛍の幼虫??と思うほどですが、
比較的デリケートな虫で、コンクリートで固められた用水には
全くいません。
よきにつけ悪しきにつけ、既にコンクリートで塗り固められた用水が
ほとんどの昨今となってきました。
少しでも、このままの姿を残して欲しいと思います。
これは、決して、「懐古趣味」でも「郷愁」ではありません。
「残すべき自然は、残す。」
コンクリートでこれ以上、塗り固め、田舎の風景を近代化しても
話題の食糧自給率は決して上がりますまいと思う昨今です。
自然にやさしく、自然と共に
それが本来の姿だと思います。
苗が大きくなり始めた稲田。
田んぼには、今おたまじゃくしがウヨウヨしています。
夜はうるさいくらいのかえるの合唱。
BGMにこんな「かえるの合唱」はいかがでしょうか。

終日の雨で、翼をぬらしたツバメが、羽を乾かす。

手前がネコヤナギの木。左が紫陽花の木。
その間を、石の積み重ねられた堰が流れます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 信州の地物野菜を美味しく食べよう・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月29日
モロッコインゲン・・・・・なぜモロッコなのか??
「モロッコインゲン」が獲れ始めました。
なぜ「モロッコ」の名前が付くのか、分からないのですが
インゲンの仲間で、平べったく、ツルがどんどん延びていく種類です。
母親が言うには、
「最近の蔓の伸びる野菜は、自分で這い上がれなくなった」と
申しておりましたが、キュウリにせよ、上には伸びていくのですが、
蔓を、ネットなどに括り付けてあげ補助してあげないと、伸びる力がなくなったそうです。
そんな「蔓の延びる」中で、モロッコインゲンだけは、旺盛で
自分で勝手にドンドン蔓を伸ばし、這い上がっていきます。
他に、細長いタイプのいわゆる「ドジョウインゲン」もあり、
スーパーの冷凍野菜売り場で見かけるインゲンは、
その「ドジョウインゲン」です。
胡麻和えが、一番一般的ですが、味噌マヨ和えも昨年トライしてみて
結構美味しかったです。
煮物にも使え、アレンジの仕方色々の「モロッコインゲン」です。
また、豆を大きくして、乾燥させ、「煮豆」としても美味しくいただけます。
ただ、「煮豆」は、20年近い自炊生活で一回もチャレンジしなかった料理で、こちらは全く出来ません。
今年は、丹波黒豆も長野県ならではの「くらかけ豆」も栽培しますので、
ぜひ「煮豆」にも挑戦したいと思っています。
夏野菜が、ドンドン獲れ始めました。
トマトがまだ今年は、不安定なお天気のため、まだですが
7月5日頃から獲れ始めるのではないかと思っています。
本格的な夏野菜のシーズンの到来です。
色々な料理を楽しみたいと思っていますので、
美味しいいただき方があれば、是非ご教授願います。
モロッコインゲン。平べったいタイプにインゲンです。

蔓の伸びが旺盛で、上に上にドンドン伸びていきます。

モロッコインゲンの花。サヤインゲンの花と似ていますが、
こちらは、サヤインゲンのように紫や赤の色が付いていません。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 信州の地物野菜を美味しく食べよう・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
なぜ「モロッコ」の名前が付くのか、分からないのですが
インゲンの仲間で、平べったく、ツルがどんどん延びていく種類です。
母親が言うには、
「最近の蔓の伸びる野菜は、自分で這い上がれなくなった」と
申しておりましたが、キュウリにせよ、上には伸びていくのですが、
蔓を、ネットなどに括り付けてあげ補助してあげないと、伸びる力がなくなったそうです。
そんな「蔓の延びる」中で、モロッコインゲンだけは、旺盛で
自分で勝手にドンドン蔓を伸ばし、這い上がっていきます。
他に、細長いタイプのいわゆる「ドジョウインゲン」もあり、
スーパーの冷凍野菜売り場で見かけるインゲンは、
その「ドジョウインゲン」です。
胡麻和えが、一番一般的ですが、味噌マヨ和えも昨年トライしてみて
結構美味しかったです。
煮物にも使え、アレンジの仕方色々の「モロッコインゲン」です。
また、豆を大きくして、乾燥させ、「煮豆」としても美味しくいただけます。
ただ、「煮豆」は、20年近い自炊生活で一回もチャレンジしなかった料理で、こちらは全く出来ません。
今年は、丹波黒豆も長野県ならではの「くらかけ豆」も栽培しますので、
ぜひ「煮豆」にも挑戦したいと思っています。
夏野菜が、ドンドン獲れ始めました。
トマトがまだ今年は、不安定なお天気のため、まだですが
7月5日頃から獲れ始めるのではないかと思っています。
本格的な夏野菜のシーズンの到来です。
色々な料理を楽しみたいと思っていますので、
美味しいいただき方があれば、是非ご教授願います。
モロッコインゲン。平べったいタイプにインゲンです。

蔓の伸びが旺盛で、上に上にドンドン伸びていきます。

モロッコインゲンの花。サヤインゲンの花と似ていますが、
こちらは、サヤインゲンのように紫や赤の色が付いていません。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 信州の地物野菜を美味しく食べよう・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月28日
サトイモの葉っぱの露(しづく)
サトイモが随分と大きくなってきました。
サトイモは、「ズク無し芋」とも呼ばれ
結構手間が掛かる芋であるということは
以前お話しましたが、もう一つサトイモで更に思い浮かべるのは、
葉っぱに乗る「露(しづく)」です。
雨の後ですとか、秋口の冷え込んだときなど
サトイモのは葉っぱに「露(しづく)」が乗っています。
子供の頃に、書道を習っていたのですが
先生がよく
「サトイモの葉っぱの露(しづく)で字を書くと上達する。」と
おっしゃっていました。
さすがに実行はしませんでしたが、
サトイモの葉っぱに乗っている露(しづく)は
何となく「コロコロ」していて、神秘的にも思えアレコレと想像させてくれました。
僕らの時代は、学校の帰りには必ず「道草」をして
サトイモの露を眺めたり、
今の時季ですとカブトムシを採集に山に出かけたりしたものです。
子供の頃は、暇なわけですが、「暇が仕事」ですから
次から次に、その暇な時間を「新たなる発見」に費やします。
小林一茶の句に
「やれ打つな 蝿が手をすり足をする」
というのがあります。
田辺聖子さんが、その句を評し、
子供というものは暇人だから
午後のひと時に「ジッと蝿を眺めて観察なぞ出来る」
というニュアンスのことを述べておられました。
大人は出来ない暇なのだからこそ出来る蝿の足をする様子を見つめる。
その様子を見ながら、アレコレと想像を巡らす。
くだらないようにも思えるのですが、
そんな蝿をジッと観察できるほどの「暇」が大切なのだと思います。
時代は変わり呑気なことは言っていられのかもしれません。、
サトイモの葉っぱに集まった露で
「字を書いて」とは言いませんし、
学校でもそんな呑気なことは言いませんでしょう。
ただ、自然の中にある実にくだらないかもしれない事象を見つめたり、
サトイモの葉っぱの「コロコロと集まった露」を見て
「奇麗だなあ!!」と思って、何かを想像して欲しいなあと思います。
サトイモの葉っぱに大粒の露がたまった。

まだ小さく成長途上のサトイモには荷が重過ぎるほど
立派な露がたまった。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
サトイモは、「ズク無し芋」とも呼ばれ
結構手間が掛かる芋であるということは
以前お話しましたが、もう一つサトイモで更に思い浮かべるのは、
葉っぱに乗る「露(しづく)」です。
雨の後ですとか、秋口の冷え込んだときなど
サトイモのは葉っぱに「露(しづく)」が乗っています。
子供の頃に、書道を習っていたのですが
先生がよく
「サトイモの葉っぱの露(しづく)で字を書くと上達する。」と
おっしゃっていました。
さすがに実行はしませんでしたが、
サトイモの葉っぱに乗っている露(しづく)は
何となく「コロコロ」していて、神秘的にも思えアレコレと想像させてくれました。
僕らの時代は、学校の帰りには必ず「道草」をして
サトイモの露を眺めたり、
今の時季ですとカブトムシを採集に山に出かけたりしたものです。
子供の頃は、暇なわけですが、「暇が仕事」ですから
次から次に、その暇な時間を「新たなる発見」に費やします。
小林一茶の句に
「やれ打つな 蝿が手をすり足をする」
というのがあります。
田辺聖子さんが、その句を評し、
子供というものは暇人だから
午後のひと時に「ジッと蝿を眺めて観察なぞ出来る」
というニュアンスのことを述べておられました。
大人は出来ない暇なのだからこそ出来る蝿の足をする様子を見つめる。
その様子を見ながら、アレコレと想像を巡らす。
くだらないようにも思えるのですが、
そんな蝿をジッと観察できるほどの「暇」が大切なのだと思います。
時代は変わり呑気なことは言っていられのかもしれません。、
サトイモの葉っぱに集まった露で
「字を書いて」とは言いませんし、
学校でもそんな呑気なことは言いませんでしょう。
ただ、自然の中にある実にくだらないかもしれない事象を見つめたり、
サトイモの葉っぱの「コロコロと集まった露」を見て
「奇麗だなあ!!」と思って、何かを想像して欲しいなあと思います。
サトイモの葉っぱに大粒の露がたまった。

まだ小さく成長途上のサトイモには荷が重過ぎるほど
立派な露がたまった。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
Posted by ドジヒコ at
04:48
│Comments(0)
2008年06月27日
豆を蒔く・・・・・・安心な地物の「豆」をいただく。
夏物の野菜の種まきもほぼ終りました。
この後は、盆明けに冬にいただく白菜や大根などの播種を行ないます。
晩秋に、「豆をはたいて」煮豆用の豆を作りますが、
その煮豆用の「豆」を蒔きました。
昨年は、豆を蒔いていい具合に発芽したところを
「鳩」にほとんど食べられてしまい、慌てて蒔き直しするというアクシデントに見舞われました。
今年は、豆を蒔き、発芽する頃に、「鳥除けのネット網」をかぶせ
発芽した頃を「柔らかい芽」を鳩に食べられないようにするつもりです。
善光寺さんの境内に鳩の餌の「煮豆」を売ってくれるおばあさんの姿が見かけなくなった昨今
餌の煮豆が無いために、わざわざここまで発芽した頃の黒豆を啄ばみにやってくるのかあなあとうのは
考えすぎでしょうか?
「豆」を蒔くのは今年2回目。
1回目は、ビールに美味しい、夏場にいただく「枝豆」を蒔きました。
2回目の今回分は、じっくりと実を熟させた「煮豆用」の豆です。
「丹波大納言」という種類の豆を半日掛けて、蒔きます。
豆は、発芽するまでに「水を与えません」
水を与えてしまうと、水分を吸って、腐ってしまう可能性があります。
蒔かれた豆は、土の中の水分を吸って大きくなり発芽していきます。
昨年、母親に言われ、「モロッコ豆」の種を蒔いたときに、
ついぞ豆の播種の際に水を与えてはいけないといいう「タブー」を知らず、
「たっぷりと水を与えた」ところ
かなりの部分が腐ってしまい、発芽がほとんどしませんでした。
この後、「小豆」も蒔くつもりです。
色々と「食の問題」が言われていますが、
「納得いくものを食べたい。」という思いもあり
小豆も、「落花生」に続き、自家栽培のものに挑戦します。
6月一杯くらいまでに、
「豆蒔き」は行なわなければならないようですので、
りんごの摘果の合間を縫って、今回の「丹波大納言黒豆」に続き
「丹波大納言小豆」も蒔きたいと思います。
豆は、「畑の肉」といわれるほど栄養分が豊富。
地味な野菜ですが、じっくりと作っていきましょう。
丹波大納言黒豆。
通常の黒豆より、「粒」が大きい気がします。

水やりをせずに、蒔く。
ここ数日の梅雨の雨で、土には結構な水分が含まれているので
その水分を吸って大きくなると思われる。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
この後は、盆明けに冬にいただく白菜や大根などの播種を行ないます。
晩秋に、「豆をはたいて」煮豆用の豆を作りますが、
その煮豆用の「豆」を蒔きました。
昨年は、豆を蒔いていい具合に発芽したところを
「鳩」にほとんど食べられてしまい、慌てて蒔き直しするというアクシデントに見舞われました。
今年は、豆を蒔き、発芽する頃に、「鳥除けのネット網」をかぶせ
発芽した頃を「柔らかい芽」を鳩に食べられないようにするつもりです。
善光寺さんの境内に鳩の餌の「煮豆」を売ってくれるおばあさんの姿が見かけなくなった昨今
餌の煮豆が無いために、わざわざここまで発芽した頃の黒豆を啄ばみにやってくるのかあなあとうのは
考えすぎでしょうか?
「豆」を蒔くのは今年2回目。
1回目は、ビールに美味しい、夏場にいただく「枝豆」を蒔きました。
2回目の今回分は、じっくりと実を熟させた「煮豆用」の豆です。
「丹波大納言」という種類の豆を半日掛けて、蒔きます。
豆は、発芽するまでに「水を与えません」
水を与えてしまうと、水分を吸って、腐ってしまう可能性があります。
蒔かれた豆は、土の中の水分を吸って大きくなり発芽していきます。
昨年、母親に言われ、「モロッコ豆」の種を蒔いたときに、
ついぞ豆の播種の際に水を与えてはいけないといいう「タブー」を知らず、
「たっぷりと水を与えた」ところ
かなりの部分が腐ってしまい、発芽がほとんどしませんでした。
この後、「小豆」も蒔くつもりです。
色々と「食の問題」が言われていますが、
「納得いくものを食べたい。」という思いもあり
小豆も、「落花生」に続き、自家栽培のものに挑戦します。
6月一杯くらいまでに、
「豆蒔き」は行なわなければならないようですので、
りんごの摘果の合間を縫って、今回の「丹波大納言黒豆」に続き
「丹波大納言小豆」も蒔きたいと思います。
豆は、「畑の肉」といわれるほど栄養分が豊富。
地味な野菜ですが、じっくりと作っていきましょう。
丹波大納言黒豆。
通常の黒豆より、「粒」が大きい気がします。

水やりをせずに、蒔く。
ここ数日の梅雨の雨で、土には結構な水分が含まれているので
その水分を吸って大きくなると思われる。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月26日
葱坊主・・・・・・田舎で見かける風景
毎日、りんごの摘果が続きます。
朝から晩まで、同じ作業をしていると
ちょっと気分転換も必要です。
梅雨の合間の好天の一日。
「葱坊主」を収獲しました。
「葱坊主」は、昨年定植したネギが大きくなったものです。
通常ですと、「葱坊主」が出来ると、成長する際の
養分が、種子のもとである「葱坊主」に行ってしまいますから、
せっかくの葱坊主は、「ポキっ」と折って、捨ててしまいます。
今回収獲したものは、わざと葱坊主を成長させ
ネギの種子を取るために、立派なものに仕上げました。
葱坊主は、この後乾燥させ、9月に田んぼにまき
来年の「ネギ苗」を発芽させます。
そのネギ苗は、4月に「松本一本ねぎ苗」として
田んぼに定植し、育てていき、料理のたびに使います。
言うならば、もう来年の準備といったところでしょうか。
つい先日、なぎ苗の定植が終ったと思ったら
もうネギの種を取るのですから、サイクルは早いものです。
色々な作業が農家にはありますが、
季節に応じての様々作業は楽しくもあります。
今年もここまできました。
何となく、ホッとさせてくれる田舎ならではの、葱坊主です。
自分の子孫を残そうと、葱坊主を大きくしたネギ。

葱坊主をよく見ると、「種子」がたくさん付いています。
この種子を9月にまきます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
朝から晩まで、同じ作業をしていると
ちょっと気分転換も必要です。
梅雨の合間の好天の一日。
「葱坊主」を収獲しました。
「葱坊主」は、昨年定植したネギが大きくなったものです。
通常ですと、「葱坊主」が出来ると、成長する際の
養分が、種子のもとである「葱坊主」に行ってしまいますから、
せっかくの葱坊主は、「ポキっ」と折って、捨ててしまいます。
今回収獲したものは、わざと葱坊主を成長させ
ネギの種子を取るために、立派なものに仕上げました。
葱坊主は、この後乾燥させ、9月に田んぼにまき
来年の「ネギ苗」を発芽させます。
そのネギ苗は、4月に「松本一本ねぎ苗」として
田んぼに定植し、育てていき、料理のたびに使います。
言うならば、もう来年の準備といったところでしょうか。
つい先日、なぎ苗の定植が終ったと思ったら
もうネギの種を取るのですから、サイクルは早いものです。
色々な作業が農家にはありますが、
季節に応じての様々作業は楽しくもあります。
今年もここまできました。
何となく、ホッとさせてくれる田舎ならではの、葱坊主です。
自分の子孫を残そうと、葱坊主を大きくしたネギ。

葱坊主をよく見ると、「種子」がたくさん付いています。
この種子を9月にまきます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月25日
にんにくを掘る・・・・・夏バテの防止に。
梅雨の中休み、
調度田んぼの土も柔らかくなったということで
にんにくを掘りました。
にんにくは、大好物で、都内にいた頃は
焼肉屋に行くと、必ずにんにくの「ホイル焼き」を
頼んで、焼肉もさることながら、
バターで焼いたホクホクのにんにくをいただくのが大好きでした。
にんにくは、青森県でしか栽培されていないのだろうと
タカをくくっていたのですが、昨年、ユータンして以来
我が家でにんにくを栽培しているのには、驚きでした。
焼肉屋さんで見かけるような「立派なにんにく」ではありませんが、
北信濃の地で越冬し、雪解け水を吸いながら
じっくりと大きくなった「北信濃産のにんにく」です。
いただくと、「味の濃さ」が際立ちます。
匂いも味も濃いです。
最近有名な「ホワイト六片」という種類と、
昭和30年代から、作り続け、種を翌年にまた植えつけるという
昔ながらの「地物のオリジナルにんにく」と、
最近話題の大振りな「無臭にんにく」の
3種類の栽培です。
「無臭にんにく」は、まだ成長途上ですから、
今日は、先に述べた2種類のにんにくを掘りました。
土が雨で柔らかいと思っていたのですが、
意外に力がいります。
2~3時間くらいで終るだろうとと思っていたのですが、
半日は、たっぷりとかかりました。
掘っていると、強烈なにんにくの匂いが、辺りに充満します。
このあと、掘ったものを干して、少しづついただいていきます。
スリおろしても良し。
ホイル焼きも良し。
これで夏場の田んぼでの力仕事をするにも
精が付きそうです。
暑い夏、夏野菜もいいですが、
にんにくのような「ピリッ」とパンチのある野菜もいいものです。
にんにくを掘る。
土の中でじっくりと育った。

土中のにんにく。
玉ねぎと違い、結構深いところに植わっている。

無臭にんにくの花。

一人での作業は、結構きつかったです。
もちろん、夜は、にんにくのホイル焼きで、冷たいビールです。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
調度田んぼの土も柔らかくなったということで
にんにくを掘りました。
にんにくは、大好物で、都内にいた頃は
焼肉屋に行くと、必ずにんにくの「ホイル焼き」を
頼んで、焼肉もさることながら、
バターで焼いたホクホクのにんにくをいただくのが大好きでした。
にんにくは、青森県でしか栽培されていないのだろうと
タカをくくっていたのですが、昨年、ユータンして以来
我が家でにんにくを栽培しているのには、驚きでした。
焼肉屋さんで見かけるような「立派なにんにく」ではありませんが、
北信濃の地で越冬し、雪解け水を吸いながら
じっくりと大きくなった「北信濃産のにんにく」です。
いただくと、「味の濃さ」が際立ちます。
匂いも味も濃いです。
最近有名な「ホワイト六片」という種類と、
昭和30年代から、作り続け、種を翌年にまた植えつけるという
昔ながらの「地物のオリジナルにんにく」と、
最近話題の大振りな「無臭にんにく」の
3種類の栽培です。
「無臭にんにく」は、まだ成長途上ですから、
今日は、先に述べた2種類のにんにくを掘りました。
土が雨で柔らかいと思っていたのですが、
意外に力がいります。
2~3時間くらいで終るだろうとと思っていたのですが、
半日は、たっぷりとかかりました。
掘っていると、強烈なにんにくの匂いが、辺りに充満します。
このあと、掘ったものを干して、少しづついただいていきます。
スリおろしても良し。
ホイル焼きも良し。
これで夏場の田んぼでの力仕事をするにも
精が付きそうです。
暑い夏、夏野菜もいいですが、
にんにくのような「ピリッ」とパンチのある野菜もいいものです。
にんにくを掘る。
土の中でじっくりと育った。

土中のにんにく。
玉ねぎと違い、結構深いところに植わっている。

無臭にんにくの花。

一人での作業は、結構きつかったです。
もちろん、夜は、にんにくのホイル焼きで、冷たいビールです。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月24日
栗の花の季節
梅雨らしい一日となった昨日、田んぼの見回りに出かけると
目に付きそして、鼻に付くのが「栗の花」です。
栗の花、花には、色々とありますが、
地味で毛虫のようなのが栗の花です。
毛虫のような「栗の花」ですが、
その特徴は、なんといってもその青臭い匂いです。
雨上がりのしっとりとした空気の中に
その青臭い栗の花の匂いは、かなり強烈ににおいます。
この毛虫のような花「栗の花が、落ちると梅雨が明け」と
祖母がよく昔言っていました。
栗の花は、梅雨ならではの風物詩のようですね。
我が家の田んぼがある、小布施橋周辺から、
小布施橋を渡って、小布施町内に入ると
この毛虫状の花を多数見かけます。
この満開の棒状の花は、「散る」というより「落ちる」のです。
「栗花落」と書いて「ついり」または、「つゆり」と読むそうです。
栗菓子の名前にあったり、姓にもあるようです。
なんとも、地味ですが、季節感溢れる花です。
梅雨時に見られる「栗の花」。
今しばらく楽しめそうです。
栗の木と棒状の栗の花。
小布施橋周辺に多く見かけます。

この毛虫状の花は、雌花。

フサフサという感じではない。
すすきの穂が出始めた頃の柔らかい感じに似ている。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
目に付きそして、鼻に付くのが「栗の花」です。
栗の花、花には、色々とありますが、
地味で毛虫のようなのが栗の花です。
毛虫のような「栗の花」ですが、
その特徴は、なんといってもその青臭い匂いです。
雨上がりのしっとりとした空気の中に
その青臭い栗の花の匂いは、かなり強烈ににおいます。
この毛虫のような花「栗の花が、落ちると梅雨が明け」と
祖母がよく昔言っていました。
栗の花は、梅雨ならではの風物詩のようですね。
我が家の田んぼがある、小布施橋周辺から、
小布施橋を渡って、小布施町内に入ると
この毛虫状の花を多数見かけます。
この満開の棒状の花は、「散る」というより「落ちる」のです。
「栗花落」と書いて「ついり」または、「つゆり」と読むそうです。
栗菓子の名前にあったり、姓にもあるようです。
なんとも、地味ですが、季節感溢れる花です。
梅雨時に見られる「栗の花」。
今しばらく楽しめそうです。
栗の木と棒状の栗の花。
小布施橋周辺に多く見かけます。

この毛虫状の花は、雌花。

フサフサという感じではない。
すすきの穂が出始めた頃の柔らかい感じに似ている。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月23日
紫玉ねぎの収獲
ここ数日雨が降り、ようやく梅雨らしい天気が続きます。
梅雨の合間を縫って、「紫玉ねぎ」の収獲を行ないました。
本来は、通常の黄色の信州玉ねぎと一緒に苗を定植し、
冬を過ごしたのですが、
今ひとつ、「紫玉ねぎ」が大きくならずにいたので、
しばらく置いておいたものです。
紫玉ねぎは、通常の玉ネギより、やや小ぶり。
収獲方法も、しばらく乾燥させる方法も同じです。
ただいただき方が違います。
こちらは、完全に「生食」専用。
スライスして、サラダに、または、ちょっとポン酢と鰹節を掛けて
酒のつまみにと、生でいただきます。
通常の信州玉ねぎももちろん今の時季は、「新玉ねぎ」ですから、
生でいただいてもベストなんですが、
紫玉ねぎは、獲れたてもしばらくおいたものも、
全て生でいただきます。
しばらく乾燥させていきますと、玉ねぎの皮に沿って、
紫色がより鮮やかになって行きます。
お弁当の彩にも最適な感じのサラダでいただく「玉ねぎ」なのです。
紫というと、他にも最近結構野菜で見かけるようになりました。
紫のキャベツ
紫のオクラ
紫のアスパラガス
等々
何れも味は、本来の野菜と代わり無いようですが
野菜の彩りは楽しめますよね。
栄養分は、オクラに関しては、「アントシアニン」という
紫色の要素の素が多いようですが、
他は余り代わりが無いようです。
これから、食卓に様々な色の野菜が並ぶようになります。
味はもちろんですが、
目で楽しむ・色で楽しむという季節の到来です。
彩りよく、バランスよく野菜を獲りたいものです。
紫玉ねぎ。皮の部分だけが紫色。

収獲して、結えて、玉ねぎハウスに掛けて・・・・・と
丸一日一人での作業でした。
夕方から雨が結構降りましたが、何とか間に合いました。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
梅雨の合間を縫って、「紫玉ねぎ」の収獲を行ないました。
本来は、通常の黄色の信州玉ねぎと一緒に苗を定植し、
冬を過ごしたのですが、
今ひとつ、「紫玉ねぎ」が大きくならずにいたので、
しばらく置いておいたものです。
紫玉ねぎは、通常の玉ネギより、やや小ぶり。
収獲方法も、しばらく乾燥させる方法も同じです。
ただいただき方が違います。
こちらは、完全に「生食」専用。
スライスして、サラダに、または、ちょっとポン酢と鰹節を掛けて
酒のつまみにと、生でいただきます。
通常の信州玉ねぎももちろん今の時季は、「新玉ねぎ」ですから、
生でいただいてもベストなんですが、
紫玉ねぎは、獲れたてもしばらくおいたものも、
全て生でいただきます。
しばらく乾燥させていきますと、玉ねぎの皮に沿って、
紫色がより鮮やかになって行きます。
お弁当の彩にも最適な感じのサラダでいただく「玉ねぎ」なのです。
紫というと、他にも最近結構野菜で見かけるようになりました。
紫のキャベツ
紫のオクラ
紫のアスパラガス
等々
何れも味は、本来の野菜と代わり無いようですが
野菜の彩りは楽しめますよね。
栄養分は、オクラに関しては、「アントシアニン」という
紫色の要素の素が多いようですが、
他は余り代わりが無いようです。
これから、食卓に様々な色の野菜が並ぶようになります。
味はもちろんですが、
目で楽しむ・色で楽しむという季節の到来です。
彩りよく、バランスよく野菜を獲りたいものです。
紫玉ねぎ。皮の部分だけが紫色。

収獲して、結えて、玉ねぎハウスに掛けて・・・・・と
丸一日一人での作業でした。
夕方から雨が結構降りましたが、何とか間に合いました。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月22日
「シソ」 あれこれパート2
農産物直売所「アグリ長沼」でも最近「シソの葉」を見かけるようになりました。
梅の季節、「梅漬け」に使うシソの葉です。
我が家のシソが、旬になるにはもうしばらく。
ちょっと放りっぱなしでいたので、草が随分と生えてしまい
草むしり兼間引きといった具合に手入れを施しました。
まだ本格的なシソにはなっていませんが、
こんな小さなシソの葉でも、
かなり強烈な「シソ特有の香り」がします。
青シソは、薬味として重宝されますが
赤シソは、専ら「梅漬け」専用。
前にもお話しましたが、
「シソジュース」も美味しいです。
青シソ・赤シソともに、」その特有の匂いは、食欲もそそります。
こういった効果抜群のシソは、日本古来からの和風の「ハーブ」です。
昔、祖母がお弁当やおにぎりが傷まないように
必ず「梅漬け」が入っていました。
夏場は傷みやすいですが、梅漬けの入ったご飯は大丈夫だとして、
夏場のご飯ものには、必ず梅漬けを入れていました。
梅には、殺菌作用・防腐作用はありませんから
その効果は、この「シソ」にあったのだと思います。
殺菌作用と防腐作用を兼ね、しかも食欲をそそり栄養価も豊富。
シソは、結構優れた和風ハーブです。
最近は、梅漬けのシソが余ってしまたため、
コマツナを湯がいて、鰹節を入れて、和えたものをアレンジして作っていただいています。
胃の中をアルコールで消毒し、さらに殺菌作用のある赤シソを
胃に入れれば、効果覿面???のはずは全く無いのですが、
夏場の食欲不振時には、結構いけそうです。
でも、どちらかというと僕の酒のつまみにピッタリ。
梅漬けというと結構脇役になりがちなシソですが、
脇役どころか、主役にもなりうる存在なのです。
今年もシソの季節。
昨年は、シソジュースにチャレンジしました。
新たなメニューがあれば、
今年も是非 「和風ハーブ」シソ を使ってみたいです。
まだ調べていないのですが、その効果はまだまだあると思われます。
地物をアレンジしてみるのもまた楽しいものです。
シソ特有の香りが既に周りに放っている。
収獲は、7月を予定。

腰の辺りの長さまで成長を待つ。
こちらの赤シソは、「ちりめんシソ」

こちらは、表がグリーン、裏が赤の「赤シソ」
正式名称は、分かりかねますが、「片面シソ」と呼んでいます。
この片面シソも梅漬けのシソとして使います。
種が市販されていないようなので、この「片面シソ」は自宅で種も取ります。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
梅の季節、「梅漬け」に使うシソの葉です。
我が家のシソが、旬になるにはもうしばらく。
ちょっと放りっぱなしでいたので、草が随分と生えてしまい
草むしり兼間引きといった具合に手入れを施しました。
まだ本格的なシソにはなっていませんが、
こんな小さなシソの葉でも、
かなり強烈な「シソ特有の香り」がします。
青シソは、薬味として重宝されますが
赤シソは、専ら「梅漬け」専用。
前にもお話しましたが、
「シソジュース」も美味しいです。
青シソ・赤シソともに、」その特有の匂いは、食欲もそそります。
こういった効果抜群のシソは、日本古来からの和風の「ハーブ」です。
昔、祖母がお弁当やおにぎりが傷まないように
必ず「梅漬け」が入っていました。
夏場は傷みやすいですが、梅漬けの入ったご飯は大丈夫だとして、
夏場のご飯ものには、必ず梅漬けを入れていました。
梅には、殺菌作用・防腐作用はありませんから
その効果は、この「シソ」にあったのだと思います。
殺菌作用と防腐作用を兼ね、しかも食欲をそそり栄養価も豊富。
シソは、結構優れた和風ハーブです。
最近は、梅漬けのシソが余ってしまたため、
コマツナを湯がいて、鰹節を入れて、和えたものをアレンジして作っていただいています。
胃の中をアルコールで消毒し、さらに殺菌作用のある赤シソを
胃に入れれば、効果覿面???のはずは全く無いのですが、
夏場の食欲不振時には、結構いけそうです。
でも、どちらかというと僕の酒のつまみにピッタリ。
梅漬けというと結構脇役になりがちなシソですが、
脇役どころか、主役にもなりうる存在なのです。
今年もシソの季節。
昨年は、シソジュースにチャレンジしました。
新たなメニューがあれば、
今年も是非 「和風ハーブ」シソ を使ってみたいです。
まだ調べていないのですが、その効果はまだまだあると思われます。
地物をアレンジしてみるのもまた楽しいものです。
シソ特有の香りが既に周りに放っている。
収獲は、7月を予定。

腰の辺りの長さまで成長を待つ。
こちらの赤シソは、「ちりめんシソ」

こちらは、表がグリーン、裏が赤の「赤シソ」
正式名称は、分かりかねますが、「片面シソ」と呼んでいます。
この片面シソも梅漬けのシソとして使います。
種が市販されていないようなので、この「片面シソ」は自宅で種も取ります。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月21日
かなり「ほけた」ズッキーニ
今年初めて植えた「ズキーニ」ですが、その成長振りには
目を見張るものがあります。
結構株を張るとは聞いていましたが、ここまで張るとは・・。
かぼちゃの仲間ですが、ツルが伸びて、
広範囲に広がるというのではなく
株がかなり広がり、その株の根元に「ズッキーニ」が実を付けます。
花も大振り。
いくつものズッキーニの実が、株の根元に実を付けています。
初物のズッキーニをいただくのももうすぐのようです。
裏の畑のトマトも、かなり実を付けて来ました。
こちらはこれから大きくなり、熟していくのですから
まだまだ時間が掛かりそうです。
ここ数日、雨がチラホラ降り、ようやく「梅雨なんだなあ」と
実感できる頃です。
この梅雨の雨を受けて、一気に大きくなっていく野菜たち。
本格的な夏野菜の勢ぞろいは7月上旬からでしょうか。
食卓に自家製のもので漬けたり、揚げたり炒めたりしたものが
上るのも間近。
でもまあ、先ずは、「生で」野菜本来の味をいただきましょう。
そのときは、りんごと同様
「丸かじり」で行きたいと思います。
結構大きなズッキーニの花。

株の根元に付いた「ズッキーニ」
結構たくさん付きました。

かなり「ほけた」ズッキーニ。
「ほける」とは長野の方言で、成長するという意味です。
方言だけは、長野での生活が、
高校生までだったからでしょうか苦手です。
近所の方と話をしていても、たまに????と分からなくなる言葉が
出てきます。
この「ほける」もその一つ。
方言は、広い長野でも、北信のなかでもかなり違うようです。
こちらを調べてみるのも面白そうですね。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
目を見張るものがあります。
結構株を張るとは聞いていましたが、ここまで張るとは・・。
かぼちゃの仲間ですが、ツルが伸びて、
広範囲に広がるというのではなく
株がかなり広がり、その株の根元に「ズッキーニ」が実を付けます。
花も大振り。
いくつものズッキーニの実が、株の根元に実を付けています。
初物のズッキーニをいただくのももうすぐのようです。
裏の畑のトマトも、かなり実を付けて来ました。
こちらはこれから大きくなり、熟していくのですから
まだまだ時間が掛かりそうです。
ここ数日、雨がチラホラ降り、ようやく「梅雨なんだなあ」と
実感できる頃です。
この梅雨の雨を受けて、一気に大きくなっていく野菜たち。
本格的な夏野菜の勢ぞろいは7月上旬からでしょうか。
食卓に自家製のもので漬けたり、揚げたり炒めたりしたものが
上るのも間近。
でもまあ、先ずは、「生で」野菜本来の味をいただきましょう。
そのときは、りんごと同様
「丸かじり」で行きたいと思います。
結構大きなズッキーニの花。

株の根元に付いた「ズッキーニ」
結構たくさん付きました。

かなり「ほけた」ズッキーニ。
「ほける」とは長野の方言で、成長するという意味です。
方言だけは、長野での生活が、
高校生までだったからでしょうか苦手です。
近所の方と話をしていても、たまに????と分からなくなる言葉が
出てきます。
この「ほける」もその一つ。
方言は、広い長野でも、北信のなかでもかなり違うようです。
こちらを調べてみるのも面白そうですね。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
美味しい信州ならではの産直サイト
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月20日
ナスのトゲ
ナスの成長が、順調です。
なすには、「ヘタ」の部分に「トゲ」がありますが、
葉っぱや、茎にも「トゲ」があります。
キュウリのトゲと違って、結構硬くて刺さると痛いものです。
たまに、手に刺さると、抜くのに、時間が掛かります。
厄介者の「トゲ」ですが、
茄子の実・葉っぱ・茎とトゲがあるということは、
「食べられまい」とするナスの抵抗でしょうか。
ナスが成長し、実をつけ、その実が熟し、
落下させ、次の年に、その熟したナスの「種」が発芽し、といった具合に
自分の子供である「茄子」を残そうとする
本能でしょう。
トゲがあるものは、他にキュウリ。
こちらは、「痛い」というほどのものではありあません。
「トゲ」が危険であるということから、
「トゲなし」の野菜の研究もされていますが、
そこまでしなくとも・・・・と思います。
「野菜の本能」をそぎとるようなものですから。
専門分野ではありませんから、分かりかねますが、
「遺伝子組み換え」の植物などバイオテクノロジーの
進歩により、様々な野菜が季節を問わず
容易に大量生産が可能となっている昨今です。
オッチョコチョイの僕ですから、今年もナスのトゲが手に刺さり、
ヒイヒイ言うのかもしれません。
まあ、自然の一部をお裾分けしてもらっているという
「共生」の考え方も必要でしょう。
トゲのある葉っぱを見つつ、
ノンビリと丸ナスが出来るのを待ちたいと思います。
成長途上の今年の茄子。
丸茄子に加え、長ナスも茄子料理の定番。

ナスの葉っぱのトゲ。
よく見ると、結構しっかりとしたトゲです。

キュウリのトゲ。
進化してここまでになったのかもしれません。
太古の昔は、きゅうりは鋭利なトゲで覆われていたのかも・・・・・

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
なすには、「ヘタ」の部分に「トゲ」がありますが、
葉っぱや、茎にも「トゲ」があります。
キュウリのトゲと違って、結構硬くて刺さると痛いものです。
たまに、手に刺さると、抜くのに、時間が掛かります。
厄介者の「トゲ」ですが、
茄子の実・葉っぱ・茎とトゲがあるということは、
「食べられまい」とするナスの抵抗でしょうか。
ナスが成長し、実をつけ、その実が熟し、
落下させ、次の年に、その熟したナスの「種」が発芽し、といった具合に
自分の子供である「茄子」を残そうとする
本能でしょう。
トゲがあるものは、他にキュウリ。
こちらは、「痛い」というほどのものではありあません。
「トゲ」が危険であるということから、
「トゲなし」の野菜の研究もされていますが、
そこまでしなくとも・・・・と思います。
「野菜の本能」をそぎとるようなものですから。
専門分野ではありませんから、分かりかねますが、
「遺伝子組み換え」の植物などバイオテクノロジーの
進歩により、様々な野菜が季節を問わず
容易に大量生産が可能となっている昨今です。
オッチョコチョイの僕ですから、今年もナスのトゲが手に刺さり、
ヒイヒイ言うのかもしれません。
まあ、自然の一部をお裾分けしてもらっているという
「共生」の考え方も必要でしょう。
トゲのある葉っぱを見つつ、
ノンビリと丸ナスが出来るのを待ちたいと思います。
成長途上の今年の茄子。
丸茄子に加え、長ナスも茄子料理の定番。

ナスの葉っぱのトゲ。
よく見ると、結構しっかりとしたトゲです。

キュウリのトゲ。
進化してここまでになったのかもしれません。
太古の昔は、きゅうりは鋭利なトゲで覆われていたのかも・・・・・

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月19日
イチゴの終了
露地ものの「イチゴ」が終了しました。
今年も、「生」でそのままいただくことも多かったですが、
やはりメインは、「自家製のイチゴジャム」です。
都合、3回煮込みました。
みんな小腹が空いたときに、ちょっとパンに塗って
食べています。
イチゴは、苗を10株ほど残して、全て引っこ抜きました。
その10株から、「ランナー」といって
本体のイチゴの苗から、つる状のものが延びてきて、
その「つる状のもの」に「根」が出て、定着します。
そうやって、10個ほどの残った苗から、いくつもの「ランナー」が伸びて、
いくつもの「イチゴ苗の株」が出来ます。
その定着した「ランナー」の小さな苗が、秋を過ぎ、冬場は
雪の下で越冬し、春先に「イチゴ苗」として
畝に定植し直し、ひとり立ちします。
毎年。この繰り返しをします。
イチゴが不作の場合や、余り出来がよくないイチゴが多い場合は、
近所の農家から、好調な苗を分けてもらったり、
イチゴ苗を購入したりします。
今年は、まあまあの出来でしたから
我が家の苗を使ってランナーを這わせ、来年の苗作りをします。
来年もイチゴジャムを作ろうかと思いますが
今年、近所のおばさんが我が家のイチゴを使って作ってくれた
「バアロア」が最高に美味しかったです。
しかし、非常に手間ひまが掛かる様子。
「イチゴジャムほど時間が掛からないわよ」と仰ってましたが、
「次回の収獲の分で作ろう」と考えているうちに、
イチゴの時期が過ぎてしまいました。
来年は、「ババロア」に挑戦しましょう。
残ったイチゴ苗。ランナーを這わせます。

引き抜いたイチゴ苗。
一年間ご苦労様でした。
このあとこの苗は、「緑肥」として田んぼに使われます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
今年も、「生」でそのままいただくことも多かったですが、
やはりメインは、「自家製のイチゴジャム」です。
都合、3回煮込みました。
みんな小腹が空いたときに、ちょっとパンに塗って
食べています。
イチゴは、苗を10株ほど残して、全て引っこ抜きました。
その10株から、「ランナー」といって
本体のイチゴの苗から、つる状のものが延びてきて、
その「つる状のもの」に「根」が出て、定着します。
そうやって、10個ほどの残った苗から、いくつもの「ランナー」が伸びて、
いくつもの「イチゴ苗の株」が出来ます。
その定着した「ランナー」の小さな苗が、秋を過ぎ、冬場は
雪の下で越冬し、春先に「イチゴ苗」として
畝に定植し直し、ひとり立ちします。
毎年。この繰り返しをします。
イチゴが不作の場合や、余り出来がよくないイチゴが多い場合は、
近所の農家から、好調な苗を分けてもらったり、
イチゴ苗を購入したりします。
今年は、まあまあの出来でしたから
我が家の苗を使ってランナーを這わせ、来年の苗作りをします。
来年もイチゴジャムを作ろうかと思いますが
今年、近所のおばさんが我が家のイチゴを使って作ってくれた
「バアロア」が最高に美味しかったです。
しかし、非常に手間ひまが掛かる様子。
「イチゴジャムほど時間が掛からないわよ」と仰ってましたが、
「次回の収獲の分で作ろう」と考えているうちに、
イチゴの時期が過ぎてしまいました。
来年は、「ババロア」に挑戦しましょう。
残ったイチゴ苗。ランナーを這わせます。

引き抜いたイチゴ苗。
一年間ご苦労様でした。
このあとこの苗は、「緑肥」として田んぼに使われます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月18日
「しろり」の漬物に備えて・・・・白瓜の種を蒔く
大分遅くなってしまいましたが、「白瓜」の種を蒔きました。
「しろ瓜」ですが、この辺りでは、「しろり」と呼んでいます。
夏場に、漬けていただき、夏の漬物といえば、北信ではおの「しろり」の漬物です。
苗木を販売しているお店でも、夏野菜の苗木の販売が一息し
今は、この「しろり」の苗木が結構店頭に並んでいます。
信州では、漬物といえば野沢菜を思い浮かべますが、
漬物は地域によっても家庭によっても様々です。
例えば、同じ「瓜」を使った漬物ですと、
一般にすぐに「奈良漬け」を思い浮かべますが
ここ北信では、瓜を使った場合、「しろり」の塩漬けでないでしょうか。
そう難しい漬物ではなく、いわゆる「浅漬け」です。
奈良漬けの場合、干したり、塩で一度漬けたりと
漬け込むのが大変ですし、「酒粕」を調達しての奈良漬けは
結構手間ひまかかります。
しろりの浅漬けの場合、塩を振って、醤油ベースの浅漬けのもとを
入れておくだけです。
信州では、酒蔵が非常にたくさんありますから、
その酒蔵から酒粕を調達して、「奈良漬」にすると合点がいくのですが、
農家が多いこの地域では、忙しがって手間ひまが掛けられず、
簡単に漬物をいただけることから
この「しろり」の浅漬けが発達したのかもしれません。
こうした「瓜」の漬物一つとっても、
奈良漬にしないのか、即席の漬物にするのか、
調べてみると面白いものです。
信州の北部、「北信地域」といっても、かなり広い地域で、
千曲川を挟んで、東の「河東」地域の旧高井郡と西の旧水内郡
水内郡のなかでも、中条村や信州新町のある西山地方もあれば
栄村も旧水内郡で、食文化も多種多様なはずです。
それは、信州名物「おやき」が北信の西山地方では、「焼いたもの」ですし、
我が家の豊野町では、「蒸かしたもの」ですし、
はたまた「油で揚げたもの」があり、
信州名物「おやき」一つとっても、
地域の背景を色濃く反映した特性そのもので、
地域ならではの「食文化」です。
そう考えると、この「しろり」こと「瓜」を使っての漬物も
こうまで店頭で、販売されているからには、
北信地域で様々な漬け方でアレンジされて、
漬物の材料として使われているかもしれません。
こういった地域地域の食生活「風土食」を調べてみるのも面白いものです。
今年の夏は、この「しろり」を使っての食文化も
長野県の北信地域だけでなく、
日本各地のものを調べられたらなあと考えています。
各地の「瓜の漬け方」があれば是非教えてください。
我が家で使った「しろり」の種。
この時季、種屋さんいは、「瓜」の種がたくさんあります。
松本系の種もありました。
松本では、また違った「瓜」のいただき方をするのでしょうか。
地域地域によって、「夏の瓜」の食べ方も様々です。

昨年8月の我が家の「しろり」の漬けた際の写真。
終ったら、漬けていただくの繰り返しが夏場行なわれる。

昨年の「しろり」の漬物の写真。
冬場の野沢菜と同様、お茶請けに最適。
お茶も進むが、夏場食欲が無いときにお茶漬けにも最適。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
「しろ瓜」ですが、この辺りでは、「しろり」と呼んでいます。
夏場に、漬けていただき、夏の漬物といえば、北信ではおの「しろり」の漬物です。
苗木を販売しているお店でも、夏野菜の苗木の販売が一息し
今は、この「しろり」の苗木が結構店頭に並んでいます。
信州では、漬物といえば野沢菜を思い浮かべますが、
漬物は地域によっても家庭によっても様々です。
例えば、同じ「瓜」を使った漬物ですと、
一般にすぐに「奈良漬け」を思い浮かべますが
ここ北信では、瓜を使った場合、「しろり」の塩漬けでないでしょうか。
そう難しい漬物ではなく、いわゆる「浅漬け」です。
奈良漬けの場合、干したり、塩で一度漬けたりと
漬け込むのが大変ですし、「酒粕」を調達しての奈良漬けは
結構手間ひまかかります。
しろりの浅漬けの場合、塩を振って、醤油ベースの浅漬けのもとを
入れておくだけです。
信州では、酒蔵が非常にたくさんありますから、
その酒蔵から酒粕を調達して、「奈良漬」にすると合点がいくのですが、
農家が多いこの地域では、忙しがって手間ひまが掛けられず、
簡単に漬物をいただけることから
この「しろり」の浅漬けが発達したのかもしれません。
こうした「瓜」の漬物一つとっても、
奈良漬にしないのか、即席の漬物にするのか、
調べてみると面白いものです。
信州の北部、「北信地域」といっても、かなり広い地域で、
千曲川を挟んで、東の「河東」地域の旧高井郡と西の旧水内郡
水内郡のなかでも、中条村や信州新町のある西山地方もあれば
栄村も旧水内郡で、食文化も多種多様なはずです。
それは、信州名物「おやき」が北信の西山地方では、「焼いたもの」ですし、
我が家の豊野町では、「蒸かしたもの」ですし、
はたまた「油で揚げたもの」があり、
信州名物「おやき」一つとっても、
地域の背景を色濃く反映した特性そのもので、
地域ならではの「食文化」です。
そう考えると、この「しろり」こと「瓜」を使っての漬物も
こうまで店頭で、販売されているからには、
北信地域で様々な漬け方でアレンジされて、
漬物の材料として使われているかもしれません。
こういった地域地域の食生活「風土食」を調べてみるのも面白いものです。
今年の夏は、この「しろり」を使っての食文化も
長野県の北信地域だけでなく、
日本各地のものを調べられたらなあと考えています。
各地の「瓜の漬け方」があれば是非教えてください。
我が家で使った「しろり」の種。
この時季、種屋さんいは、「瓜」の種がたくさんあります。
松本系の種もありました。
松本では、また違った「瓜」のいただき方をするのでしょうか。
地域地域によって、「夏の瓜」の食べ方も様々です。

昨年8月の我が家の「しろり」の漬けた際の写真。
終ったら、漬けていただくの繰り返しが夏場行なわれる。
昨年の「しろり」の漬物の写真。
冬場の野沢菜と同様、お茶請けに最適。
お茶も進むが、夏場食欲が無いときにお茶漬けにも最適。
善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全 減農薬有機栽培の新鮮野菜・・・・「旬のお野菜セット」
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月17日
丸茄子・・・・・旬を前に、6月の丸茄子
なすが随分と大きくなってきました。
我が家の栽培は、北信ならではの「丸茄子」を中心としています。
茄子といえば、長ナスのことを指すのが一般的ですが、
北信ではやはり「丸茄子」でしょう。
信州名物の「おやき」の具にします。
丸ナスを1センチ幅にスライスして、
丸ナスの間に味噌餡をはさみ、蒸かします。
お焼きは、「蒸かす派」を「焼く派」あと「油で揚げる派」が
ありますが、ふと思ったのですが
「焼く派」と「油で揚げる派」のおやきは、丸ナスを使った場合
中の具の茄子に火が入るのかなあと考えてしまいました。
他に、丸ナスをこれまた1.5センチ幅にスライスして
油で焼いて、生姜醤油か辛子醤油でいただくと
また食欲が進みますし、お酒のつまみにも最高です。
これを豊野町の浅野地区のあたりでは
「なすのしん焼き」と呼んでいます。
でも、ナスは、油を結構吸いますので、
僕のような、「おおまくらい」は注意しませんと・・・・。
でも、たっぷりの油を使ったほうが
ナスの「しん焼き」は美味しいです。
今日は、1つだけ実った丸茄子の初物をいただきました。
やはり上々。
お焼きの具にもグッド。
しん焼きにもグッド。
丸ナスは、やはり優れもの。
ただ一般料理の本には、丸ナスの調理方法は、載っていません。
ナスは、長ナスを指すようです。
信州ならではの、「丸茄子」
色々とアレンジしつつ、
いただき方をこの夏ご紹介していきたいと思います。
実が付き始めた丸茄子。
もう少し大きくなったところを「漬物」にしても美味しい。

もう少し茂って、田んぼ全体が、茄子に覆われた頃が
ナスの獲れ時。旬までもう少し。

初物の丸茄子。
一つだけ先に成長していました。
黒い艶とヘタのトゲが特徴です。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
我が家の栽培は、北信ならではの「丸茄子」を中心としています。
茄子といえば、長ナスのことを指すのが一般的ですが、
北信ではやはり「丸茄子」でしょう。
信州名物の「おやき」の具にします。
丸ナスを1センチ幅にスライスして、
丸ナスの間に味噌餡をはさみ、蒸かします。
お焼きは、「蒸かす派」を「焼く派」あと「油で揚げる派」が
ありますが、ふと思ったのですが
「焼く派」と「油で揚げる派」のおやきは、丸ナスを使った場合
中の具の茄子に火が入るのかなあと考えてしまいました。
他に、丸ナスをこれまた1.5センチ幅にスライスして
油で焼いて、生姜醤油か辛子醤油でいただくと
また食欲が進みますし、お酒のつまみにも最高です。
これを豊野町の浅野地区のあたりでは
「なすのしん焼き」と呼んでいます。
でも、ナスは、油を結構吸いますので、
僕のような、「おおまくらい」は注意しませんと・・・・。
でも、たっぷりの油を使ったほうが
ナスの「しん焼き」は美味しいです。
今日は、1つだけ実った丸茄子の初物をいただきました。
やはり上々。
お焼きの具にもグッド。
しん焼きにもグッド。
丸ナスは、やはり優れもの。
ただ一般料理の本には、丸ナスの調理方法は、載っていません。
ナスは、長ナスを指すようです。
信州ならではの、「丸茄子」
色々とアレンジしつつ、
いただき方をこの夏ご紹介していきたいと思います。
実が付き始めた丸茄子。
もう少し大きくなったところを「漬物」にしても美味しい。

もう少し茂って、田んぼ全体が、茄子に覆われた頃が
ナスの獲れ時。旬までもう少し。

初物の丸茄子。
一つだけ先に成長していました。
黒い艶とヘタのトゲが特徴です。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月16日
坊っちゃんかぼちゃ その2
入梅は、早かったものの
なかなか本格的な梅雨らしいお天気とならない今日この頃です。
過度の雨も困ったものですが
こう「空梅雨」のような状態も農家にとっては困ったものです。
でも天気予報を聞いていると、
「空梅雨」ではないといっていますが・・・・。
かぼちゃ畑の「坊っちゃんかぼちゃ」が随分と大きくなりました。
結構、繁ってきて畑全体が、かぼちゃで覆われ始めました。
昨年のブログを見ると、もう少し茂っていたような気がしますが
今年は雨が少ないせいでしょうか?もうひとつといったところです。
もう少し「お湿り」が欲しいところです。
しかし、「かぼちゃ」の実は、もうちゃんと付いていました。
まだ手のひらに乗るくらいですが、
ちゃんと「かぼちゃ」の面構えをしています。
来月頭くらいから収獲が可能になると思われます。
徐々に、夏野菜の顔ぶれが揃ってきました。
信州のしかも「北信」ならではの「丸茄子」も順調です。
農産物直売所「アグリ長沼」でも、これまた信州ならではの
夏の漬物の材料「しろ瓜」の苗も並び始めました。
夏といえば、食欲が本来は無くなるのでしょうが、
様々な夏野菜が登場する夏だからこそ、
色々な「地物」の夏野菜をいただきたいものです。
色々とアレンジできますから、料理の本を読むのが
楽しくなるのもこの季節です。
待ち遠しい季節の到来です。
目下の悩みは、また食欲が出てきて体重が増えたらどうしましょう??
長野に戻ってきて、スーツが「Y体」が「A 体」に変わってしまいました。
野菜シーズンの到来でAB体になるのも、現実味があるかもしれません。
もうかぼちゃの形をした小さな「実」があちこちで付いています。

まだ本当に小さい坊っちゃんかぼちゃの実です。
坊っちゃんかぼちゃですから、そう大きくはなりませんが
まだまだ太陽の光を浴びて育たなければならないようです。

かぼちゃ畑全体が、茂って覆われるようになりました。

なかなか本格的な梅雨らしいお天気とならない今日この頃です。
過度の雨も困ったものですが
こう「空梅雨」のような状態も農家にとっては困ったものです。
でも天気予報を聞いていると、
「空梅雨」ではないといっていますが・・・・。
かぼちゃ畑の「坊っちゃんかぼちゃ」が随分と大きくなりました。
結構、繁ってきて畑全体が、かぼちゃで覆われ始めました。
昨年のブログを見ると、もう少し茂っていたような気がしますが
今年は雨が少ないせいでしょうか?もうひとつといったところです。
もう少し「お湿り」が欲しいところです。
しかし、「かぼちゃ」の実は、もうちゃんと付いていました。
まだ手のひらに乗るくらいですが、
ちゃんと「かぼちゃ」の面構えをしています。
来月頭くらいから収獲が可能になると思われます。
徐々に、夏野菜の顔ぶれが揃ってきました。
信州のしかも「北信」ならではの「丸茄子」も順調です。
農産物直売所「アグリ長沼」でも、これまた信州ならではの
夏の漬物の材料「しろ瓜」の苗も並び始めました。
夏といえば、食欲が本来は無くなるのでしょうが、
様々な夏野菜が登場する夏だからこそ、
色々な「地物」の夏野菜をいただきたいものです。
色々とアレンジできますから、料理の本を読むのが
楽しくなるのもこの季節です。
待ち遠しい季節の到来です。
目下の悩みは、また食欲が出てきて体重が増えたらどうしましょう??
長野に戻ってきて、スーツが「Y体」が「A 体」に変わってしまいました。
野菜シーズンの到来でAB体になるのも、現実味があるかもしれません。
もうかぼちゃの形をした小さな「実」があちこちで付いています。

まだ本当に小さい坊っちゃんかぼちゃの実です。
坊っちゃんかぼちゃですから、そう大きくはなりませんが
まだまだ太陽の光を浴びて育たなければならないようです。

かぼちゃ畑全体が、茂って覆われるようになりました。

2008年06月15日
スティックセニョールでアレコレ 第2弾
アスパラガスの時季が終わり、我が家で専らいただいているのが
茎ブロッコリー「スティックセニョール」です。
ブロッコリーは、「花」を茹でていただきますが
「スティックセニョール」は、花ももちろんいただきますが
「茎」の部分をいただきます。
スティックセニョールの場合、茎の部分は、
アスパラガス風味で、どちらかというと
「花」より「茎」の方が美味しくいただけます。
料理方法も、アスパラガスと同じで
茹でて、塩をふってマヨネーズをかけたり
ベーコンで巻いたり、アスパラガスと調理方法は一緒です。
以前にもお話しましたが、
スティックセニョールは、
ブロッコリーと中国野菜のカイランを掛け合わせたもので、
もともと日本で開発された品種でした。
因みに「スティックセニョール」という名前は、
「サカタのタネ」での呼び方で、
これが「種のタキイ」ですと、「グリーンボイス」と呼ばれます。
ですから、種の会社によって、呼び方が違うので、
正式な固有名詞ではないようですが、
最近は、「スティックセニョール」でスーパーで見かけるようになりました。
日本での開発後、国内市場ではあまり受け入れられることがなく、
アメリカに輸出されたところ、栄養価での高い評価もあり、
予想外に人気が出たのです。
その後、日本に逆輸入される形で帰国を果たし
出回るようになり始めました。
ブロッコリーの仲間では、あと
「ブロッコリースプラウト」も栄養価もあり、話題を呼んでいます。
更に「はなっこりー」という山口県の農業試験場で開発され
山口県では、かなりメジャーなブロッコリーの仲間の野菜もあります。
野菜も新しい品種が出回ります。
色々な野菜、それぞれ味の長所がありますから
いただくのは楽しいものです。
新しい野菜が全ていいとは思いませんが、
昔ながらの伝統的な北信地方の「丸茄子」に加え
こういった新品種などをご紹介していきたいと思います。
花はもちろん、「茎」の部分がアスパラガス風で美味しい
スティックセニョール。


ブロッコリーは、中心の花の部分を成長させいただく。

中心に一つだけ、花が咲くブロッコリーと違い
スティックセニョールは、脇から伸びる
「茎」の部分を中心にいただきます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
茎ブロッコリー「スティックセニョール」です。
ブロッコリーは、「花」を茹でていただきますが
「スティックセニョール」は、花ももちろんいただきますが
「茎」の部分をいただきます。
スティックセニョールの場合、茎の部分は、
アスパラガス風味で、どちらかというと
「花」より「茎」の方が美味しくいただけます。
料理方法も、アスパラガスと同じで
茹でて、塩をふってマヨネーズをかけたり
ベーコンで巻いたり、アスパラガスと調理方法は一緒です。
以前にもお話しましたが、
スティックセニョールは、
ブロッコリーと中国野菜のカイランを掛け合わせたもので、
もともと日本で開発された品種でした。
因みに「スティックセニョール」という名前は、
「サカタのタネ」での呼び方で、
これが「種のタキイ」ですと、「グリーンボイス」と呼ばれます。
ですから、種の会社によって、呼び方が違うので、
正式な固有名詞ではないようですが、
最近は、「スティックセニョール」でスーパーで見かけるようになりました。
日本での開発後、国内市場ではあまり受け入れられることがなく、
アメリカに輸出されたところ、栄養価での高い評価もあり、
予想外に人気が出たのです。
その後、日本に逆輸入される形で帰国を果たし
出回るようになり始めました。
ブロッコリーの仲間では、あと
「ブロッコリースプラウト」も栄養価もあり、話題を呼んでいます。
更に「はなっこりー」という山口県の農業試験場で開発され
山口県では、かなりメジャーなブロッコリーの仲間の野菜もあります。
野菜も新しい品種が出回ります。
色々な野菜、それぞれ味の長所がありますから
いただくのは楽しいものです。
新しい野菜が全ていいとは思いませんが、
昔ながらの伝統的な北信地方の「丸茄子」に加え
こういった新品種などをご紹介していきたいと思います。
花はもちろん、「茎」の部分がアスパラガス風で美味しい
スティックセニョール。


ブロッコリーは、中心の花の部分を成長させいただく。

中心に一つだけ、花が咲くブロッコリーと違い
スティックセニョールは、脇から伸びる
「茎」の部分を中心にいただきます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月14日
トマトの枝を挿し木に
トマトがかなり大きくなってきました。
そのトマトの勢いに任せて、伸び放題にするのでなく、
伸びていく枝を、2つくらいにしぼり、
後の脇から出て伸び始めた「芽」は、
もったいないような気がしますが、切捨て、
無造作に伸びるのでなく伸びていくのを2つの枝に絞ってあげます。
りんごや桃の摘果で、収獲出来る「実」を選別し、
間引いていくように、トマトの枝も伸びて
将来的に、たくさん実を付けてくれそうな有望なもののみ残して
後の枝は落とすというわけです。
この選別により、「振り落とされた枝」を使って
「挿し木」をします。
トマトは、こうしていわゆる「枝」を挿し木にしておくと
その枝に「根っこ」が生えてきて、
小さな「苗」に変身します。
今時分に苗を作るわけですから、これは夏どりのトマトというより
秋から晩秋向けのトマトといったところでしょうか。
時季をずらして植えてあげることにより、
トマトの苗にも寿命がありますから、
早獲り用や遅い時季の収穫用といった具合に
違った苗から、比較的長い期間収獲が可能となります。
今までは、トマトの種を遅く蒔いて、
遅く収獲するための「苗」を作っていたのですが、
今年は忙しがっていて、すっかり出来ませんでした。
今年初めてのトマトの挿し木の挑戦です。
さて、根付くものやら・・・・・。
小学校の頃に、大輪の菊の挿し木を先生から教わりました。
ですから、挿し木の原理は、子供の頃から知っていますが、
野菜での挑戦は初めて・・・・。
不安げながらも、期待は大きいです。
トマトの枝を挿し木。

トマトの枝。
この先に根が付き、速成の「トマト苗」となります。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
そのトマトの勢いに任せて、伸び放題にするのでなく、
伸びていく枝を、2つくらいにしぼり、
後の脇から出て伸び始めた「芽」は、
もったいないような気がしますが、切捨て、
無造作に伸びるのでなく伸びていくのを2つの枝に絞ってあげます。
りんごや桃の摘果で、収獲出来る「実」を選別し、
間引いていくように、トマトの枝も伸びて
将来的に、たくさん実を付けてくれそうな有望なもののみ残して
後の枝は落とすというわけです。
この選別により、「振り落とされた枝」を使って
「挿し木」をします。
トマトは、こうしていわゆる「枝」を挿し木にしておくと
その枝に「根っこ」が生えてきて、
小さな「苗」に変身します。
今時分に苗を作るわけですから、これは夏どりのトマトというより
秋から晩秋向けのトマトといったところでしょうか。
時季をずらして植えてあげることにより、
トマトの苗にも寿命がありますから、
早獲り用や遅い時季の収穫用といった具合に
違った苗から、比較的長い期間収獲が可能となります。
今までは、トマトの種を遅く蒔いて、
遅く収獲するための「苗」を作っていたのですが、
今年は忙しがっていて、すっかり出来ませんでした。
今年初めてのトマトの挿し木の挑戦です。
さて、根付くものやら・・・・・。
小学校の頃に、大輪の菊の挿し木を先生から教わりました。
ですから、挿し木の原理は、子供の頃から知っていますが、
野菜での挑戦は初めて・・・・。
不安げながらも、期待は大きいです。
トマトの枝を挿し木。

トマトの枝。
この先に根が付き、速成の「トマト苗」となります。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月13日
露地ものキュウリ
露地ものキュウリの収獲がスタートしています。
まだ「ビシッ」ときまっていなくて、
ちょっと曲がっていたりして、形はいびつですが
味は、露地ものならではの「濃厚な味」が楽しめます。
キュウリは、ツルがありますが、インゲン豆のように
ツルの力が強くて、自力でツルを絡めて、
棚の上に上がっていくと言う事が出来ません。
ツルを伸ばすのですが、何となく頼り気の無いツルです。
そう考えると、キュウリですとか、「瓜」の仲間は、
もともと地面に這って伸びていく習性のものですから
やむを得ないのかもしれません。
信州では、夏場に「しろ瓜」を漬けますが、この「瓜の仲間」も地面を這います。
「地這いきゅり」という種類があるくらいですから、
地面を這う程度のツルの伸びの強さなのかもしれません。
そんな何となく頼り気の無いように見える「きゅうり」ですが、
露地ものですから、太陽の光を燦々と浴びています。
太陽の光を浴びた、露地ものは、「トゲ」もありますし、
ニオイもキュウリ独特のにおいが強くします。
これから徐々に夏野菜も収獲が始まります。
信州北信濃 坂爪農園で収獲される夏野菜を徐々にご紹介してまいりたいと思います。
ちょっと曲がっていたり、そこはご愛嬌。

今日もいいお天気。
太陽の光を浴びて育つ健康キュウリです。

上に伸びようとしますが、インゲン豆のように強力な力で上っていけませんから、
棚に結えて、ツルが上っていくのをお助けします。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
まだ「ビシッ」ときまっていなくて、
ちょっと曲がっていたりして、形はいびつですが
味は、露地ものならではの「濃厚な味」が楽しめます。
キュウリは、ツルがありますが、インゲン豆のように
ツルの力が強くて、自力でツルを絡めて、
棚の上に上がっていくと言う事が出来ません。
ツルを伸ばすのですが、何となく頼り気の無いツルです。
そう考えると、キュウリですとか、「瓜」の仲間は、
もともと地面に這って伸びていく習性のものですから
やむを得ないのかもしれません。
信州では、夏場に「しろ瓜」を漬けますが、この「瓜の仲間」も地面を這います。
「地這いきゅり」という種類があるくらいですから、
地面を這う程度のツルの伸びの強さなのかもしれません。
そんな何となく頼り気の無いように見える「きゅうり」ですが、
露地ものですから、太陽の光を燦々と浴びています。
太陽の光を浴びた、露地ものは、「トゲ」もありますし、
ニオイもキュウリ独特のにおいが強くします。
これから徐々に夏野菜も収獲が始まります。
信州北信濃 坂爪農園で収獲される夏野菜を徐々にご紹介してまいりたいと思います。
ちょっと曲がっていたり、そこはご愛嬌。

今日もいいお天気。
太陽の光を浴びて育つ健康キュウリです。

上に伸びようとしますが、インゲン豆のように強力な力で上っていけませんから、
棚に結えて、ツルが上っていくのをお助けします。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月12日
新玉ねぎの収獲
梅雨の中休みの一日、玉ねぎの収獲を行ないました。
晩秋に、たまねぎの苗を田んぼに定植し、雪の下で過ごし、
雪解けと同時に、一気に雪解け水をたっぷりと吸い
大きくなった玉ねぎです。
去年から、僕も玉ねぎの収獲に参加していますが
今年の出来は、「大玉」が多い気がします。
他の果実は大玉は、重宝されますが、
玉ねぎは、大きすぎると、料理する際に思いますが、
扱いに困ってしまい、大玉の人気はいまひとつ。
でも、新玉ネギの大玉を、スライスして、サッと水で洗い、
花カツオとポン酢でいただくと、酒のつまみには、
この上ない美味さです。
生でスライスしての美味しさは、新玉ねぎならではですから
是非、試しいただきたいと思います。
玉ねぎは、田んぼに、深く植わっていませんから、
結構簡単に収獲できます。
ただその後が大変。
玉ねぎを、6個程度束ね、紐で結わえます。
その結えた、玉ねぎを今度は、車に積み込み、
家の裏にある「玉ねぎハウス」で干すために、吊るします。
結構手間が掛かる作業で、
今年も2名のお手伝いを借りての作業です。
更に、一日玉ねぎと触れていたせいか、衣服にも体にも
猛烈な玉ねぎのニオイ。
強烈なニオイに惹かれたわけでは無いでしょうが??、
田んぼで玉ねぎを収獲していたら、
近くで工事をしていたオジサンから、
新玉ねぎを譲って欲しいと
玉ねぎ獲りの見学を兼ねながら集めってくれました。
これから1年間、今日収獲した玉ねぎをいただいていきます。
これから収獲の新じゃがと、煮込んでもまた美味しい。
そう考えると、手間は掛かりますが、梅雨の合間の収獲は、
農家にとっては、慶びです。
田んぼに植わっている玉ねぎ。
結構簡単に抜けます。

抜いた玉ねぎをズラッと並べる。
左側のように、玉ねぎハウスで干せるように、
紐で結える。

収獲した玉ねぎは、自宅裏の玉ねぎハウスまで運ぶ。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
晩秋に、たまねぎの苗を田んぼに定植し、雪の下で過ごし、
雪解けと同時に、一気に雪解け水をたっぷりと吸い
大きくなった玉ねぎです。
去年から、僕も玉ねぎの収獲に参加していますが
今年の出来は、「大玉」が多い気がします。
他の果実は大玉は、重宝されますが、
玉ねぎは、大きすぎると、料理する際に思いますが、
扱いに困ってしまい、大玉の人気はいまひとつ。
でも、新玉ネギの大玉を、スライスして、サッと水で洗い、
花カツオとポン酢でいただくと、酒のつまみには、
この上ない美味さです。
生でスライスしての美味しさは、新玉ねぎならではですから
是非、試しいただきたいと思います。
玉ねぎは、田んぼに、深く植わっていませんから、
結構簡単に収獲できます。
ただその後が大変。
玉ねぎを、6個程度束ね、紐で結わえます。
その結えた、玉ねぎを今度は、車に積み込み、
家の裏にある「玉ねぎハウス」で干すために、吊るします。
結構手間が掛かる作業で、
今年も2名のお手伝いを借りての作業です。
更に、一日玉ねぎと触れていたせいか、衣服にも体にも
猛烈な玉ねぎのニオイ。
強烈なニオイに惹かれたわけでは無いでしょうが??、
田んぼで玉ねぎを収獲していたら、
近くで工事をしていたオジサンから、
新玉ねぎを譲って欲しいと
玉ねぎ獲りの見学を兼ねながら集めってくれました。
これから1年間、今日収獲した玉ねぎをいただいていきます。
これから収獲の新じゃがと、煮込んでもまた美味しい。
そう考えると、手間は掛かりますが、梅雨の合間の収獲は、
農家にとっては、慶びです。
田んぼに植わっている玉ねぎ。
結構簡単に抜けます。

抜いた玉ねぎをズラッと並べる。
左側のように、玉ねぎハウスで干せるように、
紐で結える。

収獲した玉ねぎは、自宅裏の玉ねぎハウスまで運ぶ。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年06月11日
桑の実・・・・・甘酸っぱい思い出
りんごの摘果作業の合間を縫って田んぼの周辺をブラブラ。
「オーっ」と声をあげそうなくらいびっくりしたのが「桑の実」です。
久しぶりに見ました。「桑の実」
子供の頃は、我が家の裏の畑の隅に結構桑が生えていて、
桑の木で「秘密基地」を作り、そこに色々なものを隠しましたっけ。
秘密基地に隠れて、黒く熟した「桑の実」をよくほおばりました。
マクドナルドもケンタッキーもまだ無い時代、
野にあるものをよく口にしていました。
桑の実を余りたくさん食べると、
口の周りとかが桑の実の果汁で「紫色」になりましったっけ。
昭和も50年代、まだ小学校の裏の畑の隅には、桑が植わっていて、
桑の実をみんなおやつにして口にしていました。
生糸生産日本一を誇った信州。
ここ豊野でもご多分に漏れず、繭の生産が盛んで
お蚕様が食べる桑の葉っぱを生産すべく、たくさんの桑畑があったようです。
時代が変わり、桑畑はいつしかりんご畑に変わり、
昨今はほとんど見かけなくなった「桑」ですが、
立派な桑の実を付けていました。
久しぶりに見ると懐かしいものです。
田んぼの周りをノンビリと歩いての発見です。
味も甘酸っぱかった桑の実ですが、
甘酸っぱい懐かしい思い出の発見もあるのですね。
黒く熟した桑の実。
黒いのが食べごろ。

今では、子供も食べなくなりましたから、
専ら、鳥の餌でしょうか?

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
「オーっ」と声をあげそうなくらいびっくりしたのが「桑の実」です。
久しぶりに見ました。「桑の実」
子供の頃は、我が家の裏の畑の隅に結構桑が生えていて、
桑の木で「秘密基地」を作り、そこに色々なものを隠しましたっけ。
秘密基地に隠れて、黒く熟した「桑の実」をよくほおばりました。
マクドナルドもケンタッキーもまだ無い時代、
野にあるものをよく口にしていました。
桑の実を余りたくさん食べると、
口の周りとかが桑の実の果汁で「紫色」になりましったっけ。
昭和も50年代、まだ小学校の裏の畑の隅には、桑が植わっていて、
桑の実をみんなおやつにして口にしていました。
生糸生産日本一を誇った信州。
ここ豊野でもご多分に漏れず、繭の生産が盛んで
お蚕様が食べる桑の葉っぱを生産すべく、たくさんの桑畑があったようです。
時代が変わり、桑畑はいつしかりんご畑に変わり、
昨今はほとんど見かけなくなった「桑」ですが、
立派な桑の実を付けていました。
久しぶりに見ると懐かしいものです。
田んぼの周りをノンビリと歩いての発見です。
味も甘酸っぱかった桑の実ですが、
甘酸っぱい懐かしい思い出の発見もあるのですね。
黒く熟した桑の実。
黒いのが食べごろ。

今では、子供も食べなくなりましたから、
専ら、鳥の餌でしょうか?

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト