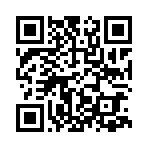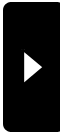2008年05月31日
草刈り・・・・乗用モア「ラビットカー」に乗って。
「百姓は、草との戦い」とよく母親から言われます。
そろそろ梅雨の季節となり、天気予報が気になる頃となりました。
梅雨を経て、一気に田んぼや畑の草は伸びます。
草は、植物の勢いをそぎますし、虫を寄せ付けますからなるべく早く除去しなければなりません。
梨の摘果が終わると、りんごの摘果に移りますが、
りんごの摘果を行なう前に、りんご畑の草刈りを進めています。
以前は、トラクターを使ったり一日仕事でしたが、
今では、「ラビットカー」を使うと作業効率が一気に上がり
四分の一近くの日数で済んでしまいます。
ラビットカーは、別名「乗用モア」
バギーカーのような車の下に、大型のカッターが付いており、
乗用して、進むとそのカッターが、回転して下草を刈ると言うシステムです。
機械音痴の僕ですが、2年目なのでかなり馴れました。
バギーカーは遊園地の中をぐるぐる回りますが、
この「乗用ラビットカー」はりんご畑や梨畑の中をグルグル回って草を刈ります。
今日一日で、ほぼりんご畑を終了しました。
これで「高所作業車」もりんご畑の中を容易に通れますし、
りんごの摘果作業の準備は万端です。
土日は、弟夫婦もやってきて、梨の摘果を一気に進めたいと思っています。
しかしながら天気予報は、雨。
雨は、辛いけど、お湿りは、無くてはならない。
農家にとっては、難しい季節の梅雨もそろそろです。
乗用モア 走れるのは畑の中だけです。
公道は走れません。

かなり茂ってしまったりんご畑の草。
色々な植物が、生えています。

ラビットカーで草を刈り田んぼを一周。
スピードをあげると早く終わりますが、雑になるので丁寧に。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
そろそろ梅雨の季節となり、天気予報が気になる頃となりました。
梅雨を経て、一気に田んぼや畑の草は伸びます。
草は、植物の勢いをそぎますし、虫を寄せ付けますからなるべく早く除去しなければなりません。
梨の摘果が終わると、りんごの摘果に移りますが、
りんごの摘果を行なう前に、りんご畑の草刈りを進めています。
以前は、トラクターを使ったり一日仕事でしたが、
今では、「ラビットカー」を使うと作業効率が一気に上がり
四分の一近くの日数で済んでしまいます。
ラビットカーは、別名「乗用モア」
バギーカーのような車の下に、大型のカッターが付いており、
乗用して、進むとそのカッターが、回転して下草を刈ると言うシステムです。
機械音痴の僕ですが、2年目なのでかなり馴れました。
バギーカーは遊園地の中をぐるぐる回りますが、
この「乗用ラビットカー」はりんご畑や梨畑の中をグルグル回って草を刈ります。
今日一日で、ほぼりんご畑を終了しました。
これで「高所作業車」もりんご畑の中を容易に通れますし、
りんごの摘果作業の準備は万端です。
土日は、弟夫婦もやってきて、梨の摘果を一気に進めたいと思っています。
しかしながら天気予報は、雨。
雨は、辛いけど、お湿りは、無くてはならない。
農家にとっては、難しい季節の梅雨もそろそろです。
乗用モア 走れるのは畑の中だけです。
公道は走れません。

かなり茂ってしまったりんご畑の草。
色々な植物が、生えています。

ラビットカーで草を刈り田んぼを一周。
スピードをあげると早く終わりますが、雑になるので丁寧に。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月30日
玉ネギの季節
田植えの季節です。
我が家の裏は、田んぼで田に水を張ったせいか
かえるの鳴き声が、毎夜聞こえます。
田植えももうすぐです。
田植えの頃に、「玉ねぎ」とりがあります。
その昔は、稲が夏、晩秋から初夏にかけ玉ねぎと
二毛作を行なっていてのですが、
豊野町浅野地区でも、ご多分に漏れず農業の高齢化の波が
押し寄せ、二毛作を行なう農家は、かなり少なくなりました。
我が家でも、田植えはここ数日中に行ないますが、
玉ねぎの収獲は、6月10日前後を予定していて、二毛作は行ないません。
今の時季には、もう玉ねぎの大きさ・成長具合が、だいぶ分かります。
成長するに越したことは無いのですが、市場では、大きすぎるのも
敬遠されてしまいますから、中程度の大きさが好まれます。
サイズは、Sの小玉から3Lの特大サイズまでに選別されて、
サイズごとに分けて、出荷します。
家庭でも、1回に使い切ることが難しい、特大サイズは、給食用にまわされるそうです。
昨年は、特大玉の一部は、出荷せずに新潟の地震の被災地の救援用に、使ってもらいました。
大鍋で煮込んで、カレーにしたようです。
全部が全部そうではありませんでしたが、お役に立てば、幸いです。
いよいよ今年もそういった玉ねぎの季節なのですね。
新玉ねぎは、生でいただくのが一番です。
この時季スーパーでは、新玉ねぎが結構お得なお値段で購入可能です。
せっかくの新玉ねぎですから、「生」でスライスした後、ちょっと時間を置くか、水に浸けるかして、鰹節を掛けて、いただくことをオススメします。
大地の根を張る玉ねぎ。
雪解け後、一気に大きくなった。
まだまだ成長しえもらい、6月10日前後まで、大きくする。

玉ねぎは、この時期になると、葉っぱが、倒れます。
稲は、収獲まで「ピン」と立っていなければ、いけないのですが、
玉ねぎは、倒れて、しばらくしてからが収獲の合図。
田んぼの玉ねぎは、そろそろ倒れ始めました。

手前の緑色のとがったのは、葱坊主。
玉ねぎで、この葱坊主の出たものは、玉が小さく、出荷は出来ません。
この葱坊主は、倒れません。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
我が家の裏は、田んぼで田に水を張ったせいか
かえるの鳴き声が、毎夜聞こえます。
田植えももうすぐです。
田植えの頃に、「玉ねぎ」とりがあります。
その昔は、稲が夏、晩秋から初夏にかけ玉ねぎと
二毛作を行なっていてのですが、
豊野町浅野地区でも、ご多分に漏れず農業の高齢化の波が
押し寄せ、二毛作を行なう農家は、かなり少なくなりました。
我が家でも、田植えはここ数日中に行ないますが、
玉ねぎの収獲は、6月10日前後を予定していて、二毛作は行ないません。
今の時季には、もう玉ねぎの大きさ・成長具合が、だいぶ分かります。
成長するに越したことは無いのですが、市場では、大きすぎるのも
敬遠されてしまいますから、中程度の大きさが好まれます。
サイズは、Sの小玉から3Lの特大サイズまでに選別されて、
サイズごとに分けて、出荷します。
家庭でも、1回に使い切ることが難しい、特大サイズは、給食用にまわされるそうです。
昨年は、特大玉の一部は、出荷せずに新潟の地震の被災地の救援用に、使ってもらいました。
大鍋で煮込んで、カレーにしたようです。
全部が全部そうではありませんでしたが、お役に立てば、幸いです。
いよいよ今年もそういった玉ねぎの季節なのですね。
新玉ねぎは、生でいただくのが一番です。
この時季スーパーでは、新玉ねぎが結構お得なお値段で購入可能です。
せっかくの新玉ねぎですから、「生」でスライスした後、ちょっと時間を置くか、水に浸けるかして、鰹節を掛けて、いただくことをオススメします。
大地の根を張る玉ねぎ。
雪解け後、一気に大きくなった。
まだまだ成長しえもらい、6月10日前後まで、大きくする。

玉ねぎは、この時期になると、葉っぱが、倒れます。
稲は、収獲まで「ピン」と立っていなければ、いけないのですが、
玉ねぎは、倒れて、しばらくしてからが収獲の合図。
田んぼの玉ねぎは、そろそろ倒れ始めました。

手前の緑色のとがったのは、葱坊主。
玉ねぎで、この葱坊主の出たものは、玉が小さく、出荷は出来ません。
この葱坊主は、倒れません。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月29日
ヘビイチゴ・・・・ヘビが食べるイチゴ??
田んぼの畦塗りが始まりました。
南北に細長い信州では、南信中信地方では、既に田植えは終了の様子。
田植えは、地域地域の気候によって、変わりますが、豊野町浅野地区では、今月末が多いです。
我が家も、昨年同様5月30日前後に田植えを行なう予定です。
田んぼの代かきや畦塗りに、追われています。
田んぼの畦に、よく生えているのが「ヘビイチゴ」です。
小さな赤い実を付けていて、子供の頃に「ヘビが食べるイチゴ」だから「ヘビイチゴ」と覚えた記憶があります。
実際、ヘビは、この「ヘビイチゴ」は食べませんが、ヘビが出そうな、湿気がある、畦とかに生えていることが多いためこの名前が付いたようです。
別名「毒イチゴ」とも呼ぶそうですが、毒はありません。
食べられますが、味も無く、汁気も無いそうです。
子供の頃は、色々と口に含んでみたり、家に採って帰ってみたりするのですが、みんなこの「ヘビイチゴ」だけは、忌避して
「毒がある」
「ヘビの好物を採って邪魔してはいけない」
と思い、ヘビイチゴで遊んだ記憶はありません。
最近は、コンクリートで地肌を覆ってしまっているせいでしょうか
昨年も数匹しかヘビは、見ませんでした。
ヘビの「抜け殻」というか脱皮した際の薄い皮をお財布に
入れておくと、お金がたまると言われたものですが
ヘビも見かけませんから、
ヘビの脱皮した皮もすっかり見かけなくなくなりました。
そのせいでも無いでしょうが、懐が寂しい。
「ヘビがイチゴを食べる。」
なんとも今となっては、面白おかしい話ですが、
子供の頃はすっかり信じていました。
「ヘビ」も「ヘビイチゴ」もなかなか見かけなくなった昨今。
子供たちは、もうこんな迷信は、知らないのでしょうね。
小さな小指の先くらいの大きさのヘビイチゴ

我が家の露地もののイチゴ。
同時期にでる。

田んぼには、水が張られ、田植えの準備が進められる。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
南北に細長い信州では、南信中信地方では、既に田植えは終了の様子。
田植えは、地域地域の気候によって、変わりますが、豊野町浅野地区では、今月末が多いです。
我が家も、昨年同様5月30日前後に田植えを行なう予定です。
田んぼの代かきや畦塗りに、追われています。
田んぼの畦に、よく生えているのが「ヘビイチゴ」です。
小さな赤い実を付けていて、子供の頃に「ヘビが食べるイチゴ」だから「ヘビイチゴ」と覚えた記憶があります。
実際、ヘビは、この「ヘビイチゴ」は食べませんが、ヘビが出そうな、湿気がある、畦とかに生えていることが多いためこの名前が付いたようです。
別名「毒イチゴ」とも呼ぶそうですが、毒はありません。
食べられますが、味も無く、汁気も無いそうです。
子供の頃は、色々と口に含んでみたり、家に採って帰ってみたりするのですが、みんなこの「ヘビイチゴ」だけは、忌避して
「毒がある」
「ヘビの好物を採って邪魔してはいけない」
と思い、ヘビイチゴで遊んだ記憶はありません。
最近は、コンクリートで地肌を覆ってしまっているせいでしょうか
昨年も数匹しかヘビは、見ませんでした。
ヘビの「抜け殻」というか脱皮した際の薄い皮をお財布に
入れておくと、お金がたまると言われたものですが
ヘビも見かけませんから、
ヘビの脱皮した皮もすっかり見かけなくなくなりました。
そのせいでも無いでしょうが、懐が寂しい。
「ヘビがイチゴを食べる。」
なんとも今となっては、面白おかしい話ですが、
子供の頃はすっかり信じていました。
「ヘビ」も「ヘビイチゴ」もなかなか見かけなくなった昨今。
子供たちは、もうこんな迷信は、知らないのでしょうね。
小さな小指の先くらいの大きさのヘビイチゴ

我が家の露地もののイチゴ。
同時期にでる。

田んぼには、水が張られ、田植えの準備が進められる。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月28日
ラ・フランス・・・洋梨の女王。生産額2位は長野県
梨の摘果も終盤を迎えています。
ご近所のベテランのおば様方に助っ人をお願いして、日々作業が進められていますが、梨が終わると、次は、桃・りんごに取り掛からねばなりません。
我が家では、9月初旬から、
甘くてジューシーな「幸水」
酸味が加わり、甘味と酸味のバランスがよい「豊水」
大きくて、とにかく甘い最近大人気な「あきづき」
濃厚な味わいの「南水」
の4種類を手がけており、
「幸水」が終了すると、「豊水」と言った具合に、
順繰りに善光寺平の梨が、楽しめます。
以上述べたのは、「和梨」と言って日本梨です。
梨には、丸い「和梨」と瓶型の「洋ナシ」があります。
数年前から栽培し、昨年我が家で商品として出荷を開始したのが
洋ナシである「ラ・フランス」。
洋ナシには、今述べた「ラ・フランス」のほかに、
「ル・レクチェ」とか「オーロラ」などがあります。
さて我が家で栽培の「ラ・フランス」ですが、
ご存知のように、ラ・フランス生産第1位は、山形県ですが、
長野県は、意外にも第2位です。
すぐにいただける和梨と比べると、収穫後、しばらく「追熟」が必要な
「ラ・フランス」。
まだまだ認知度が今ひとつで
「追熟」が必要なため、食べごろがわかりかね、
本当の「ラ・フランス」の味をまだお楽しみいただけていない方、
是非今年は、和梨に加え
「ラ・フランス」お気軽にお楽しみください。
「ラ・フランス」生産額第2位は、長野県もお忘れなく・・・・。
もちろん、発送は追熟後に行ないますから、
「食べごろ」にお届けいたします。
なお、昨年は、11月末の発送でした。
徳利型で、和梨の丸型とは、既に違う「ラ・フランス」の実。


善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ご近所のベテランのおば様方に助っ人をお願いして、日々作業が進められていますが、梨が終わると、次は、桃・りんごに取り掛からねばなりません。
我が家では、9月初旬から、
甘くてジューシーな「幸水」
酸味が加わり、甘味と酸味のバランスがよい「豊水」
大きくて、とにかく甘い最近大人気な「あきづき」
濃厚な味わいの「南水」
の4種類を手がけており、
「幸水」が終了すると、「豊水」と言った具合に、
順繰りに善光寺平の梨が、楽しめます。
以上述べたのは、「和梨」と言って日本梨です。
梨には、丸い「和梨」と瓶型の「洋ナシ」があります。
数年前から栽培し、昨年我が家で商品として出荷を開始したのが
洋ナシである「ラ・フランス」。
洋ナシには、今述べた「ラ・フランス」のほかに、
「ル・レクチェ」とか「オーロラ」などがあります。
さて我が家で栽培の「ラ・フランス」ですが、
ご存知のように、ラ・フランス生産第1位は、山形県ですが、
長野県は、意外にも第2位です。
すぐにいただける和梨と比べると、収穫後、しばらく「追熟」が必要な
「ラ・フランス」。
まだまだ認知度が今ひとつで
「追熟」が必要なため、食べごろがわかりかね、
本当の「ラ・フランス」の味をまだお楽しみいただけていない方、
是非今年は、和梨に加え
「ラ・フランス」お気軽にお楽しみください。
「ラ・フランス」生産額第2位は、長野県もお忘れなく・・・・。
もちろん、発送は追熟後に行ないますから、
「食べごろ」にお届けいたします。
なお、昨年は、11月末の発送でした。
徳利型で、和梨の丸型とは、既に違う「ラ・フランス」の実。


善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月27日
地豆(落花生)を作る。 その1
今年、初めて「地豆」を蒔きました。
「地豆(じまめ)」とは、このあたりでは、「落花生」のことを言います。
「地豆」というと、その地のオリジナルの豆の総称のようで、
例えば、信州では、「くらかけ豆」が、信州全般でよく栽培されていますから、「地豆」なのでしょうが、
この場合は、アクセントが「豆」にあります。
我が家を始め、豊野町浅野では「地豆」は、「地」にアクセントがある、落花生のことを言います。
地豆(落花生)は、千葉産とばかり思っていた僕ですが、最近は
国外産の輸入物もかなり多く、出回っているようです。
安くてお手頃価格が、国外産のいいところですが、
やはり地物を安心安全で、たくさん食べたいとの思いから
一念発起して、今年から栽培へ。
「地豆を作ろう」と言い出したのは、母親で、
母親の友人が、昨年栽培して、非常に美味しかったことの影響もあります。
浅野(豊野町浅野地区)で地豆(落花生)???出来るの???
と思ったのですが、昨年、枝豆が出かけた頃に、
その芽が全部鳥に啄ばまれて、全滅し危惧はしましたものの、
何とか芽は、出ました。
通常の枝豆や、先ほどお話した信州特産の「くらかけ豆」とは
ちょっと違う芽で、豆類では無いような、芽です。
このあと、大きく成長し、黄色い花が咲くそうです。
その後、花が咲き終わると、地下に向かって、
「子房柄」が伸び、地中にまで伸び、地中で実(豆の実)が付くそうです。
花が落ちて、地中で実るから「落花生」と言うのですね。
地豆は、地中で実が付くことから、「地豆」というのですね。
枝豆やくらかけ豆は、地上で実り、地中で実るのはこの豆だけです。
そう考えると、
「落花生」という呼び方も、
「地豆」と言う呼び方も
それぞれ的を得た言い方で、どちらも素敵な呼び方です。
「地豆の花」も、「豆が地中で実る」と言うことも初めて経験します。
口にすることは、頻繁にありますが、栽培の様子はほとんど見たことが無い地豆の様子を、今年は、時折ご案内したいと思います。
地豆(落花生)の芽。
生まれて初めて見ました。
花が咲いた後、地中に潜って実が付く・・・
興味津々です。

芽は出たものの、草がすごい。
草との戦いもしなければなりません。

小布施島という田んぼで栽培しています。
このあたりには、小布施島・浅野島・吉島など、田んぼには
「島」の付く名前が多いです。
「島」は中州の事を指し、「中洲」から来ているのでしょうか?
千曲川に堤防が無かった頃は、洪水のたびに、千曲川の流れが
変わり「島」が出没したようです。
ガーデントラクターに乗って、小布施橋を渡ってきたそうです。
軽トラが多くなり、すっかりガーデントラクターで畑に行く風景も
見かけなくなりました。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
「地豆(じまめ)」とは、このあたりでは、「落花生」のことを言います。
「地豆」というと、その地のオリジナルの豆の総称のようで、
例えば、信州では、「くらかけ豆」が、信州全般でよく栽培されていますから、「地豆」なのでしょうが、
この場合は、アクセントが「豆」にあります。
我が家を始め、豊野町浅野では「地豆」は、「地」にアクセントがある、落花生のことを言います。
地豆(落花生)は、千葉産とばかり思っていた僕ですが、最近は
国外産の輸入物もかなり多く、出回っているようです。
安くてお手頃価格が、国外産のいいところですが、
やはり地物を安心安全で、たくさん食べたいとの思いから
一念発起して、今年から栽培へ。
「地豆を作ろう」と言い出したのは、母親で、
母親の友人が、昨年栽培して、非常に美味しかったことの影響もあります。
浅野(豊野町浅野地区)で地豆(落花生)???出来るの???
と思ったのですが、昨年、枝豆が出かけた頃に、
その芽が全部鳥に啄ばまれて、全滅し危惧はしましたものの、
何とか芽は、出ました。
通常の枝豆や、先ほどお話した信州特産の「くらかけ豆」とは
ちょっと違う芽で、豆類では無いような、芽です。
このあと、大きく成長し、黄色い花が咲くそうです。
その後、花が咲き終わると、地下に向かって、
「子房柄」が伸び、地中にまで伸び、地中で実(豆の実)が付くそうです。
花が落ちて、地中で実るから「落花生」と言うのですね。
地豆は、地中で実が付くことから、「地豆」というのですね。
枝豆やくらかけ豆は、地上で実り、地中で実るのはこの豆だけです。
そう考えると、
「落花生」という呼び方も、
「地豆」と言う呼び方も
それぞれ的を得た言い方で、どちらも素敵な呼び方です。
「地豆の花」も、「豆が地中で実る」と言うことも初めて経験します。
口にすることは、頻繁にありますが、栽培の様子はほとんど見たことが無い地豆の様子を、今年は、時折ご案内したいと思います。
地豆(落花生)の芽。
生まれて初めて見ました。
花が咲いた後、地中に潜って実が付く・・・
興味津々です。

芽は出たものの、草がすごい。
草との戦いもしなければなりません。

小布施島という田んぼで栽培しています。
このあたりには、小布施島・浅野島・吉島など、田んぼには
「島」の付く名前が多いです。
「島」は中州の事を指し、「中洲」から来ているのでしょうか?
千曲川に堤防が無かった頃は、洪水のたびに、千曲川の流れが
変わり「島」が出没したようです。
ガーデントラクターに乗って、小布施橋を渡ってきたそうです。
軽トラが多くなり、すっかりガーデントラクターで畑に行く風景も
見かけなくなりました。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月26日
柿の葉と桃の葉・・・・・若葉の季節に。
「慈雨」と言う言葉がふさわしく、
土日の雨は結構降り、田んぼや畑の植物たちにまさに恵みの雨でした。
空気が洗われるとはまさにこのことで、新緑の季節
雨上がりの今日は、緑がことのほか美しい。
新緑のなかで、際立って緑が、美しく、若々しく鮮やかなのが、「柿の葉」である。
「柿の葉」は、あまりの若葉の美しさから、初夏の季語となっている。
山奥に出かけなくとも、「柿の葉」であれば、近所でも裏庭でも簡単に見ることが出来る。
雨上がりの、新鮮な空気の下で、柿の若葉を見ると、初夏の季語然りといったところである。
季語の「柿の葉」を歌った句に、富安風生さんの
「柿若葉 重なりして 透く緑」
と言うのがある。
柿の若葉を歌った有名な句で、今の時季の柿の葉にピッタリの句でもある。
柿の若葉は、また美しさとともに、食用にでも出来る。
天ぷらにしていただくと美味しい。
山菜の季節も終了であるから、是非試してみたいと思っている。
「柿の葉寿司」や「柿の葉茶」もあるくらいだから、
八十八夜を過ぎた、夏季の若葉は、目にも体にも優しいようである。
「柿の葉」も、美しいが、「桃の葉」も柔らかい。
「桃の葉」は試してみたことが無いのであるが、
汗ものときに、湯船に浮かべて、浸かるとよいと聞いたことがある。
桃の葉も、じっと見ると、その柔らかさとしなやかさに、感動する。
若葉の季節である、五月もそろそろ終了。
都内にいた頃は、会社帰りに、ふと何気なく立ち寄った、ドラッグストア
で、「柿の葉茶」や「どくだみ茶」を買い求め、健康に気遣っていたのであるが、田舎のこの辺りでは、そう簡単に、ドラッグストアに行くわけにもいかない。
「柿の葉茶」を作ろうと思ってはいるものの、いつになるやら・・・。
まあ、毎日、柿の葉も桃の葉も実際に間近で見ているのであるから、
飲む必要も無いかと思っている。
鮮やかな柿の葉。
ワックスをかけたように、艶がある。
この葉を狙って、「アメリカシロヒトリ」が活動するのは、夏。

重なり合う、柿の葉の裏を、木の下から見る。
緑が、透けるようである。

桃の若葉。
柔らかく、しなやか。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
土日の雨は結構降り、田んぼや畑の植物たちにまさに恵みの雨でした。
空気が洗われるとはまさにこのことで、新緑の季節
雨上がりの今日は、緑がことのほか美しい。
新緑のなかで、際立って緑が、美しく、若々しく鮮やかなのが、「柿の葉」である。
「柿の葉」は、あまりの若葉の美しさから、初夏の季語となっている。
山奥に出かけなくとも、「柿の葉」であれば、近所でも裏庭でも簡単に見ることが出来る。
雨上がりの、新鮮な空気の下で、柿の若葉を見ると、初夏の季語然りといったところである。
季語の「柿の葉」を歌った句に、富安風生さんの
「柿若葉 重なりして 透く緑」
と言うのがある。
柿の若葉を歌った有名な句で、今の時季の柿の葉にピッタリの句でもある。
柿の若葉は、また美しさとともに、食用にでも出来る。
天ぷらにしていただくと美味しい。
山菜の季節も終了であるから、是非試してみたいと思っている。
「柿の葉寿司」や「柿の葉茶」もあるくらいだから、
八十八夜を過ぎた、夏季の若葉は、目にも体にも優しいようである。
「柿の葉」も、美しいが、「桃の葉」も柔らかい。
「桃の葉」は試してみたことが無いのであるが、
汗ものときに、湯船に浮かべて、浸かるとよいと聞いたことがある。
桃の葉も、じっと見ると、その柔らかさとしなやかさに、感動する。
若葉の季節である、五月もそろそろ終了。
都内にいた頃は、会社帰りに、ふと何気なく立ち寄った、ドラッグストア
で、「柿の葉茶」や「どくだみ茶」を買い求め、健康に気遣っていたのであるが、田舎のこの辺りでは、そう簡単に、ドラッグストアに行くわけにもいかない。
「柿の葉茶」を作ろうと思ってはいるものの、いつになるやら・・・。
まあ、毎日、柿の葉も桃の葉も実際に間近で見ているのであるから、
飲む必要も無いかと思っている。
鮮やかな柿の葉。
ワックスをかけたように、艶がある。
この葉を狙って、「アメリカシロヒトリ」が活動するのは、夏。

重なり合う、柿の葉の裏を、木の下から見る。
緑が、透けるようである。

桃の若葉。
柔らかく、しなやか。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月25日
コマツナをいじりながら・・・・・毛虫と芋虫
キャベツとコマツナを毎日梨の摘果の合間を縫って収獲しています。
昨日は、きゅうりの初収獲となりました。
梨・桃・りんごの摘果が続くため、そうたくさんは作れないのですが、
楽しみながらの栽培です。
農薬は使わないようにしていますが、こう暑くなってきますと
結構「虫」が出没してきます。
キャベツときゅうりは、まだ見かけていないのですが、
コマツナには、小さな毛が無い「青虫」を見かけます。
見つけたら、その場で潰すようにしています。
こんな僕ですが、毛虫の類は、大嫌いで、
ヘビとともに子供の頃から苦手で、見つけるとちょっと驚きの悲鳴を上げてしまいます。
「毛虫」と一言で呼びますが、蝶や蛾の幼虫で、
毛のあるものを「毛虫」
毛の無いものを「芋虫」
と呼ぶようです。
ですから「毛虫」は毛虫と芋虫の総称と言うことです。
コマツナをいじっていると、小さな青虫
・・・これは、毛が無いから芋虫??
を見かけますが、
どうも土の中にいるのを「芋虫」と思い込んでいた僕にとっては
違和感を覚えます。
近所のおばさんたちにも、その話をしたら、「へえ??」と初耳だったようですから、
その分類の仕方は、正しいのか最近疑問に思っています。
カッコウも活動し、燕も子育てに余念が無い昨今ですが、
その鳥たちの餌になるのが、こうした虫たち。
新緑の若葉も毛虫たちにとっては、柔らかいのか格好の餌となりますが、
その毛虫の類は、子育てに忙しい鳥たちには、格好の餌です。
農家にとては、害虫ですから、いないに越したことは無いのですが、
こうして考えると、毛虫も鳥も人間も「循環社会」の一員とである人間である以上、
仲良くとまではいきませんが、持ちつ持たれつ。
虫も鳥も我々人間も「共存共栄」と思い、なるべく自然に優しく
農業を続けたいものです。
きゅうりとコマツナ。
きゅうりは初採り。
初物きゅうりは、そのまま生で。
瑞々しかったです。

どんどん咲き始めたきゅうりの花。
トマト・ナスも咲き始めましたが、
こちらは収獲まで結構時間が掛かります。

そろそろ収獲の春キャベツ。
夏場になると、葉もの野菜は、虫との闘いです。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
昨日は、きゅうりの初収獲となりました。
梨・桃・りんごの摘果が続くため、そうたくさんは作れないのですが、
楽しみながらの栽培です。
農薬は使わないようにしていますが、こう暑くなってきますと
結構「虫」が出没してきます。
キャベツときゅうりは、まだ見かけていないのですが、
コマツナには、小さな毛が無い「青虫」を見かけます。
見つけたら、その場で潰すようにしています。
こんな僕ですが、毛虫の類は、大嫌いで、
ヘビとともに子供の頃から苦手で、見つけるとちょっと驚きの悲鳴を上げてしまいます。
「毛虫」と一言で呼びますが、蝶や蛾の幼虫で、
毛のあるものを「毛虫」
毛の無いものを「芋虫」
と呼ぶようです。
ですから「毛虫」は毛虫と芋虫の総称と言うことです。
コマツナをいじっていると、小さな青虫
・・・これは、毛が無いから芋虫??
を見かけますが、
どうも土の中にいるのを「芋虫」と思い込んでいた僕にとっては
違和感を覚えます。
近所のおばさんたちにも、その話をしたら、「へえ??」と初耳だったようですから、
その分類の仕方は、正しいのか最近疑問に思っています。
カッコウも活動し、燕も子育てに余念が無い昨今ですが、
その鳥たちの餌になるのが、こうした虫たち。
新緑の若葉も毛虫たちにとっては、柔らかいのか格好の餌となりますが、
その毛虫の類は、子育てに忙しい鳥たちには、格好の餌です。
農家にとては、害虫ですから、いないに越したことは無いのですが、
こうして考えると、毛虫も鳥も人間も「循環社会」の一員とである人間である以上、
仲良くとまではいきませんが、持ちつ持たれつ。
虫も鳥も我々人間も「共存共栄」と思い、なるべく自然に優しく
農業を続けたいものです。
きゅうりとコマツナ。
きゅうりは初採り。
初物きゅうりは、そのまま生で。
瑞々しかったです。

どんどん咲き始めたきゅうりの花。
トマト・ナスも咲き始めましたが、
こちらは収獲まで結構時間が掛かります。

そろそろ収獲の春キャベツ。
夏場になると、葉もの野菜は、虫との闘いです。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月24日
サクランボとプルーン・・・・庭の主役の移り変わり
4月20日過ぎに、櫻が咲き始め、
ゴールデンウイーク中に、くだものの花が一気に咲き始めた
ここ善光寺平の北端、豊野町浅野地区。
桃・りんご、梨の田んぼに広がりますが、我が家の裏庭に
同時期に咲いた花では、サクランボとプルーンの木がそれぞれ2本ずつあります。
何れも、自家用に栽培しているのですが、結構大きな木になりました。
僕が、長野にいた今から20年ほど前の18歳の時には、
無かった木ですがいつの間にか、クルミと栗の木が無くなり、
2つの樹に変わったようです。
くるみも栗も結構「地味」な木ですが、料理にも使い方色々で
楽しみのある食べ物です。
どちらかと言うと地味な存在で、、そのままいただいても非常に味わい深く、美味なのですが、
両者とも、いつの間にかお菓子の材料として使われるほうが多くなった気がします。
サクランボは、6月に、プルーンは8月末に実を付けます。
サクランボは、そのまま。
プルーンは、そのままでもいただけるのですが、
昨年も、結構な量が収獲できましたので
煮込んで干して、「干しプルーン」にして、いただきました。
くだもの好きな僕としては、プルーン・サクランボは、非常に美味しくいただけて、うれしい限りですが、
酒飲みでもある僕としては、クルミを使ったつまみにも大いに興味があります。
でもまあ、それは欲張りと言うものでしょう。
庭の鳥たちにとっては、サクランボやプルーンに変わってよかったのかも。
特にサクランボは、鳥たちの絶好の好物のようですから。
堅固な殻や厳つい殻に包まれている栗・クルミより
色も味も甘い2つのくだものたちのほうが、鳥は喜んでいるでしょう。
クルミも栗も美味しいのですが・・・・・。
まあ、鳥たちにその味を覚えてもらっても困るのですが・・・・。
プルーンの実。
これから摘果をしなければならないのですが、
桃・梨・りんごの摘果が忙しく、
とても手が回りそうもありません。

実を付けたサクランボ。
6月には、熟して美味しくいただけます。

こちらは、ジャーマンアイリスの花。
ジャーマンアイリスも、確か20年前には無かったはず。
僕のいないうちに、我が家だけでなく
北信地方では、アヤメからこのジャーマンアイリスに
変わったようです。
庭の花も、時代とともに変わるものなのですね。
今年は、大輪の菊を育てたいと思っているのですが、
もうそんな時代では無いのでしょうか??

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ゴールデンウイーク中に、くだものの花が一気に咲き始めた
ここ善光寺平の北端、豊野町浅野地区。
桃・りんご、梨の田んぼに広がりますが、我が家の裏庭に
同時期に咲いた花では、サクランボとプルーンの木がそれぞれ2本ずつあります。
何れも、自家用に栽培しているのですが、結構大きな木になりました。
僕が、長野にいた今から20年ほど前の18歳の時には、
無かった木ですがいつの間にか、クルミと栗の木が無くなり、
2つの樹に変わったようです。
くるみも栗も結構「地味」な木ですが、料理にも使い方色々で
楽しみのある食べ物です。
どちらかと言うと地味な存在で、、そのままいただいても非常に味わい深く、美味なのですが、
両者とも、いつの間にかお菓子の材料として使われるほうが多くなった気がします。
サクランボは、6月に、プルーンは8月末に実を付けます。
サクランボは、そのまま。
プルーンは、そのままでもいただけるのですが、
昨年も、結構な量が収獲できましたので
煮込んで干して、「干しプルーン」にして、いただきました。
くだもの好きな僕としては、プルーン・サクランボは、非常に美味しくいただけて、うれしい限りですが、
酒飲みでもある僕としては、クルミを使ったつまみにも大いに興味があります。
でもまあ、それは欲張りと言うものでしょう。
庭の鳥たちにとっては、サクランボやプルーンに変わってよかったのかも。
特にサクランボは、鳥たちの絶好の好物のようですから。
堅固な殻や厳つい殻に包まれている栗・クルミより
色も味も甘い2つのくだものたちのほうが、鳥は喜んでいるでしょう。
クルミも栗も美味しいのですが・・・・・。
まあ、鳥たちにその味を覚えてもらっても困るのですが・・・・。
プルーンの実。
これから摘果をしなければならないのですが、
桃・梨・りんごの摘果が忙しく、
とても手が回りそうもありません。

実を付けたサクランボ。
6月には、熟して美味しくいただけます。

こちらは、ジャーマンアイリスの花。
ジャーマンアイリスも、確か20年前には無かったはず。
僕のいないうちに、我が家だけでなく
北信地方では、アヤメからこのジャーマンアイリスに
変わったようです。
庭の花も、時代とともに変わるものなのですね。
今年は、大輪の菊を育てたいと思っているのですが、
もうそんな時代では無いのでしょうか??

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月23日
我が家のイチゴ
路地イチゴの季節となりました。
どこで聞いたのか全く覚えていないのですが
最近では、冬の方がイチゴの収穫高が多いそうです。
ケーキ用に使うイチゴの需要が多いせいでしょうか?
「露地もののイチゴ」という言葉も、ほとんど聞かなくなりました。
ほとんどハウス栽培のイチゴではないでしょうか。
1年中、スーパーに行けば、先ず店頭にあるイチゴとなりました。
静岡・栃木・長野等九州・四国も含め全国で栽培されています。
その昔、まだハウス栽培が今日ほど発達していなかった頃、
ここ豊野町浅野地区では、肥沃な土地柄を利用して
稲の裏作として、「露地ものイチゴ」を栽培していました。
まだ小学生の頃で、朝早く一輪車に収獲したイチゴを載せ
家に運んで手伝ったのを覚えています。
収獲し、運んだイチゴは、パックに詰め、箱に入れて出荷します。
結構たくさんの農家が栽培していて、近くの八百屋のおじさんが
集めたイチゴを須坂の市場に持って行き、「セリ」にかけるのです。
小学校高学年になると、その記憶が全くありませんから
もうその頃には、我が家では、栽培こそ行なっていたものの、
出荷は行なっていなかったのかもしれません。
どんぶりにイチゴを山盛りにし、砂糖をかけて食べていたように記憶しています。
なぜ砂糖をかけたのか覚えていません。
砂糖が必要なほど、当時のイチゴは酸味があったのでしょうか??
それとも、僕が単に甘党だったのでしょうか?
イチゴの品種は、かなり変遷し、昨今では、
より大粒で甘いものになっているようですから、
当時のイチゴはもっと酸っぱかったのかもしれません。
これからしばらくイチゴが採れます。
先ずは、そのままいただきたいと思います。
さすがに昔のように、砂糖を掛けて食べようとは思いませんが。
その後しばらくしたら、イチゴジャムつくりを行なおうかと思っています。
砂糖をこってりと入れて、よく練ったイチゴジャムは、長期保存が可能。
しばらく「我が家のイチゴ」のお世話になりそうです。
小さな実を漬け始めたイチゴ。
これから2週間ほど毎朝、イチゴを楽しみたいと思います。


イチゴの畝が、3列ありますので、1日おきに収獲しています。
収穫といっても、僕がその場で食べてしまうので、
かなり「収穫減」になっていると思います。
農薬を一切使っていないので、その場で採ったイチゴを
その場で食べてしまいます。

ご案内
昨日のブログ「カッコウと百舌」で
百舌の写真で掲載しましたものが、「ムクドリ」のようでした。
20年ぶりの田舎暮らし・農家生活で、記憶や知識に間違ったものがある場合があるかもしれません。
異論等がある場合は、ご指摘、今後ともよろしくお願い申し上げます。
善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
どこで聞いたのか全く覚えていないのですが
最近では、冬の方がイチゴの収穫高が多いそうです。
ケーキ用に使うイチゴの需要が多いせいでしょうか?
「露地もののイチゴ」という言葉も、ほとんど聞かなくなりました。
ほとんどハウス栽培のイチゴではないでしょうか。
1年中、スーパーに行けば、先ず店頭にあるイチゴとなりました。
静岡・栃木・長野等九州・四国も含め全国で栽培されています。
その昔、まだハウス栽培が今日ほど発達していなかった頃、
ここ豊野町浅野地区では、肥沃な土地柄を利用して
稲の裏作として、「露地ものイチゴ」を栽培していました。
まだ小学生の頃で、朝早く一輪車に収獲したイチゴを載せ
家に運んで手伝ったのを覚えています。
収獲し、運んだイチゴは、パックに詰め、箱に入れて出荷します。
結構たくさんの農家が栽培していて、近くの八百屋のおじさんが
集めたイチゴを須坂の市場に持って行き、「セリ」にかけるのです。
小学校高学年になると、その記憶が全くありませんから
もうその頃には、我が家では、栽培こそ行なっていたものの、
出荷は行なっていなかったのかもしれません。
どんぶりにイチゴを山盛りにし、砂糖をかけて食べていたように記憶しています。
なぜ砂糖をかけたのか覚えていません。
砂糖が必要なほど、当時のイチゴは酸味があったのでしょうか??
それとも、僕が単に甘党だったのでしょうか?
イチゴの品種は、かなり変遷し、昨今では、
より大粒で甘いものになっているようですから、
当時のイチゴはもっと酸っぱかったのかもしれません。
これからしばらくイチゴが採れます。
先ずは、そのままいただきたいと思います。
さすがに昔のように、砂糖を掛けて食べようとは思いませんが。
その後しばらくしたら、イチゴジャムつくりを行なおうかと思っています。
砂糖をこってりと入れて、よく練ったイチゴジャムは、長期保存が可能。
しばらく「我が家のイチゴ」のお世話になりそうです。
小さな実を漬け始めたイチゴ。
これから2週間ほど毎朝、イチゴを楽しみたいと思います。


イチゴの畝が、3列ありますので、1日おきに収獲しています。
収穫といっても、僕がその場で食べてしまうので、
かなり「収穫減」になっていると思います。
農薬を一切使っていないので、その場で採ったイチゴを
その場で食べてしまいます。

ご案内
昨日のブログ「カッコウと百舌」で
百舌の写真で掲載しましたものが、「ムクドリ」のようでした。
20年ぶりの田舎暮らし・農家生活で、記憶や知識に間違ったものがある場合があるかもしれません。
異論等がある場合は、ご指摘、今後ともよろしくお願い申し上げます。
善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月22日
カッコウと百舌
朝方カッコウの声を耳にしました。
以前、鶯の泣き声が聞こえた旨書きましたが、
田舎とは言うものの我が家の一帯は、比較的住宅地であり、
鶯・カッコウと泣き声が、聞けるのはうれしい限りです。
カッコウは、5月半ばに日本に飛来し、繁殖活動をするようです。
繁殖といっても、「托卵」といい、他の種類の鳥の巣に卵を産みつけ
その鳥に、育てさせます。
「百舌(もず)」がいい例で、我が家周辺では、百舌が結構いますから
カッコウは、百舌の巣に卵を産みつけ、百舌は、カッコウの卵を
自分の卵と勘違い?し、孵らせてヒナを育てます。
百舌の巣で孵ったヒナも凄腕の持ち主で、自分を除いて、孵った百舌ののヒナを巣から落としてしまいます。
百舌は、そうとは知らずに、カッコウのヒナを自分の子として育ててしまうのです。
百舌は、りんごをつついたり、農家にとっては、外敵でいわば、「害鳥」です。
害鳥の百舌は、りんごをつついて食べてしまうのですが、どういうわけか「美味しい甘いりんご」ばかり狙って、つついてしまうので、結構困り者です。
そう考えると、カッコウの存在も侮れないものがありますが、
百舌は本来昆虫など虫の類を食べますから、
百舌もまた生態系の中の一員で、田舎には、欠かせない存在です。
草刈りをしていたら、百舌がサッと集まってきて、草刈り後の、
地面に露出した昆虫たちを食べていました。
今年も、カッコウの声を聞いたということは、この百舌たちは、
カッコウの子育てをするのでしょう。
循環している、生態系。
自然に任せることが大切です。
僕は敢えて、「駆除」であるとか、何かをしようかとは思いませんが、
自然の摂理を見守りたいと思います。
草刈り後の、地面の露出部分で、餌を探す百舌。
どこから集まってくるのか、サッと8羽ぐらいが集まった。

玉ねぎ畑。
玉ねぎ畑ではこの時季、「ヒバリ」の巣を見かけることがある。
地面に作られたヒバリの巣は、こう暖かくなってくると
ヘビに狙われやすい。
しかし、これもまた生態系の一部であり、見守るしかない。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
以前、鶯の泣き声が聞こえた旨書きましたが、
田舎とは言うものの我が家の一帯は、比較的住宅地であり、
鶯・カッコウと泣き声が、聞けるのはうれしい限りです。
カッコウは、5月半ばに日本に飛来し、繁殖活動をするようです。
繁殖といっても、「托卵」といい、他の種類の鳥の巣に卵を産みつけ
その鳥に、育てさせます。
「百舌(もず)」がいい例で、我が家周辺では、百舌が結構いますから
カッコウは、百舌の巣に卵を産みつけ、百舌は、カッコウの卵を
自分の卵と勘違い?し、孵らせてヒナを育てます。
百舌の巣で孵ったヒナも凄腕の持ち主で、自分を除いて、孵った百舌ののヒナを巣から落としてしまいます。
百舌は、そうとは知らずに、カッコウのヒナを自分の子として育ててしまうのです。
百舌は、りんごをつついたり、農家にとっては、外敵でいわば、「害鳥」です。
害鳥の百舌は、りんごをつついて食べてしまうのですが、どういうわけか「美味しい甘いりんご」ばかり狙って、つついてしまうので、結構困り者です。
そう考えると、カッコウの存在も侮れないものがありますが、
百舌は本来昆虫など虫の類を食べますから、
百舌もまた生態系の中の一員で、田舎には、欠かせない存在です。
草刈りをしていたら、百舌がサッと集まってきて、草刈り後の、
地面に露出した昆虫たちを食べていました。
今年も、カッコウの声を聞いたということは、この百舌たちは、
カッコウの子育てをするのでしょう。
循環している、生態系。
自然に任せることが大切です。
僕は敢えて、「駆除」であるとか、何かをしようかとは思いませんが、
自然の摂理を見守りたいと思います。
草刈り後の、地面の露出部分で、餌を探す百舌。
どこから集まってくるのか、サッと8羽ぐらいが集まった。

玉ねぎ畑。
玉ねぎ畑ではこの時季、「ヒバリ」の巣を見かけることがある。
地面に作られたヒバリの巣は、こう暖かくなってくると
ヘビに狙われやすい。
しかし、これもまた生態系の一部であり、見守るしかない。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月21日
初夏の野菜の収穫スタート。
昨年の晩秋に、定植したキャベツがかなり大きくなり、初めて収獲しました。
秋口、確か10月松だったような気がしますが、梨やりんご「シナノスイート」の収獲に忙しい中、顰蹙を買いながら、種を蒔き、11月に田んぼに定植したものです。
雪の下で、じっと耐え、雪解け後見たときは、雪でやられて腐ってしまったのか???と思ったほど弱々しげな「キャベツ苗」だったのですが、
雪解け水を吸って、ここ最近グングン成長していたものです。
信州玉ねぎも、同様で、ここ最近の成長は、めざましいものがあります。収獲は、6月末。あとしばらくです。
4月に蒔いた、「コマツナ」は一気に大きくなり青々としています。
煮びたしにしていただくと、また田舎の味です。
ニオイの強いものが好きな僕は、「春菊」を「サラダ」として食べたくて、
蒔いたのですが、こちらはまだの様子。成長が望まれます。
露地ものイチゴも真っ赤に熟し、本日初収獲。
自画自賛ですが、露地ものは「濃厚な甘さ」がします。
こうして、田舎の地物野菜の初夏の収獲がスタートしました。
これからしばらく、初夏ものの野菜が採れ食卓に並びます。
夏にいただきたい、ナスや酒のつまみの唐辛子は既に定植済み。
夏には、夏野菜の収獲があります。
季節に応じて、季節の野菜をいただく。
生でサラダに、野菜同士を煮込んだり、炒めたり。
都内にいた頃は、酒のつまみは比較的刺身が多かったのですが、
こう新鮮なものが続くと、自分で料理していただくのが一番美味いです。
長野は酒もまた美味い土地柄。
今年もつまみも酒も信州のものを満喫したいと思います。
大きくなって、割れてしまったキャベツ。
春のキャベツは、種類にもよりますが、
ビシッと密に重なり合っておらず、筍のように、柔らかな葉が
重なり合っているのが特徴。
とにかく柔らかですから、サラダが一番。

コマツナ。農薬は一切使っていませんから、虫食いがあるのはご愛嬌。

太陽を燦々と浴びるコマツナは、緑が濃い。
時季があるので、夏になると「コマツナ」は虫が付きやすくなる。
夏には、夏の野菜をいただくので、コマツナは、我が家では
比較的初夏の野菜。

一気に大きくなりたくさん収獲できたはつか大根。
昨日の雨の影響で、「割れ」が結構あった。
忙しがっていたので、「間引き」が出来ず、
スーパーで見かけるようなはつか大根ほど
大きくならなかったが、味は同じ。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
秋口、確か10月松だったような気がしますが、梨やりんご「シナノスイート」の収獲に忙しい中、顰蹙を買いながら、種を蒔き、11月に田んぼに定植したものです。
雪の下で、じっと耐え、雪解け後見たときは、雪でやられて腐ってしまったのか???と思ったほど弱々しげな「キャベツ苗」だったのですが、
雪解け水を吸って、ここ最近グングン成長していたものです。
信州玉ねぎも、同様で、ここ最近の成長は、めざましいものがあります。収獲は、6月末。あとしばらくです。
4月に蒔いた、「コマツナ」は一気に大きくなり青々としています。
煮びたしにしていただくと、また田舎の味です。
ニオイの強いものが好きな僕は、「春菊」を「サラダ」として食べたくて、
蒔いたのですが、こちらはまだの様子。成長が望まれます。
露地ものイチゴも真っ赤に熟し、本日初収獲。
自画自賛ですが、露地ものは「濃厚な甘さ」がします。
こうして、田舎の地物野菜の初夏の収獲がスタートしました。
これからしばらく、初夏ものの野菜が採れ食卓に並びます。
夏にいただきたい、ナスや酒のつまみの唐辛子は既に定植済み。
夏には、夏野菜の収獲があります。
季節に応じて、季節の野菜をいただく。
生でサラダに、野菜同士を煮込んだり、炒めたり。
都内にいた頃は、酒のつまみは比較的刺身が多かったのですが、
こう新鮮なものが続くと、自分で料理していただくのが一番美味いです。
長野は酒もまた美味い土地柄。
今年もつまみも酒も信州のものを満喫したいと思います。
大きくなって、割れてしまったキャベツ。
春のキャベツは、種類にもよりますが、
ビシッと密に重なり合っておらず、筍のように、柔らかな葉が
重なり合っているのが特徴。
とにかく柔らかですから、サラダが一番。

コマツナ。農薬は一切使っていませんから、虫食いがあるのはご愛嬌。

太陽を燦々と浴びるコマツナは、緑が濃い。
時季があるので、夏になると「コマツナ」は虫が付きやすくなる。
夏には、夏の野菜をいただくので、コマツナは、我が家では
比較的初夏の野菜。

一気に大きくなりたくさん収獲できたはつか大根。
昨日の雨の影響で、「割れ」が結構あった。
忙しがっていたので、「間引き」が出来ず、
スーパーで見かけるようなはつか大根ほど
大きくならなかったが、味は同じ。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月20日
梨の摘果続く・・・・・根気の要る作業
ゴールデンウイーク中に咲いた桃・梨・リンゴの花が結実し
摘果作業に終われる日々です。
昨日は、梨の摘果を行ないました。
ここ1週間ほど、梨・桃の摘果を行なっています。
摘果の中でも、梨は、一番難しいかもしれません。
次いで桃でしょうか。
梨は、花が5つくらい咲き、それを結実し小さな実になりますが、
大きさツルの長さ等バランスを考え、1つだけ残します。
余り深く考えていると、時間が掛かりますので、
パッとその場で「コレダ!!」と思うものを残していきます。
「粗摘果」といって、先ず1回目の摘果ですから、
気楽といってはいけないのですが、新人の僕にも比較的難しく考えずに出来る作業です。
梨は、「棚」で栽培しますが、その棚の高さが地上2メートルくらい。
身長176センチの僕にとっては、「ギリギリ」で棚の下での作業は辛いものがあります。
百貨店の婦人服に15年ほど勤めていましたが、百貨店は先ず「同じ作業」というものがありません。
接客したり、買い付けしたり、営業したり・・・・・
日々違う作業をこなしていきます。
それに比べ、摘果作業は、瞬時で見分け判断し、手際よくこなすということの繰り返しで、その繰り返し作業を、月末くらいまでずっとこなさなければなりません。
なかなか根気と経験の要る作業です。
飽きっぽい僕は、合間合間に、セリとかフキとかノビロとかを採ってきて
摘果作業を進めます。
お陰で、結構なフキ・セリが収獲できました。
今年は、是非「セリの味噌漬け」に挑戦しようかと思っています。
なんだかんだで、摘果作業中も「食べ物のこと」を考えている毎日です。
梨「幸水」の摘果作業。
小指大から親指の大きさまでの小さな実を見分けて行なう。

幸水が、出荷できるのは、北信の我が家では、9月上旬。
9月上旬から、幸水・農水・南水と味の違う梨の出荷が始まる。
これから9月まで、小さな実が大きな梨の実になるまで育てます。

梨畑の中に生えている柔らかく細いフキを採る。
身欠きにしんと煮込んだり、
砂糖とお醤油で煮込んで佃煮にしても美味しい。
摘果作業の合間にも、ついうち食べ物のことを考えてしまう。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
摘果作業に終われる日々です。
昨日は、梨の摘果を行ないました。
ここ1週間ほど、梨・桃の摘果を行なっています。
摘果の中でも、梨は、一番難しいかもしれません。
次いで桃でしょうか。
梨は、花が5つくらい咲き、それを結実し小さな実になりますが、
大きさツルの長さ等バランスを考え、1つだけ残します。
余り深く考えていると、時間が掛かりますので、
パッとその場で「コレダ!!」と思うものを残していきます。
「粗摘果」といって、先ず1回目の摘果ですから、
気楽といってはいけないのですが、新人の僕にも比較的難しく考えずに出来る作業です。
梨は、「棚」で栽培しますが、その棚の高さが地上2メートルくらい。
身長176センチの僕にとっては、「ギリギリ」で棚の下での作業は辛いものがあります。
百貨店の婦人服に15年ほど勤めていましたが、百貨店は先ず「同じ作業」というものがありません。
接客したり、買い付けしたり、営業したり・・・・・
日々違う作業をこなしていきます。
それに比べ、摘果作業は、瞬時で見分け判断し、手際よくこなすということの繰り返しで、その繰り返し作業を、月末くらいまでずっとこなさなければなりません。
なかなか根気と経験の要る作業です。
飽きっぽい僕は、合間合間に、セリとかフキとかノビロとかを採ってきて
摘果作業を進めます。
お陰で、結構なフキ・セリが収獲できました。
今年は、是非「セリの味噌漬け」に挑戦しようかと思っています。
なんだかんだで、摘果作業中も「食べ物のこと」を考えている毎日です。
梨「幸水」の摘果作業。
小指大から親指の大きさまでの小さな実を見分けて行なう。

幸水が、出荷できるのは、北信の我が家では、9月上旬。
9月上旬から、幸水・農水・南水と味の違う梨の出荷が始まる。
これから9月まで、小さな実が大きな梨の実になるまで育てます。

梨畑の中に生えている柔らかく細いフキを採る。
身欠きにしんと煮込んだり、
砂糖とお醤油で煮込んで佃煮にしても美味しい。
摘果作業の合間にも、ついうち食べ物のことを考えてしまう。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月19日
坊っちゃんかぼちゃ・・・・5月のかぼちゃ畑にて
2週間ほど前に定植した「坊っちゃんかぼちゃ」が随分と育ってきました。
昨年は、せっかく定植したものの「霜」に遭ってしまい、
また種を蒔き直し、再定植という憂き目に遭ってしまったのですが、
今年は「霜」もひどいものは無く、なんとかここまで順調にきました。
霜は、農家にとって大敵。
りんごや梨・桃などの果樹の小さな実にも被害を及ぼしますし、
小さな野菜は、致命傷となってしまうこともあります。
遅霜も「八十八夜」で終わりということになっていますが、
その通説どうりに行かないのが、自然の摂理です。
このあと、太陽の光を燦々と浴び、梅雨時の雨を吸ってグングン育っていきます。来月末には、小ぶりな「坊っちゃんかぼちゃ」が実り始めると思われます。
今日は、グングン育つことを予定して、藁を敷きました。
「坊っちゃんかぼちゃ」が傷つかないようにしたいのと、また
草が坊っちゃんかぼちゃの成長を阻まないようにするためです。
草は、農家にとっては大敵。
昨年は、「百姓は、草との戦いだ!」と号令をかけられ、
りんご畑・梨畑など果樹を始め、野菜の草退治を
百姓の新人の僕は、専らしました。
除草剤を使えば簡単なのですが、
除草剤は、使いたくありません。
藁を敷いて、草の成長を妨げたり、こまめに草取りをしたり・・・・。
徐々に出来ることからスタートしていきたいと思います。
新人の割には、結構年齢がいっているのですが、
まあ長い人生と思って、ノンビリやりたいと思います。
咲き始めた「坊っちゃんかぼちゃの花」

既に、かぼちゃの実が付き始めています。
受粉は、蜂に任せます。

ビニールシートを敷くと、草が生えないのですが、
今度はせっかくの雨水が、土にしみこまなくなります。
ここは、昔ながらの「藁」を使います。
農家にとって「藁」は、大変重宝します。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
昨年は、せっかく定植したものの「霜」に遭ってしまい、
また種を蒔き直し、再定植という憂き目に遭ってしまったのですが、
今年は「霜」もひどいものは無く、なんとかここまで順調にきました。
霜は、農家にとって大敵。
りんごや梨・桃などの果樹の小さな実にも被害を及ぼしますし、
小さな野菜は、致命傷となってしまうこともあります。
遅霜も「八十八夜」で終わりということになっていますが、
その通説どうりに行かないのが、自然の摂理です。
このあと、太陽の光を燦々と浴び、梅雨時の雨を吸ってグングン育っていきます。来月末には、小ぶりな「坊っちゃんかぼちゃ」が実り始めると思われます。
今日は、グングン育つことを予定して、藁を敷きました。
「坊っちゃんかぼちゃ」が傷つかないようにしたいのと、また
草が坊っちゃんかぼちゃの成長を阻まないようにするためです。
草は、農家にとっては大敵。
昨年は、「百姓は、草との戦いだ!」と号令をかけられ、
りんご畑・梨畑など果樹を始め、野菜の草退治を
百姓の新人の僕は、専らしました。
除草剤を使えば簡単なのですが、
除草剤は、使いたくありません。
藁を敷いて、草の成長を妨げたり、こまめに草取りをしたり・・・・。
徐々に出来ることからスタートしていきたいと思います。
新人の割には、結構年齢がいっているのですが、
まあ長い人生と思って、ノンビリやりたいと思います。
咲き始めた「坊っちゃんかぼちゃの花」

既に、かぼちゃの実が付き始めています。
受粉は、蜂に任せます。

ビニールシートを敷くと、草が生えないのですが、
今度はせっかくの雨水が、土にしみこまなくなります。
ここは、昔ながらの「藁」を使います。
農家にとって「藁」は、大変重宝します。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月18日
ルバーブを使って・・・・・・手造りジャム第1弾
昨年ワラビを採りに行った叔母がお土産に信濃町で「ルバーブ」の苗を
買ってきてくれ、定植し、ほぼ1年が経ちました。
ルバーブは、もともとはロシアのシベリア原産で、
よく野で見かける「スカンボ」の仲間だそうです。
信濃町は、野尻湖があり別荘地がたくさんあることから、
別荘で過ごす外人さんが、栽培を始め、
「酸っぱい美味しさ」が受けたのでしょうか、徐々に広まってきました。
僕は、「ルバーブ」を全く知らず、こちらに戻ってきてから知りました。
「ルバーブジャム」でいただいたのが始まりで、酸味が強いのですが
その「酸っぱさ」に感動し、大ファンになり、
自分で作りたいと前々から思っていたのです。
種類は、茎が赤いものと黄色いものがあるそうですが、
「赤い」方が味は良好との事です。
ジャムの作り方は、いたって簡単で、「葉柄」の刻んで煮込んでいくだけです。
子供の頃から、祖母にイチゴジャムを作る際、焦げないように
常に鍋のそばにいて、かき混ぜるよう言われ、ジャム作りは経験があったため、比較的簡単に出来ました。
酸味が強いのですが、甘味は砂糖を加え自分で調整できます。
すぐにいただくものは、比較的砂糖を少なく、
長期で瓶詰めで保存するものは砂糖多めで煮込みました。
このあと、イチゴの収獲が始まり、しばらくすると、我が家では栽培していませんが
杏も、美味しい季節となります。
この二つは、もちろん「生」も美味しいのですが、ジャムも非常に美味です。
こうして「ルバーブジャム」「杏ジャム」「イチゴジャム」と手造りし、
1年を通して、毎朝いただきます。
唯一、我が家で文句を言われつつも、朝食にご飯が馴染めず、毎日ジャムをこってりと付けて
いただく僕には、ジャムは欠かせません。
昨年は、秋には、保存のジャムが無くなり、市販ジャムに変更し
物足りなさを感じましたので、意気込みたいと思っています。
りんごのジャム作りに、今年はチャレンジしようと思っていたのですが、
遂に作らずじまいになってしまいました。
くだものを生のままいただくのが一番ですが、
ジャムにして、いつまでも楽しむのも、また楽しみの一つです。
ルバーブの根元。この葉柄を煮込む。
アグリ長沼では、ふきの棒くらいの長さのものが販売されていたが、
我が家の裏庭は、「ルバーブ」にあうのか。
かなり大きくなった。

ルバーブジャムの味をシメタ僕は、今年は、3つルバーブ苗を定植。
昨年定植のものは、1年で上の写真のようになった。
来年の成長が楽しみ。

砂糖加減で、固さ・甘さ自由に調節可能。
酸味が特徴なので、イチゴジャムや杏ジャムと味わい比べるのも楽しい。
イチゴ・杏と比べると、「香り」は余り無い。
農産物直売所「アグリ長沼」でも販売されていた。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
買ってきてくれ、定植し、ほぼ1年が経ちました。
ルバーブは、もともとはロシアのシベリア原産で、
よく野で見かける「スカンボ」の仲間だそうです。
信濃町は、野尻湖があり別荘地がたくさんあることから、
別荘で過ごす外人さんが、栽培を始め、
「酸っぱい美味しさ」が受けたのでしょうか、徐々に広まってきました。
僕は、「ルバーブ」を全く知らず、こちらに戻ってきてから知りました。
「ルバーブジャム」でいただいたのが始まりで、酸味が強いのですが
その「酸っぱさ」に感動し、大ファンになり、
自分で作りたいと前々から思っていたのです。
種類は、茎が赤いものと黄色いものがあるそうですが、
「赤い」方が味は良好との事です。
ジャムの作り方は、いたって簡単で、「葉柄」の刻んで煮込んでいくだけです。
子供の頃から、祖母にイチゴジャムを作る際、焦げないように
常に鍋のそばにいて、かき混ぜるよう言われ、ジャム作りは経験があったため、比較的簡単に出来ました。
酸味が強いのですが、甘味は砂糖を加え自分で調整できます。
すぐにいただくものは、比較的砂糖を少なく、
長期で瓶詰めで保存するものは砂糖多めで煮込みました。
このあと、イチゴの収獲が始まり、しばらくすると、我が家では栽培していませんが
杏も、美味しい季節となります。
この二つは、もちろん「生」も美味しいのですが、ジャムも非常に美味です。
こうして「ルバーブジャム」「杏ジャム」「イチゴジャム」と手造りし、
1年を通して、毎朝いただきます。
唯一、我が家で文句を言われつつも、朝食にご飯が馴染めず、毎日ジャムをこってりと付けて
いただく僕には、ジャムは欠かせません。
昨年は、秋には、保存のジャムが無くなり、市販ジャムに変更し
物足りなさを感じましたので、意気込みたいと思っています。
りんごのジャム作りに、今年はチャレンジしようと思っていたのですが、
遂に作らずじまいになってしまいました。
くだものを生のままいただくのが一番ですが、
ジャムにして、いつまでも楽しむのも、また楽しみの一つです。
ルバーブの根元。この葉柄を煮込む。
アグリ長沼では、ふきの棒くらいの長さのものが販売されていたが、
我が家の裏庭は、「ルバーブ」にあうのか。
かなり大きくなった。

ルバーブジャムの味をシメタ僕は、今年は、3つルバーブ苗を定植。
昨年定植のものは、1年で上の写真のようになった。
来年の成長が楽しみ。

砂糖加減で、固さ・甘さ自由に調節可能。
酸味が特徴なので、イチゴジャムや杏ジャムと味わい比べるのも楽しい。
イチゴ・杏と比べると、「香り」は余り無い。
農産物直売所「アグリ長沼」でも販売されていた。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月17日
初夏の風物いろいろ
五月も半ばとなりました。
イチゴがようやく赤く染まり、きゅうりは小さな実を付けました。
雪解けのあと、「腐ってしまったのか???」と思った晩秋に定植した
キャベツは、生命力を多いに発揮し、かなり大きくなりました。
「春キャベツ」が市場で出回っていますが、北信濃では、晩秋に定植したキャベツの苗が、明けてこの春に、活動を再スタートし、今の時季あたりから、一気に成長を早め、「北信濃の春キャベツ」となります。
地物の「柔らかな春キャベツ」をいただけるまでもう少しのようです。
5月といえば、やはり男の子は「鯉のぼり」
鯉のぼりで浮かべるのは、
屋根より高い 鯉のぼり 大きい 真鯉はお父さん・・・・・・・
でしょうか。
比較的忘れがちなのが、
甍の波と雲の波
重なる波の 中空を
橘かおる 朝風に
高く泳ぐや 鯉のぼり
小学校で習った記憶が無いのですが、
僕はこちらのリズムも好きです。
空の鯉も、気持ちよく泳いでいるでしょう。
都内での生活をしていた頃は、
マンションのベランダから見える「小さな鯉」でしたが、
こちらの鯉は、大空を存分に泳いでいる様子。
そろそろ鯉も終わりの季節。
鯉のぼり・春キャベツ・・・・・
初夏の装いも日々変わっています。
露地もののイチゴも、赤く熟し始めた。
太陽を燦々と浴びた「露地もの」は甘さが濃厚。

きゅうりが花を付けた。
トゲやイボイボがあるある田舎ならではのきゅうりである。

「玉」が大きくなり始めたキャベツ。
祖母は、「たまな」とキャベツのことを呼んでいた。
玉のような「お菜」から来たのだろうか?
たまなの季節になると、エンドウが実を付ける。
たまなとエンドウのにつけも美味しい。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
イチゴがようやく赤く染まり、きゅうりは小さな実を付けました。
雪解けのあと、「腐ってしまったのか???」と思った晩秋に定植した
キャベツは、生命力を多いに発揮し、かなり大きくなりました。
「春キャベツ」が市場で出回っていますが、北信濃では、晩秋に定植したキャベツの苗が、明けてこの春に、活動を再スタートし、今の時季あたりから、一気に成長を早め、「北信濃の春キャベツ」となります。
地物の「柔らかな春キャベツ」をいただけるまでもう少しのようです。
5月といえば、やはり男の子は「鯉のぼり」
鯉のぼりで浮かべるのは、
屋根より高い 鯉のぼり 大きい 真鯉はお父さん・・・・・・・
でしょうか。
比較的忘れがちなのが、
甍の波と雲の波
重なる波の 中空を
橘かおる 朝風に
高く泳ぐや 鯉のぼり
小学校で習った記憶が無いのですが、
僕はこちらのリズムも好きです。
空の鯉も、気持ちよく泳いでいるでしょう。
都内での生活をしていた頃は、
マンションのベランダから見える「小さな鯉」でしたが、
こちらの鯉は、大空を存分に泳いでいる様子。
そろそろ鯉も終わりの季節。
鯉のぼり・春キャベツ・・・・・
初夏の装いも日々変わっています。
露地もののイチゴも、赤く熟し始めた。
太陽を燦々と浴びた「露地もの」は甘さが濃厚。

きゅうりが花を付けた。
トゲやイボイボがあるある田舎ならではのきゅうりである。

「玉」が大きくなり始めたキャベツ。
祖母は、「たまな」とキャベツのことを呼んでいた。
玉のような「お菜」から来たのだろうか?
たまなの季節になると、エンドウが実を付ける。
たまなとエンドウのにつけも美味しい。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
Posted by ドジヒコ at
06:12
│Comments(0)
2008年05月16日
たくあんを使って・・・・・・化粧直しをして再登場
昨年の初頭に漬けたものに野沢菜とたくあんがあります。
野沢菜は、信州ならではの漬物。
たくあんは、広く全国で漬けられますが、このあたりの農家では、
たくあん用の大根から栽培しますから、結構な量が漬けられます。
今の時季になると、「春キャベツ」が出てきますから、「浅漬け」が
漬物としては、結構食卓に上っているのではないでしょうか。
12月から約4ヶ月ほど、我が家の食卓に上った野沢菜やたくあんも
暖かくなると同時に終わりです。
結構な量を、野沢菜・たくあんとも漬け、冬場の保存食として重宝されますが、今の時季になると、両者とも酸っぱくなります。
野沢菜は過日に、炒めていただく方法をご紹介しましたが、
たくあんも炒めて、また違った味わいの一品として食卓に上ります。
結構な量が、余ってしまった今年。
捨てるのももったいないので、先ずは、「塩抜き」
散々、初頭の頃には、干した大根に塩を入れて、漬け込むたくあんですが、今の時季には、逆にその「塩を抜く」というのですからおかしい。
でも、散々「塩気のある味のたくあん」を楽しんだ後に、
今度は炒めたたくあんをいただけるのですから、「保存食としてのたくあん」は、やはり優れものです。
何度も水を替え、塩を抜いたあと、今度はお醤油で炒めます。
今回も、野沢菜を炒めたのと同様、「鰹節と唐辛子」が使われます。
1年を通じて思ったのですが、とにかく「唐辛子」「鷹の爪」をよく使います。今年は、是非「唐辛子」「鷹の爪」とも自給したいものだと思っています。
油で炒めたたくあんは、塩気が無く、たくあんの面影は余り無いのですが、ピリリと辛味のある炒め物に変身し、酒のつまみとして、ご飯のはし休めとして、重宝されます。
保存食としての漬物のたくあんも、最後までこうしていただけると思うと、優れものと痛感する次第です。
たくあんの古漬けをスライスして、何度も水を交換して
塩気を抜く。
醤油を使い、粉カツオ・唐辛子を加え炒める。
お好みで、辛さを変えて。
酒飲みの僕は、辛めにして、つまみとして頂く。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
野沢菜は、信州ならではの漬物。
たくあんは、広く全国で漬けられますが、このあたりの農家では、
たくあん用の大根から栽培しますから、結構な量が漬けられます。
今の時季になると、「春キャベツ」が出てきますから、「浅漬け」が
漬物としては、結構食卓に上っているのではないでしょうか。
12月から約4ヶ月ほど、我が家の食卓に上った野沢菜やたくあんも
暖かくなると同時に終わりです。
結構な量を、野沢菜・たくあんとも漬け、冬場の保存食として重宝されますが、今の時季になると、両者とも酸っぱくなります。
野沢菜は過日に、炒めていただく方法をご紹介しましたが、
たくあんも炒めて、また違った味わいの一品として食卓に上ります。
結構な量が、余ってしまった今年。
捨てるのももったいないので、先ずは、「塩抜き」
散々、初頭の頃には、干した大根に塩を入れて、漬け込むたくあんですが、今の時季には、逆にその「塩を抜く」というのですからおかしい。
でも、散々「塩気のある味のたくあん」を楽しんだ後に、
今度は炒めたたくあんをいただけるのですから、「保存食としてのたくあん」は、やはり優れものです。
何度も水を替え、塩を抜いたあと、今度はお醤油で炒めます。
今回も、野沢菜を炒めたのと同様、「鰹節と唐辛子」が使われます。
1年を通じて思ったのですが、とにかく「唐辛子」「鷹の爪」をよく使います。今年は、是非「唐辛子」「鷹の爪」とも自給したいものだと思っています。
油で炒めたたくあんは、塩気が無く、たくあんの面影は余り無いのですが、ピリリと辛味のある炒め物に変身し、酒のつまみとして、ご飯のはし休めとして、重宝されます。
保存食としての漬物のたくあんも、最後までこうしていただけると思うと、優れものと痛感する次第です。
たくあんの古漬けをスライスして、何度も水を交換して
塩気を抜く。

醤油を使い、粉カツオ・唐辛子を加え炒める。
お好みで、辛さを変えて。
酒飲みの僕は、辛めにして、つまみとして頂く。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月15日
名勝つつじ山を歩く
豊野町の名勝「つつじ山」に出かけました。
「つつじ山」は、豊野町川谷地区にあり、ツツジが山肌を這うように群生している名勝です。
国道18号線を信濃町方面に北上して行くと、左手に今であれば
つつじの花で「朱色」に染まった山肌を見つけることが出来ます。
川谷地区の氏神として鎮座している「冨士社」という神社があり、
その裏手にツツジが咲き誇っています。
明治時代辺りから整備が進み、5月半ばの「冨士社」の祭礼日には、
つつじも花が見ごろのことから、「つつじ山祭り」が開かれ、
近隣からも大勢の花見客が、訪れたようです。
今年の「つつじ山祭り」は、5月10日に開催され、忙しがって行けませんでしたが
地元の主婦たちが「おやきの屋台」を出したり、好評だったようです。
つつじ山はそんな高い山では無いため、15分くらいで頂上まで登れます。その頂上への途上に、数々の石碑類が建っていて、多数の見物客が訪れたことを物語っています。
遠くは上杉謙信 田山花袋も訪れたようですし、松本出身の大陸浪人でかの川島芳子の育ての親 川島浪速の句碑、
はたまた、須坂の製糸匿名組合「山丸組」の石碑もあります。
山丸組は、須坂の製糸組合の一つで、いわば企業カルテルといってもいいのではないでしょうか、
須坂の町を岡谷に並ぶ製糸の町に押し上げた中核の一つです。
製糸王国信州の一翼を担った組織のひとつであり、
女工さんたちの朝から晩までの労働も製糸王国信州の担い手です。
製糸の町須坂のことは、また次回に譲るとして、
朝早くから夜遅くまで働いた女工さんたちが、日頃の疲れを癒せたでしょうか、遠足に訪れたりしたようですし、
つつじ山を整備するために、寄付までしてくれたそうです。
往時の繁盛こそありませんが、つつじ山は人気だったのでしょう。
僕が行った昨日は、既に「ツツジも終わり」であったにもかかわらず
思った以上の人出でした。
行政の合併により、こうした地区・地域の小行事に目が届かなくなりがちですが、いつまでも遠い昔から愛され、多くの訪れた見物客を楽しませてくれた小さな山をめぐっての人々の営み・喜びは続いてほしいと思います。
山肌に這うつつじ。明治に整備された際のツツジですから
樹齢100年以上。数々の見物客を和ませてくれます。

頂上には東屋が建ち、15分ほどの山道を登る疲れを癒してくれる。
ちょっとしたお散歩がてらには、最適な場所である。
この裏手には、「丹霞郷」に続く林道があり、新緑の季節、
林道を歩いて、森林浴をしつつ歩くのも楽しい。

山頂から、千曲川方面を望む。
善光寺平の向こうの山々は志賀高原。

山肌を覆うツツジ。一本高い木があるが、アカシデ。
この高木の木の下に川島浪速の句碑がある。
「男装の麗人」川島芳子の句碑も浅野正見寺にあるというから、
親子でこの豊野にゆかりが合ったということである。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
「つつじ山」は、豊野町川谷地区にあり、ツツジが山肌を這うように群生している名勝です。
国道18号線を信濃町方面に北上して行くと、左手に今であれば
つつじの花で「朱色」に染まった山肌を見つけることが出来ます。
川谷地区の氏神として鎮座している「冨士社」という神社があり、
その裏手にツツジが咲き誇っています。
明治時代辺りから整備が進み、5月半ばの「冨士社」の祭礼日には、
つつじも花が見ごろのことから、「つつじ山祭り」が開かれ、
近隣からも大勢の花見客が、訪れたようです。
今年の「つつじ山祭り」は、5月10日に開催され、忙しがって行けませんでしたが
地元の主婦たちが「おやきの屋台」を出したり、好評だったようです。
つつじ山はそんな高い山では無いため、15分くらいで頂上まで登れます。その頂上への途上に、数々の石碑類が建っていて、多数の見物客が訪れたことを物語っています。
遠くは上杉謙信 田山花袋も訪れたようですし、松本出身の大陸浪人でかの川島芳子の育ての親 川島浪速の句碑、
はたまた、須坂の製糸匿名組合「山丸組」の石碑もあります。
山丸組は、須坂の製糸組合の一つで、いわば企業カルテルといってもいいのではないでしょうか、
須坂の町を岡谷に並ぶ製糸の町に押し上げた中核の一つです。
製糸王国信州の一翼を担った組織のひとつであり、
女工さんたちの朝から晩までの労働も製糸王国信州の担い手です。
製糸の町須坂のことは、また次回に譲るとして、
朝早くから夜遅くまで働いた女工さんたちが、日頃の疲れを癒せたでしょうか、遠足に訪れたりしたようですし、
つつじ山を整備するために、寄付までしてくれたそうです。
往時の繁盛こそありませんが、つつじ山は人気だったのでしょう。
僕が行った昨日は、既に「ツツジも終わり」であったにもかかわらず
思った以上の人出でした。
行政の合併により、こうした地区・地域の小行事に目が届かなくなりがちですが、いつまでも遠い昔から愛され、多くの訪れた見物客を楽しませてくれた小さな山をめぐっての人々の営み・喜びは続いてほしいと思います。
山肌に這うつつじ。明治に整備された際のツツジですから
樹齢100年以上。数々の見物客を和ませてくれます。

頂上には東屋が建ち、15分ほどの山道を登る疲れを癒してくれる。
ちょっとしたお散歩がてらには、最適な場所である。
この裏手には、「丹霞郷」に続く林道があり、新緑の季節、
林道を歩いて、森林浴をしつつ歩くのも楽しい。

山頂から、千曲川方面を望む。
善光寺平の向こうの山々は志賀高原。

山肌を覆うツツジ。一本高い木があるが、アカシデ。
この高木の木の下に川島浪速の句碑がある。
「男装の麗人」川島芳子の句碑も浅野正見寺にあるというから、
親子でこの豊野にゆかりが合ったということである。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月14日
土手の楽しみ
最近は分かりませんが、僕が子供の頃
昭和50年代にはよく「土手」(堤防)で遊んだものです。
土手には、色々な植物があって、その植物がどんな植物か、どんな風に遊べるか、友達同士や近所のお兄さんやお姉さんに教わりつつ、覚えていったものである。
色々調べたくって、図鑑をおねだりして買ってもらったこともありましたが、地域によって植生が違うからでしょうか、このあたりの植生の草木が必ず乗っているとは限らず、お兄さん・お姉さんに聞くのが一番早く分かり易かった。
学校以外に、熟に通うことが当たり前になった昨今では、
そんな暇は無いかもしれません。
でも、「暇」があることが、子供の特権であったと思うのです。
子供は大人と違って、「暇」さえあれば、
ゴロゴロしているわけでもありませんから、
土手に遊びに行ったり、川に魚を捕まえに行ったり・・・・。
子供の視点も多い小林一茶の句に
「やれ打つな 蝿が手をすり 足をする」
というのがあります。
作家の田辺聖子さんがおっしゃるには、
子供は、暇人だから止まった蝿が、足や手をすり合わせたりするのを
よく観察できます。
大人になると、蝿の仕草など観察しませんでしょう。
暇な子供ならではの「特権」であると。
(八十二文化財団 地域文化参考)
最近の子供たちは、忙しいのか土手で遊んでいる様子も見掛けません。暇でも無いようですから、僕らの子供の頃のように、蝿を観察したりすることも無いのでは??
土手では、遊びもしましたが、
ニラを取ったり、ノビロをとったり。
ニラは、自然に生えている自生のニラが一番美味しいそうです。
ノビロは、お焼きにしていただくと美味しい。
この年になると、土手に遊びに行くわけに行きませんが、
なるべく自然に触れたいと思う今日この頃です。
土手のノビロ。
「野蒜」(のびる)が正式な呼び名のようですが、
この辺りでは、「ノビロ」です。
根っこの玉は、細かく刻んでいただくと美味しい。
葉は、細かく刻んでおやきの具にすると、これまた美味しい。

帰化植物「ヒメノ踊り子草」
ピンクの花の部分に甘味があって、「チュチュウ」吸ったものです。
しかし昨今の「ヒメノ踊り子草」の繁殖には驚くものがあります。
帰化植物ですが、完全に全国を制覇したのではないでしょうか?

スカンポ 正式名称「スイバ」
酸っぱい茎が特徴で、よく噛んだものです。
もう「野生の草」をしゃぶるようなことはしないでしょう。
「ゆとり教育」ってのがありましたが、「ゆとり」とは、学校で敢えて教えるものではないと思うのですが・・・・・。
野や山で遊んで、子供の視点で考え・ものを見る。
それが「ゆとり」だと思うのですが・・・・・。

野生のセリ。毒ぜりもありますから注意が必要です。
サッと茹でて、粉カツオをかけて、お醤油のみ。
このニオイがたまりません。
酒好きの僕には、「個性ある」強烈なニオイや味のものは、堪りません。
善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
昭和50年代にはよく「土手」(堤防)で遊んだものです。
土手には、色々な植物があって、その植物がどんな植物か、どんな風に遊べるか、友達同士や近所のお兄さんやお姉さんに教わりつつ、覚えていったものである。
色々調べたくって、図鑑をおねだりして買ってもらったこともありましたが、地域によって植生が違うからでしょうか、このあたりの植生の草木が必ず乗っているとは限らず、お兄さん・お姉さんに聞くのが一番早く分かり易かった。
学校以外に、熟に通うことが当たり前になった昨今では、
そんな暇は無いかもしれません。
でも、「暇」があることが、子供の特権であったと思うのです。
子供は大人と違って、「暇」さえあれば、
ゴロゴロしているわけでもありませんから、
土手に遊びに行ったり、川に魚を捕まえに行ったり・・・・。
子供の視点も多い小林一茶の句に
「やれ打つな 蝿が手をすり 足をする」
というのがあります。
作家の田辺聖子さんがおっしゃるには、
子供は、暇人だから止まった蝿が、足や手をすり合わせたりするのを
よく観察できます。
大人になると、蝿の仕草など観察しませんでしょう。
暇な子供ならではの「特権」であると。
(八十二文化財団 地域文化参考)
最近の子供たちは、忙しいのか土手で遊んでいる様子も見掛けません。暇でも無いようですから、僕らの子供の頃のように、蝿を観察したりすることも無いのでは??
土手では、遊びもしましたが、
ニラを取ったり、ノビロをとったり。
ニラは、自然に生えている自生のニラが一番美味しいそうです。
ノビロは、お焼きにしていただくと美味しい。
この年になると、土手に遊びに行くわけに行きませんが、
なるべく自然に触れたいと思う今日この頃です。
土手のノビロ。
「野蒜」(のびる)が正式な呼び名のようですが、
この辺りでは、「ノビロ」です。
根っこの玉は、細かく刻んでいただくと美味しい。
葉は、細かく刻んでおやきの具にすると、これまた美味しい。

帰化植物「ヒメノ踊り子草」
ピンクの花の部分に甘味があって、「チュチュウ」吸ったものです。
しかし昨今の「ヒメノ踊り子草」の繁殖には驚くものがあります。
帰化植物ですが、完全に全国を制覇したのではないでしょうか?

スカンポ 正式名称「スイバ」
酸っぱい茎が特徴で、よく噛んだものです。
もう「野生の草」をしゃぶるようなことはしないでしょう。
「ゆとり教育」ってのがありましたが、「ゆとり」とは、学校で敢えて教えるものではないと思うのですが・・・・・。
野や山で遊んで、子供の視点で考え・ものを見る。
それが「ゆとり」だと思うのですが・・・・・。

野生のセリ。毒ぜりもありますから注意が必要です。

サッと茹でて、粉カツオをかけて、お醤油のみ。
このニオイがたまりません。
酒好きの僕には、「個性ある」強烈なニオイや味のものは、堪りません。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月13日
美味しい田んぼでいただく「スイーツ」の定植
梨の摘果の合間を縫って、「スイカとプリンスメロン」の定植を行ないました。
昨年は、スイカの種「タヒチ」を購入して、蒔いたらほぼ100%発芽し、
結構な量のスイカの定植となりましたが、スイカは、
「熟れているかどうか」見極めるのが難しく、「美味しいかどうか???」
なかなか分からず、というわけで昨年のスイカ栽培は、結構大変でした。
暑い盛りに、田んぼから獲ってきて、ちょっと一服の時に
田んぼで、割っていただくと、最高です。
去年も、結構実ったのですが、ほとんど田んぼで一服の時にいただきました。冷えてはおりませんが、その場でみんなでいただくスイカは美味しいものです。
今年も、田んぼでの一服の時にいただけるよう、「大玉スイカ」と
甘さが強い「黒いスイカ」を定植しました。
スイカもメロンも比較的定植した時は、弱いため
「風の影響」を受けないように「行灯」といって
定植した苗の周りを囲ってあげます。
スイカとメロンは、比較的根っこが弱いそうです。
しばらく行灯で囲ってあげて、見守ってあげたいと思います。
ドンドン大きくなるのを期待したい「スイカ」

新聞紙を再利用。
定植した苗を、囲ってあげ、守ります。
「行灯」のように見えますよね。
今は、「パオパオ」と言う不敷布で覆う場合が多いのですが、
「スイカ」は、敢えて新聞紙で行灯を作ってみました。

行灯の行列。
こんな風景を、豊野町浅野あたりでは、ちょくちょく見かけます。

プリンスメロン。
子供の頃から「プリンスメロン」でしたから、
網が掛かった「マスクメロン」は、マスクの方がお値段もいいのですが、
どうも「マスクメロン」のような網がけメロンは苦手です。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
昨年は、スイカの種「タヒチ」を購入して、蒔いたらほぼ100%発芽し、
結構な量のスイカの定植となりましたが、スイカは、
「熟れているかどうか」見極めるのが難しく、「美味しいかどうか???」
なかなか分からず、というわけで昨年のスイカ栽培は、結構大変でした。
暑い盛りに、田んぼから獲ってきて、ちょっと一服の時に
田んぼで、割っていただくと、最高です。
去年も、結構実ったのですが、ほとんど田んぼで一服の時にいただきました。冷えてはおりませんが、その場でみんなでいただくスイカは美味しいものです。
今年も、田んぼでの一服の時にいただけるよう、「大玉スイカ」と
甘さが強い「黒いスイカ」を定植しました。
スイカもメロンも比較的定植した時は、弱いため
「風の影響」を受けないように「行灯」といって
定植した苗の周りを囲ってあげます。
スイカとメロンは、比較的根っこが弱いそうです。
しばらく行灯で囲ってあげて、見守ってあげたいと思います。
ドンドン大きくなるのを期待したい「スイカ」

新聞紙を再利用。
定植した苗を、囲ってあげ、守ります。
「行灯」のように見えますよね。
今は、「パオパオ」と言う不敷布で覆う場合が多いのですが、
「スイカ」は、敢えて新聞紙で行灯を作ってみました。

行灯の行列。
こんな風景を、豊野町浅野あたりでは、ちょくちょく見かけます。

プリンスメロン。
子供の頃から「プリンスメロン」でしたから、
網が掛かった「マスクメロン」は、マスクの方がお値段もいいのですが、
どうも「マスクメロン」のような網がけメロンは苦手です。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年05月12日
梨の摘果作業・・・・・・・若い青葉の季節に
梨の花が咲いてからほぼ2週間ほど経ちました。
可憐な花は、散り若葉が棚を覆い梨の小さな実がいくつも見えるようになりました。
開花中に行なった、蜂や僕たちの「受粉作業」が実を結んだのか
小さな梨の実がたくさん付いています。
このまま全て、秋に収獲できませんから、梨の実が5~6個付いている
集団の中から一つだけ残し、後は取り除きます。
この残った1つが、秋には美味しい梨の実になると言うわけです。
今回は、「粗摘果」といって、第1回目の大まかな「摘果」です。
この「摘果作業」を何度か経て、選りすぐりのものが、
大きな梨の実となって、収獲できると言うわけです。
今日行なったのは、「南水」という長野県生まれの
甘さとコクがある一番人気の梨です。
梨の摘果を行ないつつ、桃・りんごの小さな実の成長具合を見ます。
梨も、このあと「幸水・あきづき・豊水」を行ないつつ
りんご・桃の摘果も行なわなければなりません。
夏の作業では、一番忙しい時期といっても過言では無いでしょう。
午前中は、まさに「慈雨」とも言うべき雨が久しぶりに降りました。
この雨を吸って、野菜も成長し、木々の緑も益々青さを増していくでしょう。もちろん、りんご畑や梨畑の下草も成長すること間違いなし。
花の季節から「若葉の季節」へ。
若葉もこんなに「柔らかで爽やかな青」は、うれしくなります。
田んぼの梨の若葉を見つつ、「摘果」を進めていると、
思わず
「この柔らかな葉っぱはサラダでいただけるのでは???」
と思うほどです。
小さな実がたくさん付いた。
この実を選り分けて「摘果」を行なう。

たくさんあった実を1つだけ残す。
どれを残すのか見分けるのも難しい。

梨の若葉。
柔らかくて、「青さ」が瑞々しくて、そのまま食べられそう。
余りの柔らかさは、お茶畑の「茶」の葉っぱに似ているとよく思う。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
可憐な花は、散り若葉が棚を覆い梨の小さな実がいくつも見えるようになりました。
開花中に行なった、蜂や僕たちの「受粉作業」が実を結んだのか
小さな梨の実がたくさん付いています。
このまま全て、秋に収獲できませんから、梨の実が5~6個付いている
集団の中から一つだけ残し、後は取り除きます。
この残った1つが、秋には美味しい梨の実になると言うわけです。
今回は、「粗摘果」といって、第1回目の大まかな「摘果」です。
この「摘果作業」を何度か経て、選りすぐりのものが、
大きな梨の実となって、収獲できると言うわけです。
今日行なったのは、「南水」という長野県生まれの
甘さとコクがある一番人気の梨です。
梨の摘果を行ないつつ、桃・りんごの小さな実の成長具合を見ます。
梨も、このあと「幸水・あきづき・豊水」を行ないつつ
りんご・桃の摘果も行なわなければなりません。
夏の作業では、一番忙しい時期といっても過言では無いでしょう。
午前中は、まさに「慈雨」とも言うべき雨が久しぶりに降りました。
この雨を吸って、野菜も成長し、木々の緑も益々青さを増していくでしょう。もちろん、りんご畑や梨畑の下草も成長すること間違いなし。
花の季節から「若葉の季節」へ。
若葉もこんなに「柔らかで爽やかな青」は、うれしくなります。
田んぼの梨の若葉を見つつ、「摘果」を進めていると、
思わず
「この柔らかな葉っぱはサラダでいただけるのでは???」
と思うほどです。
小さな実がたくさん付いた。
この実を選り分けて「摘果」を行なう。

たくさんあった実を1つだけ残す。
どれを残すのか見分けるのも難しい。

梨の若葉。
柔らかくて、「青さ」が瑞々しくて、そのまま食べられそう。
余りの柔らかさは、お茶畑の「茶」の葉っぱに似ているとよく思う。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト