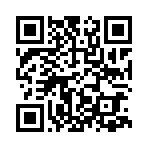2014年08月27日
夏の終わりに・・・・。
先のアジア太平洋戦争中、
長野県は首都圏の小中学校の疎開先として、
多数の小中学生を受け入れました。
東京元浅草に生まれた永六輔さんも小諸に疎開し、
地元の学童からいじめられたという話は有名ですが、
父母と離れ、毎日異郷の地で過ごすということは
小学生にとってはさぞや辛かったことと思います。
先日、戦時中を知る近所のおじさんと疎開の話が出ましたが、
ここ長野市豊野町でも学童の疎開を受け入れたそうです。
当時、今の豊野町は、戦後合併する以前
西部地域を「神郷村」、東部地域が「鳥居村」に分かれていました。
多くの東京からの学童疎開は、志賀高原のふもとの山ノ内町の
湯田中温泉や渋温泉で受け入れたそうですが、
余りの温泉郷への集中疎開で、食糧問題等の弊害が出て、
再度、山ノ内町地区から、北信(長野県の北部、長野市以北の地域)に分散して、疎開がなされたそうです。
旧鳥居村では、豊島区の高田地区の約120名ほどが、
再疎開し、男子は、浅野地区のお寺 正見寺に
女子は、そのお寺のそばにある公会堂に疎開したそうです。
豊野町町誌など、文献を調べてみたのですが、
疎開のことは余り載っておらず、
詳しい生活の様子はわかりかねるのですが、
写真の公会堂で、約7ヶ月間という短い期間であたものの、
疎開生活がなされたようです。
その女子児童が疎開した中町公会堂は、
曹洞宗のお寺の宝蔵院の隣にあります。
宝蔵院には、ミャンマー(旧ビルマ)のインパール作戦に従軍して、
奇跡的に助かり帰還した方が中心となり、
二度とこのような戦争が起きぬ様にと、
平成の時代に「平和の鐘」が設置されたお寺です。
その宝蔵院の隣にこの「中町公会堂」が位置し、
都会生まれの女子生徒が親元を離れ、寝起きしたのです。
何とも頼りない建物での女子生徒50名ほどの
まだ親が恋しい子供達のとっての集団生活は、
さぞやきつかったことと思われます。
せめてもの救いは、当時、ここ豊野町東部の鳥居村地区では、
米も野菜も果物も首都圏と比べ流通していたはずで、
空腹に悩まされたということは無かったのではないかと推察します。
戦争中当時の様子を伺うことが出来る方々が、
かなり高齢となってきました。
高齢の方々が積極的に戦争について
語ることは少なくなってきており
我々現役世代が少しでも多くの方と出会いお話を伺って、
後世にこのようなことが二度と起きないように
戦争の悲惨さをリレーしていく時代となりました。
長野県は、蚕を中心とする生糸産業(工業・農業ともに)が
日本で一番盛んで製糸・養蚕産業への偏重の余り、
生糸の価格の暴落による手痛い打撃のため、
市街地も農村もおおいに疲弊しました。
それが一つの要因となり、
結果的に多くの満洲への移民を、
「長野県の政策」として出さざるを得なくなり、
満洲移民が全国で一番多かった県です。
そして結果的に満洲への移民は
戦後に多くの悲劇を生みました。
戦争を実際に経験していない世代が、大半となり、
僕たちは、「当たり前のように」豊かな時代を謳歌しています。
8月は広島長崎への原爆投下
そして終戦・敗戦がありました。
二度と戦争を起こして欲しくない、
おこしてはいけないという見地からも、
戦争についての長野県での様子も
学び調べたいと思う昨今です。
曹洞宗のお寺「宝蔵院」の隣にある公会堂。
ここで女子生徒50名が疎開生活をおくりました。

宝蔵院の境内にある「平和観音像」
インパール作戦に従事した地元の方が建立されました。

平和観音像の横にあ平和の鐘の下に位置する「不戦の伝言」
この伝言がいつまでも伝わるようにしたいものです。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
「信州のくだもののある生活」をごいっしょに!!
美味しい信州りんごを召し上がれ ・・・・信州の甘いりんご「つがる」 ご予約承り中。
瑞々しさをご堪能あれ・・・・・・・・・・・秋の信州梨、ご予約承り中。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

長野県は首都圏の小中学校の疎開先として、
多数の小中学生を受け入れました。
東京元浅草に生まれた永六輔さんも小諸に疎開し、
地元の学童からいじめられたという話は有名ですが、
父母と離れ、毎日異郷の地で過ごすということは
小学生にとってはさぞや辛かったことと思います。
先日、戦時中を知る近所のおじさんと疎開の話が出ましたが、
ここ長野市豊野町でも学童の疎開を受け入れたそうです。
当時、今の豊野町は、戦後合併する以前
西部地域を「神郷村」、東部地域が「鳥居村」に分かれていました。
多くの東京からの学童疎開は、志賀高原のふもとの山ノ内町の
湯田中温泉や渋温泉で受け入れたそうですが、
余りの温泉郷への集中疎開で、食糧問題等の弊害が出て、
再度、山ノ内町地区から、北信(長野県の北部、長野市以北の地域)に分散して、疎開がなされたそうです。
旧鳥居村では、豊島区の高田地区の約120名ほどが、
再疎開し、男子は、浅野地区のお寺 正見寺に
女子は、そのお寺のそばにある公会堂に疎開したそうです。
豊野町町誌など、文献を調べてみたのですが、
疎開のことは余り載っておらず、
詳しい生活の様子はわかりかねるのですが、
写真の公会堂で、約7ヶ月間という短い期間であたものの、
疎開生活がなされたようです。
その女子児童が疎開した中町公会堂は、
曹洞宗のお寺の宝蔵院の隣にあります。
宝蔵院には、ミャンマー(旧ビルマ)のインパール作戦に従軍して、
奇跡的に助かり帰還した方が中心となり、
二度とこのような戦争が起きぬ様にと、
平成の時代に「平和の鐘」が設置されたお寺です。
その宝蔵院の隣にこの「中町公会堂」が位置し、
都会生まれの女子生徒が親元を離れ、寝起きしたのです。
何とも頼りない建物での女子生徒50名ほどの
まだ親が恋しい子供達のとっての集団生活は、
さぞやきつかったことと思われます。
せめてもの救いは、当時、ここ豊野町東部の鳥居村地区では、
米も野菜も果物も首都圏と比べ流通していたはずで、
空腹に悩まされたということは無かったのではないかと推察します。
戦争中当時の様子を伺うことが出来る方々が、
かなり高齢となってきました。
高齢の方々が積極的に戦争について
語ることは少なくなってきており
我々現役世代が少しでも多くの方と出会いお話を伺って、
後世にこのようなことが二度と起きないように
戦争の悲惨さをリレーしていく時代となりました。
長野県は、蚕を中心とする生糸産業(工業・農業ともに)が
日本で一番盛んで製糸・養蚕産業への偏重の余り、
生糸の価格の暴落による手痛い打撃のため、
市街地も農村もおおいに疲弊しました。
それが一つの要因となり、
結果的に多くの満洲への移民を、
「長野県の政策」として出さざるを得なくなり、
満洲移民が全国で一番多かった県です。
そして結果的に満洲への移民は
戦後に多くの悲劇を生みました。
戦争を実際に経験していない世代が、大半となり、
僕たちは、「当たり前のように」豊かな時代を謳歌しています。
8月は広島長崎への原爆投下
そして終戦・敗戦がありました。
二度と戦争を起こして欲しくない、
おこしてはいけないという見地からも、
戦争についての長野県での様子も
学び調べたいと思う昨今です。
曹洞宗のお寺「宝蔵院」の隣にある公会堂。
ここで女子生徒50名が疎開生活をおくりました。
宝蔵院の境内にある「平和観音像」
インパール作戦に従事した地元の方が建立されました。

平和観音像の横にあ平和の鐘の下に位置する「不戦の伝言」
この伝言がいつまでも伝わるようにしたいものです。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
「信州のくだもののある生活」をごいっしょに!!
美味しい信州りんごを召し上がれ ・・・・信州の甘いりんご「つがる」 ご予約承り中。
瑞々しさをご堪能あれ・・・・・・・・・・・秋の信州梨、ご予約承り中。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
2013年09月17日
台風一過
農家が最も恐れている台風が
長野県下では飯田地方を通過し
日本各地で甚大な被害を引き起こし
列島を縦断していきました。
9月もいよいよ後半、
稲刈りも始まり、
黄金の実りを収穫し
各地で秋の収穫を神に感謝する
収穫祭なども行なわれる季節です。
そんな頃に、
1年間膨大な労力と時間をかけて
育てた農作物を一瞬にして
強力な風や大量の雨で
「無」にしてしまう台風、
自然災害の恐ろしさを
あらためて痛感いたします。
今回は降雨量が非常に多く
長野県北部では、
長野県に降った大量の雨のうち
半分を引き受ける千曲川が
かなり増水しました。
かつて高校生の頃
千曲川の堤防ギリギリに
そして中野市の立ヶ花橋を飲み込もうとするほどの
膨大な量が流れる千曲川を見て
「千曲川の洪水」の恐ろしさを経験しました。
江戸時代においては
まだ近代的な堤防が無かった時代
立ヶ花橋より上流で
千曲川に合流する篠井川が逆流し、
中野市の広大な延徳田んぼが
水で溢れたという近世以降最悪の「戌の満水」に
見られるように、
千曲川の洪水の恐怖は
ずっと伝わっています。
今回、増水した千曲川ですが
溢れるほどではないものの
一部河川敷の畑のうち
低地にある箇所では
冠水し、りんごや栗の樹が
水に浸かったようです。
被害に遭われた農家さんには
心よりお見舞申し上げます。
広大な長野県の
北半分を千曲川が
南半分を天竜川と木曽川が引きうけ
県下に降雨した雨を
それぞれ太平洋と日本海に流します。
千曲川の下流域の新潟県
天竜川下流域の静岡県
木曽川下流域の愛知県
それぞれの県にも増水し洪水となった場合
甚大な被害をもたらします。
当地では収穫祭は来週の3連休に行なわれます。
収穫に感謝すると同時に
各地で自然災害が起きないよう
風神雷神にも安寧であるように
祈りたいと思います。
浅川と千曲川が合流するあたり。
河川敷でも低い場所に当たり
一部栗の木などが冠水しました。

洪水にあう恐れがあるため
ここ数年、耕作放棄地が多く
農作物の被害はそれほどでもないと思われますが
被害に遭われた農家さんには
心よりお見舞申し上げます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
信州の秋の真っ赤な林檎「秋映」・・・・・・・2013年度ご予約承り中。発送は810月半ばより。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。

にほんブログ村
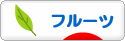
にほんブログ村
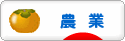
にほんブログ村


長野県下では飯田地方を通過し
日本各地で甚大な被害を引き起こし
列島を縦断していきました。
9月もいよいよ後半、
稲刈りも始まり、
黄金の実りを収穫し
各地で秋の収穫を神に感謝する
収穫祭なども行なわれる季節です。
そんな頃に、
1年間膨大な労力と時間をかけて
育てた農作物を一瞬にして
強力な風や大量の雨で
「無」にしてしまう台風、
自然災害の恐ろしさを
あらためて痛感いたします。
今回は降雨量が非常に多く
長野県北部では、
長野県に降った大量の雨のうち
半分を引き受ける千曲川が
かなり増水しました。
かつて高校生の頃
千曲川の堤防ギリギリに
そして中野市の立ヶ花橋を飲み込もうとするほどの
膨大な量が流れる千曲川を見て
「千曲川の洪水」の恐ろしさを経験しました。
江戸時代においては
まだ近代的な堤防が無かった時代
立ヶ花橋より上流で
千曲川に合流する篠井川が逆流し、
中野市の広大な延徳田んぼが
水で溢れたという近世以降最悪の「戌の満水」に
見られるように、
千曲川の洪水の恐怖は
ずっと伝わっています。
今回、増水した千曲川ですが
溢れるほどではないものの
一部河川敷の畑のうち
低地にある箇所では
冠水し、りんごや栗の樹が
水に浸かったようです。
被害に遭われた農家さんには
心よりお見舞申し上げます。
広大な長野県の
北半分を千曲川が
南半分を天竜川と木曽川が引きうけ
県下に降雨した雨を
それぞれ太平洋と日本海に流します。
千曲川の下流域の新潟県
天竜川下流域の静岡県
木曽川下流域の愛知県
それぞれの県にも増水し洪水となった場合
甚大な被害をもたらします。
当地では収穫祭は来週の3連休に行なわれます。
収穫に感謝すると同時に
各地で自然災害が起きないよう
風神雷神にも安寧であるように
祈りたいと思います。
浅川と千曲川が合流するあたり。
河川敷でも低い場所に当たり
一部栗の木などが冠水しました。
洪水にあう恐れがあるため
ここ数年、耕作放棄地が多く
農作物の被害はそれほどでもないと思われますが
被害に遭われた農家さんには
心よりお見舞申し上げます。
善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
信州の秋の真っ赤な林檎「秋映」・・・・・・・2013年度ご予約承り中。発送は810月半ばより。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村

2013年01月10日
3つの大日向村とは???
新聞によると群馬県の富岡製糸場が
世界遺産に申請されるそうである。
富岡製糸場は、日本史の教科書でも習ったように
追いつけ追い越せの明治時代の殖産工業の先導的模範事例としてとして
時代の先端を行くものであった。
信州からも松代藩から、上級藩士の娘横田英が富岡に赴き
機械化された製糸産業を「女工」として習得し
信州に戻った後は、教師役として、活躍をした。
日本の中でもどちらかと言うと「後発組」だった信州長野県の製糸産業は
そのたゆまぬ努力と勤勉さで、先発していたの福島・群馬を追い越し
原料生産・製品生産ともに日本一となっていく。
また、桑畑はかなりの「傾斜地」でも栽培が可能であり、
広大で平坦な農地が少なかった信州では
そんなことも桑栽培を盛んにさせた理由の一つである。
しかしながら、昭和の初期からの不況と
その後の世界恐慌、
及びストッキングに使用する繊維が
「絹」から、「ナイロン」に
変わることが、信州どころか
日本の国全体を、大きく変えることとなる。
こんな不況の煽りを一番受けたのが
蚕糸王国信州で、「絹」という繊維を作っっていた
岡谷や諏訪・須坂であり
原料の「繭」を生産していた
県下一円の農家で、いずれも一大打撃を蒙ることとなった。
信州の農家は歴史を紐解くと
大概が桑栽培・養蚕を生業としていて、
大打撃を蒙ったように
我が家も養蚕産業の一翼を担っていて、窮乏することとなる。
こうした県下各地の農村不況・疲弊を打開したのが
いわゆる「満州移民」である。
国として県として、長野県からの満州移民を
積極的に奨励し、農家次男坊を中心に旧満州に
開拓移民として送り込むこととなった。
「満蒙は、帝国の生命線」という言葉が
そのことを物語っている。
蚕を飼っても、金にならず
現在のように、リンゴや梨のようなくだもの生産もままならず
桑栽培が盛んだった信州の農村
及び製糸産業に大きな重きをなしていた長野県全体が疲弊していたのだ。
結局のところ
農村での「余剰な人員」を整理する意味もあり
また、次男・三男坊の働き先として信州は、全国で一番、満州への移民を
排出せざるをえなくなる。
満州への開拓移民と言っても
歴史の教科書で周知のように、
「王道楽土」とか「五族共和」と言うフレーズは
なかなかその通りには行かなかったようである。
そして何よりも悲惨であったことは
防衛してくれるはずがいち早く逃げた関東軍に代わり
ソ連の脅威からの防波堤として
壮青年の開拓移民が現地で召集され活躍せざるを得なくなり
残されたのは、老若男女となったことだ。
こうして、ソ連の侵攻により、着の身着のままで逃避行を開始
婦女子も最終的には、下高井郡の「高社郷」に見られるように
移民した村全体で自決という
悲劇もうんでしまった。
満州からの逃避行でに関してその様子は、
「国家の品格」を著した藤原正彦さんの
ご母堂の藤原ていさんの
「流れる星は生きている」などでも詳しい。
さて。こうした「満州への移民の悲劇」を
如実に物語っているのが
昨年春に長野県立歴史館で企画された
「三つの大日向村」展である。
3つの大日向村とは
同じ大日向村という村が、
3回も村自体が移動していることを指す。
昭和初期にあった「南佐久郡」の1つ目の大日向村は、
先ほど述べた昭和恐慌の煽りを受け
村の一部を「分村」として
満州に村民を送り出す。
満州に分村した2つ目の大日向村は
ソ連の侵攻とともに崩壊し
日本への引き揚げ・逃避行となる。
満州への分村を出した1つ目の「南佐久郡」の大日向村には
本国に帰ってきても既に、満州へ分村移民した2つ目の大日向村の人々を養う「余裕」が無く
やむを得ず、満州から引き上げた人々は
3つ目の大日向村を浅間山麓の軽井沢の原野に
まさに開拓をして、3つ目の大日向村を誕生させる。
このような3つもの村を
作らざるを得なかった状況と環境、
今でこそ信州は
果樹栽培が盛んであるが
こうした大きな悲劇・苦労を経て
今日があることを忘れてはならない。
どうして、場所を変えて
3つもの「大日向村」を作らなければならなかったのか?
先人たちが苦労して
今日の長野県農業の礎を作り上げた。
同じ農業をするものとして
こうした「事実」を忘れてはいけないと思っている。
2012年春の長野県立歴史館の企画展のリーフレット

古今東西を問わず戦争で一番犠牲を蒙るのは
子供であり、弱者である。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。

にほんブログ村
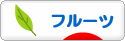
にほんブログ村
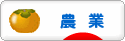
にほんブログ村


世界遺産に申請されるそうである。
富岡製糸場は、日本史の教科書でも習ったように
追いつけ追い越せの明治時代の殖産工業の先導的模範事例としてとして
時代の先端を行くものであった。
信州からも松代藩から、上級藩士の娘横田英が富岡に赴き
機械化された製糸産業を「女工」として習得し
信州に戻った後は、教師役として、活躍をした。
日本の中でもどちらかと言うと「後発組」だった信州長野県の製糸産業は
そのたゆまぬ努力と勤勉さで、先発していたの福島・群馬を追い越し
原料生産・製品生産ともに日本一となっていく。
また、桑畑はかなりの「傾斜地」でも栽培が可能であり、
広大で平坦な農地が少なかった信州では
そんなことも桑栽培を盛んにさせた理由の一つである。
しかしながら、昭和の初期からの不況と
その後の世界恐慌、
及びストッキングに使用する繊維が
「絹」から、「ナイロン」に
変わることが、信州どころか
日本の国全体を、大きく変えることとなる。
こんな不況の煽りを一番受けたのが
蚕糸王国信州で、「絹」という繊維を作っっていた
岡谷や諏訪・須坂であり
原料の「繭」を生産していた
県下一円の農家で、いずれも一大打撃を蒙ることとなった。
信州の農家は歴史を紐解くと
大概が桑栽培・養蚕を生業としていて、
大打撃を蒙ったように
我が家も養蚕産業の一翼を担っていて、窮乏することとなる。
こうした県下各地の農村不況・疲弊を打開したのが
いわゆる「満州移民」である。
国として県として、長野県からの満州移民を
積極的に奨励し、農家次男坊を中心に旧満州に
開拓移民として送り込むこととなった。
「満蒙は、帝国の生命線」という言葉が
そのことを物語っている。
蚕を飼っても、金にならず
現在のように、リンゴや梨のようなくだもの生産もままならず
桑栽培が盛んだった信州の農村
及び製糸産業に大きな重きをなしていた長野県全体が疲弊していたのだ。
結局のところ
農村での「余剰な人員」を整理する意味もあり
また、次男・三男坊の働き先として信州は、全国で一番、満州への移民を
排出せざるをえなくなる。
満州への開拓移民と言っても
歴史の教科書で周知のように、
「王道楽土」とか「五族共和」と言うフレーズは
なかなかその通りには行かなかったようである。
そして何よりも悲惨であったことは
防衛してくれるはずがいち早く逃げた関東軍に代わり
ソ連の脅威からの防波堤として
壮青年の開拓移民が現地で召集され活躍せざるを得なくなり
残されたのは、老若男女となったことだ。
こうして、ソ連の侵攻により、着の身着のままで逃避行を開始
婦女子も最終的には、下高井郡の「高社郷」に見られるように
移民した村全体で自決という
悲劇もうんでしまった。
満州からの逃避行でに関してその様子は、
「国家の品格」を著した藤原正彦さんの
ご母堂の藤原ていさんの
「流れる星は生きている」などでも詳しい。
さて。こうした「満州への移民の悲劇」を
如実に物語っているのが
昨年春に長野県立歴史館で企画された
「三つの大日向村」展である。
3つの大日向村とは
同じ大日向村という村が、
3回も村自体が移動していることを指す。
昭和初期にあった「南佐久郡」の1つ目の大日向村は、
先ほど述べた昭和恐慌の煽りを受け
村の一部を「分村」として
満州に村民を送り出す。
満州に分村した2つ目の大日向村は
ソ連の侵攻とともに崩壊し
日本への引き揚げ・逃避行となる。
満州への分村を出した1つ目の「南佐久郡」の大日向村には
本国に帰ってきても既に、満州へ分村移民した2つ目の大日向村の人々を養う「余裕」が無く
やむを得ず、満州から引き上げた人々は
3つ目の大日向村を浅間山麓の軽井沢の原野に
まさに開拓をして、3つ目の大日向村を誕生させる。
このような3つもの村を
作らざるを得なかった状況と環境、
今でこそ信州は
果樹栽培が盛んであるが
こうした大きな悲劇・苦労を経て
今日があることを忘れてはならない。
どうして、場所を変えて
3つもの「大日向村」を作らなければならなかったのか?
先人たちが苦労して
今日の長野県農業の礎を作り上げた。
同じ農業をするものとして
こうした「事実」を忘れてはいけないと思っている。
2012年春の長野県立歴史館の企画展のリーフレット
古今東西を問わず戦争で一番犠牲を蒙るのは
子供であり、弱者である。
善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村

2012年04月16日
「油沢」・・・・・・地名が語る歴史
「地名」ほど面白いものは無いと思っている。
例えば、豊野町の旧神代宿(かじろじゅく)があった立町の
観音様の裏は「油沢」と呼ばれている。
「ゆざわ」は
通常「湯沢」が多く(越後湯沢など)、
「湯」が豊富に出るとか
温泉など「湯」に関係した場所が多い。
では、豊野町の観音様裏の「油沢」はどうかというと
中学校のときの担任でもあった豊野町出身の理科の先生によると
「油」=「石油」が湧いていたそうだ。
「湧く」と言っても
恐らく「たゆみなく」湧き出るのではなく
「にじみ出る」とか
水の中に油が「浮く」程度であったかと
思うのであるが、その辺はまだよく聞いていない。
しかし、懇意にしていただいている「うさぎちゃん」こと
長野市北郷の松木武久農園に行く際には
浅川のループ橋をわたっていくのであるが
そのループ橋の途中に浅川真光寺地区があり
こちらの真光寺では、かなり石油が出たそうである。
「長野市誌」だったと思うのであるが
真光寺地区の水田には、「くそうず}(臭い水=石油)が
湧き出て、灯火に煮炊きに
多いに利用されたと読んだことがある。
なお、そのあたりのことは
小布施町の「日本の明かり博物館」の
館長であった故金箱正美さんと
同学芸員であった故山崎ます美さんの著書に詳しく
大変興味深く面白く、読むことが可能である。
さて、豊野町の「油沢」にもどるが
明治の初頭には
石坂周造という幕末には新撰組にも関わった志士が
一転して長野の真光寺の地や
この豊野町の油沢などにも注目し、
石油の掘削事業を起こしている。
石坂の起こした「長野石油会社」は
結局放漫経営や近代的な機械掘りなど行なったにもかかわらず
「くそうず」(臭い水)として
そこから算出される「油」は灯火などへの利用は、
可能であったようだが
「一攫千金」を夢見ての大規模な産出は叶わず
成功しなかったようである。
地名を探っていくと
様々な歴史に遭遇する。
歴史は江戸や京都だけで
華々しい武士や公家・貴族だけで作られたものではない。
地方で田舎で
農民や漁民が築き上げた実に興味深い歴史が
多数存在しているのである。
そういった、教科書に先ずは載らない歴史
そんな歴史を調べてみるのも実に興味深い。
豊野町立町の公会堂そばにある観音様

観音様の説明看板
「油沢山 正行寺」と書いてある。
この裏が「油沢」地区。

小布施町「日本の明かり博物館」
元スタッフ金箱正美さん山崎ます美さんの著書
博物館のほか、
長野市大門町 西澤書店でも販売されている。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
2012年5月13日「母の日」ギフト好適品・・・・・信州のりんごジュース&ジャムの詰め合わせ
たくさん食べたい信州のりんご ・・・・・「完熟サンふじ」家庭用コース販売中!!
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。

にほんブログ村
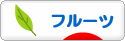
にほんブログ村
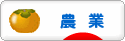
にほんブログ村


例えば、豊野町の旧神代宿(かじろじゅく)があった立町の
観音様の裏は「油沢」と呼ばれている。
「ゆざわ」は
通常「湯沢」が多く(越後湯沢など)、
「湯」が豊富に出るとか
温泉など「湯」に関係した場所が多い。
では、豊野町の観音様裏の「油沢」はどうかというと
中学校のときの担任でもあった豊野町出身の理科の先生によると
「油」=「石油」が湧いていたそうだ。
「湧く」と言っても
恐らく「たゆみなく」湧き出るのではなく
「にじみ出る」とか
水の中に油が「浮く」程度であったかと
思うのであるが、その辺はまだよく聞いていない。
しかし、懇意にしていただいている「うさぎちゃん」こと
長野市北郷の松木武久農園に行く際には
浅川のループ橋をわたっていくのであるが
そのループ橋の途中に浅川真光寺地区があり
こちらの真光寺では、かなり石油が出たそうである。
「長野市誌」だったと思うのであるが
真光寺地区の水田には、「くそうず}(臭い水=石油)が
湧き出て、灯火に煮炊きに
多いに利用されたと読んだことがある。
なお、そのあたりのことは
小布施町の「日本の明かり博物館」の
館長であった故金箱正美さんと
同学芸員であった故山崎ます美さんの著書に詳しく
大変興味深く面白く、読むことが可能である。
さて、豊野町の「油沢」にもどるが
明治の初頭には
石坂周造という幕末には新撰組にも関わった志士が
一転して長野の真光寺の地や
この豊野町の油沢などにも注目し、
石油の掘削事業を起こしている。
石坂の起こした「長野石油会社」は
結局放漫経営や近代的な機械掘りなど行なったにもかかわらず
「くそうず」(臭い水)として
そこから算出される「油」は灯火などへの利用は、
可能であったようだが
「一攫千金」を夢見ての大規模な産出は叶わず
成功しなかったようである。
地名を探っていくと
様々な歴史に遭遇する。
歴史は江戸や京都だけで
華々しい武士や公家・貴族だけで作られたものではない。
地方で田舎で
農民や漁民が築き上げた実に興味深い歴史が
多数存在しているのである。
そういった、教科書に先ずは載らない歴史
そんな歴史を調べてみるのも実に興味深い。
豊野町立町の公会堂そばにある観音様
観音様の説明看板
「油沢山 正行寺」と書いてある。
この裏が「油沢」地区。
小布施町「日本の明かり博物館」
元スタッフ金箱正美さん山崎ます美さんの著書
博物館のほか、
長野市大門町 西澤書店でも販売されている。
善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
2012年5月13日「母の日」ギフト好適品・・・・・信州のりんごジュース&ジャムの詰め合わせ
たくさん食べたい信州のりんご ・・・・・「完熟サンふじ」家庭用コース販売中!!
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村

2012年02月26日
「足元を見る。」とは
「足元を見る」と言う言葉がある。
今の時期は、
ロングブーツや滑走防止のための運動靴
スノウシューズ、長靴・・・・と様々。
しかしながら、顔や服装は良く見ていても
足元をジッと見ることは先ず無い。
山手線や総武線のような窓伝いに
横長に座席シートが置いてあっても
なかなか足元なぞ見ないものである。
しかしながら、遠い昔
街道筋や宿場などで、
駕籠屋や馬方などが、旅人の「足取り」を見て、
その疲れ具合によって、値段を要求をしていた頃
ジッと足元は注目されていたはずである。
そんな事から、
多少法外な値段を要求しても、
疲れていれば喜んで受け入れてしまうことも
「足元を見る」という「言葉」となった。
故人であるが
橋本龍太郎元総理は、
毎日自分で自分の靴を磨いている、
と大学時代の政治家になった先輩から
聞いたことがある。
橋本元総理、通称「橋龍」は
ポマードでビシッと決め込んだ
お洒落な政治家であった。
橋龍は、毎日靴の手入れをして
足元には気を遣っていたはずである。
しかしながら、橋龍の消費税の導入時期の過誤は
経済成長率の落ち込みを招き、拓銀の破綻や
証券会社がバタバタと潰れることの遠因ともなった。
結局自分の足元には十分に注意を払っていたにもかかわらず
ちょっとひどい言い方をすれば
大蔵省に「足元を見られ」、導入時期の判断を誤り
消費税のアップに突き進み
退陣はおろか、日本にとってもその後散々な目に遭うことになる。
これまた昔の話であるが
小布施橋を渡った「神農社」という小さな社の境内に
「脛石」という大きな平たい石がある。
越後から出稼ぎにやってきた農民たちに
脛石の上に「足」を出させ
その「足の状況」によって
何の仕事に配属させるか判断したという
言い伝えが残っている。
「足元を見る。」
なかなか注意が行き届かないのであるが
見ている人は見ている。
十分に注意を払った方が良さそうである。
昨日は飲みすぎてしまい
千鳥足とまで行かないが
「足元」がおぼつかなかった。

小布施橋を豊野方面から渡り直ぐに左折
神農社があり、そこに「脛石」はある。

脛石由来の看板

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
たくさん食べたい信州のりんご ・・・・・「完熟サンふじ」家庭用コース販売中!!
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。

にほんブログ村
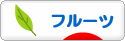
にほんブログ村
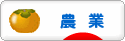
にほんブログ村


今の時期は、
ロングブーツや滑走防止のための運動靴
スノウシューズ、長靴・・・・と様々。
しかしながら、顔や服装は良く見ていても
足元をジッと見ることは先ず無い。
山手線や総武線のような窓伝いに
横長に座席シートが置いてあっても
なかなか足元なぞ見ないものである。
しかしながら、遠い昔
街道筋や宿場などで、
駕籠屋や馬方などが、旅人の「足取り」を見て、
その疲れ具合によって、値段を要求をしていた頃
ジッと足元は注目されていたはずである。
そんな事から、
多少法外な値段を要求しても、
疲れていれば喜んで受け入れてしまうことも
「足元を見る」という「言葉」となった。
故人であるが
橋本龍太郎元総理は、
毎日自分で自分の靴を磨いている、
と大学時代の政治家になった先輩から
聞いたことがある。
橋本元総理、通称「橋龍」は
ポマードでビシッと決め込んだ
お洒落な政治家であった。
橋龍は、毎日靴の手入れをして
足元には気を遣っていたはずである。
しかしながら、橋龍の消費税の導入時期の過誤は
経済成長率の落ち込みを招き、拓銀の破綻や
証券会社がバタバタと潰れることの遠因ともなった。
結局自分の足元には十分に注意を払っていたにもかかわらず
ちょっとひどい言い方をすれば
大蔵省に「足元を見られ」、導入時期の判断を誤り
消費税のアップに突き進み
退陣はおろか、日本にとってもその後散々な目に遭うことになる。
これまた昔の話であるが
小布施橋を渡った「神農社」という小さな社の境内に
「脛石」という大きな平たい石がある。
越後から出稼ぎにやってきた農民たちに
脛石の上に「足」を出させ
その「足の状況」によって
何の仕事に配属させるか判断したという
言い伝えが残っている。
「足元を見る。」
なかなか注意が行き届かないのであるが
見ている人は見ている。
十分に注意を払った方が良さそうである。
昨日は飲みすぎてしまい
千鳥足とまで行かないが
「足元」がおぼつかなかった。
小布施橋を豊野方面から渡り直ぐに左折
神農社があり、そこに「脛石」はある。

脛石由来の看板

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
たくさん食べたい信州のりんご ・・・・・「完熟サンふじ」家庭用コース販売中!!
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村

2011年09月10日
「かかし」・・・・これで納得
収獲の秋 稲刈りまで
もうあとわずかである。
今年は、猛暑であったものの
昨年のような9月に入っての連日の猛暑も
今のところ感じられない。
熱帯作物ではあるものの
「猛暑・酷暑」には弱い稲にとっては
今年は、幾分か過ごし易かったのではなかろうか。
そんな稲刈りを待つ田んぼで
スズメから米を守ってくれているのが
案山子やスズメ除けである。
スズメ対策の「スズメ除け」は、
最近では反射テープを田んぼ周囲に掲げ
スズメの接近を防止するか
田んぼ全体を「網」で覆い、
スズメが米にありつけないように
するものが多い。
その際に一緒に「案山子」が
置かれている場合が多い。
その「案山子(かかし)」
人形のようなものを「案山子」と呼ぶと
ずっと思っていたのだ。
しかしながら、
最近岩波の「言葉の道草」を読んでいたら
どうも「かかし」は
獣肉などを焼いて串に刺し
その「ニオイ」を「かがせて」
鳥獣を退散させて事から
「かがし」→「かかし」と
なったようで
「串刺しの獣肉」を事を
本来「かかし」と呼んだようである。
「かかし」はおなじみの「人形」が案山子だとばかり
思っていたのだが、
「ニオイをかがせる串刺し」が
本来の「かかし」とは
全くの青天の霹靂であった。
そう考えると
以前から今の時期
田んぼにジャガイモやきゅうりを
いぼ竹に串刺し
田んぼ周囲に掲げている
農家があり、
「なぜジャガイモの串刺しなど掲げるのか???」と
ここ数年来不思議に思っていたのだが
この「かがせ」の原理で
やっと納得が出来たのである。
さすがに、
獣肉を串刺しにして
ニオイを出す風景には出くわさなかったが
「ジャガイモの串刺し」は
チラホラ見かけたので
これで合点がいった次第である。
きゅうりやジャガイモを
串に刺し、腐らせて
「ニオイ」を発生させ、鳥類たちに忌避させる。
しかし・・・・・
スズメに「かがし」した場合
「ニオイ」は判別できるのであろうか???
「スズメ」がニオイが分かるのだろうか???
とまた疑問がわいてしまったのである。
ハエや犬のように
ニオイで寄ってくるものもいるが
スズメなど鳥類が「ニオイ」を
判別して「忌避」するのであろうか???
やっとここ数年来の「ジャガイモの串刺し」が
案山子の一種ということで
一つ疑問が解決したのだが
また鳥類にニオイが分かるのかという
疑問が生じてしまった。
「鳥にニオイが分かるのか???」
また調べてみようと思っている。
ジャガイモの串刺し
何かのおまじないかと思っていました。

これが本来の「かがし」→「かかし」なのでしょう。

こちらはきゅうり

人形の「かかし」

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
瑞々しさをご堪能あれ!! ・・・・・・・・・「信州善光寺平の梨シリーズ」ご予約開始
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村


もうあとわずかである。
今年は、猛暑であったものの
昨年のような9月に入っての連日の猛暑も
今のところ感じられない。
熱帯作物ではあるものの
「猛暑・酷暑」には弱い稲にとっては
今年は、幾分か過ごし易かったのではなかろうか。
そんな稲刈りを待つ田んぼで
スズメから米を守ってくれているのが
案山子やスズメ除けである。
スズメ対策の「スズメ除け」は、
最近では反射テープを田んぼ周囲に掲げ
スズメの接近を防止するか
田んぼ全体を「網」で覆い、
スズメが米にありつけないように
するものが多い。
その際に一緒に「案山子」が
置かれている場合が多い。
その「案山子(かかし)」
人形のようなものを「案山子」と呼ぶと
ずっと思っていたのだ。
しかしながら、
最近岩波の「言葉の道草」を読んでいたら
どうも「かかし」は
獣肉などを焼いて串に刺し
その「ニオイ」を「かがせて」
鳥獣を退散させて事から
「かがし」→「かかし」と
なったようで
「串刺しの獣肉」を事を
本来「かかし」と呼んだようである。
「かかし」はおなじみの「人形」が案山子だとばかり
思っていたのだが、
「ニオイをかがせる串刺し」が
本来の「かかし」とは
全くの青天の霹靂であった。
そう考えると
以前から今の時期
田んぼにジャガイモやきゅうりを
いぼ竹に串刺し
田んぼ周囲に掲げている
農家があり、
「なぜジャガイモの串刺しなど掲げるのか???」と
ここ数年来不思議に思っていたのだが
この「かがせ」の原理で
やっと納得が出来たのである。
さすがに、
獣肉を串刺しにして
ニオイを出す風景には出くわさなかったが
「ジャガイモの串刺し」は
チラホラ見かけたので
これで合点がいった次第である。
きゅうりやジャガイモを
串に刺し、腐らせて
「ニオイ」を発生させ、鳥類たちに忌避させる。
しかし・・・・・
スズメに「かがし」した場合
「ニオイ」は判別できるのであろうか???
「スズメ」がニオイが分かるのだろうか???
とまた疑問がわいてしまったのである。
ハエや犬のように
ニオイで寄ってくるものもいるが
スズメなど鳥類が「ニオイ」を
判別して「忌避」するのであろうか???
やっとここ数年来の「ジャガイモの串刺し」が
案山子の一種ということで
一つ疑問が解決したのだが
また鳥類にニオイが分かるのかという
疑問が生じてしまった。
「鳥にニオイが分かるのか???」
また調べてみようと思っている。
ジャガイモの串刺し
何かのおまじないかと思っていました。
これが本来の「かがし」→「かかし」なのでしょう。
こちらはきゅうり
人形の「かかし」
善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
瑞々しさをご堪能あれ!! ・・・・・・・・・「信州善光寺平の梨シリーズ」ご予約開始
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村

タグ :かかし
2011年07月08日
杏から思ったこと・・・・・・長野県の名前
長野県ほど呼び方がいくつもある県は
無いと思っている。
長野県はもちろん「信州」 「信濃」 「信山」・・・
遡ってみると、
明治のの廃藩置県のとき
現在の東北信は、「中野県」であり、
中南信は、「筑摩県」であった。
当初、須坂をはじめ飯山も飯田・諏訪も江戸時代の各藩は
それぞれ須坂県・飯田県になったのだが、
北信地域をなぜ中野が代表したかかというと
中野は、恐らく北信で唯一の天領で、
陣屋があったせいであろう。
郷土史家の故小林計一郎さんの書物によると
長野県の長野は、現在の長野市妻科地域辺りの
「長野村」の呼称であり
当時は、江戸の頃から、門前町として栄えた「善光寺町」の方が
よっぽど大きかったようであり
いわゆる長野村は一寒村の呼び名だったと言っても
差し支えあるまい。
それが、いつの間にか
善光寺町を抜いて現在の長野地域を指す呼び名となり
いつの間にか、南北に広い巨大な県の呼び名にまでなってしまった。
当初、維新の頃の「中野県」は
東北信を指す呼称として、認知されたものの
中野県自体が、善光寺を有する長野村の方が
繁栄しており県庁の所在地としてふさわしいとして
その地位を譲ってしまった経緯がある。
こうして中野県から禅譲されて誕生した
東北信を指す長野県である。
その後、東北信を指す長野県と、中南信を指す筑摩県も
合併したものの、その県庁所在地を巡って
多いに争われていて、
その争いは、現在の長野県庁が建立される
昭和40年代前半まで続いたのである。
なぜ、信濃県とか、信州県としなかったのか。
江戸の頃は、信州・信濃という呼び方は
全国区であり、長野村を表す「長野」より
よっぽど有名であったはずなのに。
さて、なぜ今日こんなことを書いたかと言うと
杏の季節、
杏の品種名に長野県を指す呼び方が実に多いからだ。
「信州サワー」 「信山丸」 「信陽」・・・・
「信山」も「信陽」も長野県を指す古い呼称である。
こう杏に「長野県」を指す呼び方が付くと
次の品種は、「長野○○」か「筑摩○○」か
「信濃○○」か・・・・??
などと勘繰ってしまうのである。
ここでもしかしたら
中野県の逆襲で、「中野○○」と
中野が再登場するかもしれない・・・・・。
実にくだらない話であるが
美味しい杏の季節、
ついつい杏に実に信州の名前が冠されていて
ふと考えてしまた次第である。
ただいま真っ只中
生食でも加工しても美味しい信州の杏

ジャムにすると
杏特有の酸っぱさがたまりません。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
善光寺平の旬の桃を3回にわたって産直・・・・・・・・・「善光寺平の桃紀行」 ご予約開始
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村


無いと思っている。
長野県はもちろん「信州」 「信濃」 「信山」・・・
遡ってみると、
明治のの廃藩置県のとき
現在の東北信は、「中野県」であり、
中南信は、「筑摩県」であった。
当初、須坂をはじめ飯山も飯田・諏訪も江戸時代の各藩は
それぞれ須坂県・飯田県になったのだが、
北信地域をなぜ中野が代表したかかというと
中野は、恐らく北信で唯一の天領で、
陣屋があったせいであろう。
郷土史家の故小林計一郎さんの書物によると
長野県の長野は、現在の長野市妻科地域辺りの
「長野村」の呼称であり
当時は、江戸の頃から、門前町として栄えた「善光寺町」の方が
よっぽど大きかったようであり
いわゆる長野村は一寒村の呼び名だったと言っても
差し支えあるまい。
それが、いつの間にか
善光寺町を抜いて現在の長野地域を指す呼び名となり
いつの間にか、南北に広い巨大な県の呼び名にまでなってしまった。
当初、維新の頃の「中野県」は
東北信を指す呼称として、認知されたものの
中野県自体が、善光寺を有する長野村の方が
繁栄しており県庁の所在地としてふさわしいとして
その地位を譲ってしまった経緯がある。
こうして中野県から禅譲されて誕生した
東北信を指す長野県である。
その後、東北信を指す長野県と、中南信を指す筑摩県も
合併したものの、その県庁所在地を巡って
多いに争われていて、
その争いは、現在の長野県庁が建立される
昭和40年代前半まで続いたのである。
なぜ、信濃県とか、信州県としなかったのか。
江戸の頃は、信州・信濃という呼び方は
全国区であり、長野村を表す「長野」より
よっぽど有名であったはずなのに。
さて、なぜ今日こんなことを書いたかと言うと
杏の季節、
杏の品種名に長野県を指す呼び方が実に多いからだ。
「信州サワー」 「信山丸」 「信陽」・・・・
「信山」も「信陽」も長野県を指す古い呼称である。
こう杏に「長野県」を指す呼び方が付くと
次の品種は、「長野○○」か「筑摩○○」か
「信濃○○」か・・・・??
などと勘繰ってしまうのである。
ここでもしかしたら
中野県の逆襲で、「中野○○」と
中野が再登場するかもしれない・・・・・。
実にくだらない話であるが
美味しい杏の季節、
ついつい杏に実に信州の名前が冠されていて
ふと考えてしまた次第である。
ただいま真っ只中
生食でも加工しても美味しい信州の杏
ジャムにすると
杏特有の酸っぱさがたまりません。
善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
善光寺平の旬の桃を3回にわたって産直・・・・・・・・・「善光寺平の桃紀行」 ご予約開始
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村

2010年09月08日
秋の感謝と平穏無事を願う祭りに向けて
日本の各地で夏祭りが行なわれましたが、
ここ豊野町浅野地区では秋祭り(浅野神社秋の例大祭)が
9月24日に行なわれます。
浅野地区には、6つの集落があり、
伊勢社や諏訪社(伊勢神宮を本家とする神社信仰と長野県諏訪市の諏訪大社を本家とする神社信仰。近世の北信濃の神社信仰については、後日またご案内します。)など、それぞれ異なる神様を各集落ごとに信仰していました。
これが、明治の廃仏毀釈に伴い、
「浅野神社」として統一され今日に至っています。
秋の例大祭には、
五穀豊穣の願いと感謝の気持ちを込めて行われます。
以前にも書きましたが、善光寺平は、千曲川沿岸の肥沃の地ですが、「洪水」に常に悩まされ続け、戦ってきた歴史の側面もあります。
ですから、この例大祭では、
台風が洪水など多大な被害をもたらさないように
「水神様」の意味合いも含まれます。
こうした様々な「祈り」と「感謝」を年に1度祭りとして行ないます。
当日は、小学生を中心とする「お神輿」が出て、
浅野地区の全ての家にて、「神輿」が舞い、
各家庭の平穏無事を祈ります。
大人たちは、浅野地区の祭礼の保存会メンバーにより
「山車」を出し、事前に請われた家庭で「悪魔払い」という儀式を執り行い、獅子が舞いその家の災難を除難します。
こうした、9月24日に向けた浅野神社のお祭りの準備が、
夜になると、行われるようになりました。
子供たちが太鼓や笛などの吹き方を
浅野地区の祭礼の保存会メンバーの方々に教わるため、
毎日、公民館に集合して練習をしています。
僕も小学生の頃に、もちろん習いました。
その頃に、毎日太鼓や笛を習ったせいか、
今、練習で聞こえてくる太鼓の音や笛の音には、
長い間この地から離れてはいたものの、
体に染み込んでしまったのでしょうか、リズムを思い出します。
この夜中の練習で、「笛の音」や「太鼓の響き」が流れてくると、
本格的な秋です。
日中は、まだ厳しい暑さではあるものの、
朝晩すっかり涼しくなりました。
秋の味覚、梨「幸水」も収穫の最盛期を迎えました。
9月末に収穫予定の「シナノドルチェ」も
ピンク色に色づき始めました。
一方夏野菜とはそろそろお別れです。
キレイに咲いた「オクラの花」も見られるのはあとわずかです。
台風が接近していて、ヤキモキさせますが
何とか、被害が各地に及ばずに済むことを祈りたいと思います。
ハイビスカスのようなオクラの花。
夏もそろそろいいかなって感じの暑さが
まだ続きますが、朝晩は随分と気温が下がるようになりました。

こちらは茄子の花。
ナスは、まだまだ10月辺りまで収穫が可能です。

毎日幸水梨の収穫が行われています。
ただいま、捥ぎたての新鮮な幸水梨を
全国に産直しています。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
「信州のくだもののある生活」をごいっしょに!!
美味しい信州りんごを召し上がれ ・・・・信州の甘いりんご「つがる」 ご予約受け付け開始いたしました。
瑞々しさをご堪能あれ・・・・・・・・・・・秋の信州梨、ご予約開始いたしました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村


ここ豊野町浅野地区では秋祭り(浅野神社秋の例大祭)が
9月24日に行なわれます。
浅野地区には、6つの集落があり、
伊勢社や諏訪社(伊勢神宮を本家とする神社信仰と長野県諏訪市の諏訪大社を本家とする神社信仰。近世の北信濃の神社信仰については、後日またご案内します。)など、それぞれ異なる神様を各集落ごとに信仰していました。
これが、明治の廃仏毀釈に伴い、
「浅野神社」として統一され今日に至っています。
秋の例大祭には、
五穀豊穣の願いと感謝の気持ちを込めて行われます。
以前にも書きましたが、善光寺平は、千曲川沿岸の肥沃の地ですが、「洪水」に常に悩まされ続け、戦ってきた歴史の側面もあります。
ですから、この例大祭では、
台風が洪水など多大な被害をもたらさないように
「水神様」の意味合いも含まれます。
こうした様々な「祈り」と「感謝」を年に1度祭りとして行ないます。
当日は、小学生を中心とする「お神輿」が出て、
浅野地区の全ての家にて、「神輿」が舞い、
各家庭の平穏無事を祈ります。
大人たちは、浅野地区の祭礼の保存会メンバーにより
「山車」を出し、事前に請われた家庭で「悪魔払い」という儀式を執り行い、獅子が舞いその家の災難を除難します。
こうした、9月24日に向けた浅野神社のお祭りの準備が、
夜になると、行われるようになりました。
子供たちが太鼓や笛などの吹き方を
浅野地区の祭礼の保存会メンバーの方々に教わるため、
毎日、公民館に集合して練習をしています。
僕も小学生の頃に、もちろん習いました。
その頃に、毎日太鼓や笛を習ったせいか、
今、練習で聞こえてくる太鼓の音や笛の音には、
長い間この地から離れてはいたものの、
体に染み込んでしまったのでしょうか、リズムを思い出します。
この夜中の練習で、「笛の音」や「太鼓の響き」が流れてくると、
本格的な秋です。
日中は、まだ厳しい暑さではあるものの、
朝晩すっかり涼しくなりました。
秋の味覚、梨「幸水」も収穫の最盛期を迎えました。
9月末に収穫予定の「シナノドルチェ」も
ピンク色に色づき始めました。
一方夏野菜とはそろそろお別れです。
キレイに咲いた「オクラの花」も見られるのはあとわずかです。
台風が接近していて、ヤキモキさせますが
何とか、被害が各地に及ばずに済むことを祈りたいと思います。
ハイビスカスのようなオクラの花。
夏もそろそろいいかなって感じの暑さが
まだ続きますが、朝晩は随分と気温が下がるようになりました。
こちらは茄子の花。
ナスは、まだまだ10月辺りまで収穫が可能です。
毎日幸水梨の収穫が行われています。
ただいま、捥ぎたての新鮮な幸水梨を
全国に産直しています。
善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
「信州のくだもののある生活」をごいっしょに!!
美味しい信州りんごを召し上がれ ・・・・信州の甘いりんご「つがる」 ご予約受け付け開始いたしました。
瑞々しさをご堪能あれ・・・・・・・・・・・秋の信州梨、ご予約開始いたしました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村

2010年03月22日
北信濃の昔を偲ぶ・・・・手子塚城跡
中世、鎌倉後期から
幕府の「タガ」が緩んでくるせいか
各地各地の「領主」が力をつけ
台頭してくる。
領主たちは、
勢力拡大をもくろみ
互いに戦争を繰り返していくのであるが
そんな頃に、建てられたのであろうか
豊野町域にそんな抗争の拠点となった
城がいくつかある。
国道18号線を上越方面に向かい
浅野地区で中野方面に右折し
千曲川に架かる「立ヶ花橋」を渡る前に
木々が茂る小さな森がある。
そこが「手子塚城(てごづかじょう)」である。
現在、手子塚城は、手子塚神社として
諏訪社となり、手子塚地域の
産土神社として祀られているが、
その昔は、千曲川渕にあったため
越後方面・中野方面からの
敵からの防衛の拠点として
大いに利用されたはずである。
その後、
越後の上杉謙信と甲斐の武田信玄が
信濃の地を巡り、抗争と繰り返すのであるが
千曲川沿いにあり、中野方面を望める
この「手子塚城」は、見張りの拠点となって
歴史を見つめてきた。
現在、「城」の面影は全く無いのであるが
りんご畑の中にこんもりと松が生い茂る
手子塚神社は、すぐにわかる存在である。
眼下に千曲川、遠方には高社山を中心に
高井地域が望める風景は
今も昔も変わるまい。
春休みも始まり
ちょっとした空き時間に
地域の史跡を巡り、
古人の足跡をたどるのもまた楽しいものである。
手子塚城があった地に建つ手子塚神社

史跡の看板が立ち、その昔を窺うことが出来る。

鉄塔の陰で見えにくいのであるが
手子塚城の下は「崖」になっていて
がけ下には、千曲川が流れる。

松が生い茂り
国道18号線を中野方面に右折し
セブンイレブンを過ぎると
すぐ右手に手子塚城跡は見える。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州からのちょっとした贈り物・・・・坂爪農園の田舎のりんごジャム&田舎のりんごジュース
たくさん食べたい信州のリンゴ・・・ ・・・レッドバザール 恒例のマークダウンでご好評販売中
しぼりたての美味しさをお届け・・・・・・・信州北信濃 坂爪農園のりんごジュース
りんごが「ゴロッ」と入った素朴な味わい・・田舎のりんごジャム 販売中。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村


幕府の「タガ」が緩んでくるせいか
各地各地の「領主」が力をつけ
台頭してくる。
領主たちは、
勢力拡大をもくろみ
互いに戦争を繰り返していくのであるが
そんな頃に、建てられたのであろうか
豊野町域にそんな抗争の拠点となった
城がいくつかある。
国道18号線を上越方面に向かい
浅野地区で中野方面に右折し
千曲川に架かる「立ヶ花橋」を渡る前に
木々が茂る小さな森がある。
そこが「手子塚城(てごづかじょう)」である。
現在、手子塚城は、手子塚神社として
諏訪社となり、手子塚地域の
産土神社として祀られているが、
その昔は、千曲川渕にあったため
越後方面・中野方面からの
敵からの防衛の拠点として
大いに利用されたはずである。
その後、
越後の上杉謙信と甲斐の武田信玄が
信濃の地を巡り、抗争と繰り返すのであるが
千曲川沿いにあり、中野方面を望める
この「手子塚城」は、見張りの拠点となって
歴史を見つめてきた。
現在、「城」の面影は全く無いのであるが
りんご畑の中にこんもりと松が生い茂る
手子塚神社は、すぐにわかる存在である。
眼下に千曲川、遠方には高社山を中心に
高井地域が望める風景は
今も昔も変わるまい。
春休みも始まり
ちょっとした空き時間に
地域の史跡を巡り、
古人の足跡をたどるのもまた楽しいものである。
手子塚城があった地に建つ手子塚神社
史跡の看板が立ち、その昔を窺うことが出来る。
鉄塔の陰で見えにくいのであるが
手子塚城の下は「崖」になっていて
がけ下には、千曲川が流れる。
松が生い茂り
国道18号線を中野方面に右折し
セブンイレブンを過ぎると
すぐ右手に手子塚城跡は見える。
善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州からのちょっとした贈り物・・・・坂爪農園の田舎のりんごジャム&田舎のりんごジュース
たくさん食べたい信州のリンゴ・・・ ・・・レッドバザール 恒例のマークダウンでご好評販売中
しぼりたての美味しさをお届け・・・・・・・信州北信濃 坂爪農園のりんごジュース
りんごが「ゴロッ」と入った素朴な味わい・・田舎のりんごジャム 販売中。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村

2008年04月30日
鳥居川の水車・・・・・・水に親しかった頃
太公望には、またとない時期の到来です。
鳥居川も釣りにいい季節となりました。
その、鳥居川を使って、江戸末期から大正期に掛けて、「水車」が活躍しました。
鳥居川の水を、引き入れて、その水力を利用して、米や小麦を引いたのです。
往時、鳥居川の水車があった豊野町大倉入地区(イリ地区)には、20箇所ほどの
水車が活躍していたそうです。
信州とりわけ、北信濃では、「おやき」を中心に粉食が盛んであったわけですが、豊野地区でも、リンゴが作付けされる以前は当時の豊野町北部は、「菜黄麦青」といわれたように、春には、菜の花の黄色と、麦の青さが際立つ春であったわけです。
今の時季善光寺平の豊野辺りでは、「菜黄麦青」の面影は無く、リンゴや梨の白い花が奇麗に咲いていますが・・・・。
刈り取った小麦をこの水車を使った、「精米やさん」に粉に引いてもらったのでしょう。そうして、北信名物の「丸茄子」など使って「北信ならではの丸ナスのおやき」をずっと今の時代に伝えてきたのです。
おやきの文化は、こうして麦の栽培から、麦を挽いて、自家で米の代わりに主食として、伝わったのでしょう。
「水車」は、電力が発達する、大正末期までかなり繁盛したようです。
こういった小さな水車は、須坂の町にもあったようです。
須坂は、ご存知のように、岡谷と並ぶ製糸の街でしたが、
製糸に使う糸を繰る機械に水車の動力は欠かせなかったようです。
今は、豊野町入地区でも須坂でも水車の面影はありません。
川は、ひとたび豪雨になると、家をも飲み込む脅威でしたが、
田んぼの水を引いたり、水車に使ったり、身近に上手く川を利用していたに違いありません。
鳥居川で、泳いだり、石の下に手を突っ込んで、魚を捕まえたりは、
もうしていないのでしょう。
鳥居川は、生活に無くてはならなかった川はもとよりですが、
昭和50年代の小学生にとっては、遊びに欠かせない絶好の遊び場でした。
もっと言うならば、鳥居川は、小学生にとっては身近な場所でした。
最近、鳥居川の川辺に行っていません。
釣りもトンとご無沙汰です。
「水車」はなくなり、川で遊ぶ小学生も今ではいないでしょうが、
もっと身近に川を考えたいものだと思う今日この頃です。
鳥居川大倉入地区付近。
この辺りから、用水に水を引き、水車を回したのでしょうか。

石の下に手を突っ込むと、「ハヤ」や「オイカワ」をつかまえることが出来たが、今はどうでしょうか。
ニジマスは、簡単に釣れますが、技術を要する「友釣り」をしなければならない「鮎釣り」は、
我々小学生にとって、憧れであった。

鳥居川が、千曲川のに合流する付近。
未踏の地に探検するには、勇気が要った。
河口付近は、千曲川が身近でなかったせいか、「恐怖感」があり、
近寄りがたかった。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
鳥居川も釣りにいい季節となりました。
その、鳥居川を使って、江戸末期から大正期に掛けて、「水車」が活躍しました。
鳥居川の水を、引き入れて、その水力を利用して、米や小麦を引いたのです。
往時、鳥居川の水車があった豊野町大倉入地区(イリ地区)には、20箇所ほどの
水車が活躍していたそうです。
信州とりわけ、北信濃では、「おやき」を中心に粉食が盛んであったわけですが、豊野地区でも、リンゴが作付けされる以前は当時の豊野町北部は、「菜黄麦青」といわれたように、春には、菜の花の黄色と、麦の青さが際立つ春であったわけです。
今の時季善光寺平の豊野辺りでは、「菜黄麦青」の面影は無く、リンゴや梨の白い花が奇麗に咲いていますが・・・・。
刈り取った小麦をこの水車を使った、「精米やさん」に粉に引いてもらったのでしょう。そうして、北信名物の「丸茄子」など使って「北信ならではの丸ナスのおやき」をずっと今の時代に伝えてきたのです。
おやきの文化は、こうして麦の栽培から、麦を挽いて、自家で米の代わりに主食として、伝わったのでしょう。
「水車」は、電力が発達する、大正末期までかなり繁盛したようです。
こういった小さな水車は、須坂の町にもあったようです。
須坂は、ご存知のように、岡谷と並ぶ製糸の街でしたが、
製糸に使う糸を繰る機械に水車の動力は欠かせなかったようです。
今は、豊野町入地区でも須坂でも水車の面影はありません。
川は、ひとたび豪雨になると、家をも飲み込む脅威でしたが、
田んぼの水を引いたり、水車に使ったり、身近に上手く川を利用していたに違いありません。
鳥居川で、泳いだり、石の下に手を突っ込んで、魚を捕まえたりは、
もうしていないのでしょう。
鳥居川は、生活に無くてはならなかった川はもとよりですが、
昭和50年代の小学生にとっては、遊びに欠かせない絶好の遊び場でした。
もっと言うならば、鳥居川は、小学生にとっては身近な場所でした。
最近、鳥居川の川辺に行っていません。
釣りもトンとご無沙汰です。
「水車」はなくなり、川で遊ぶ小学生も今ではいないでしょうが、
もっと身近に川を考えたいものだと思う今日この頃です。
鳥居川大倉入地区付近。
この辺りから、用水に水を引き、水車を回したのでしょうか。

石の下に手を突っ込むと、「ハヤ」や「オイカワ」をつかまえることが出来たが、今はどうでしょうか。
ニジマスは、簡単に釣れますが、技術を要する「友釣り」をしなければならない「鮎釣り」は、
我々小学生にとって、憧れであった。

鳥居川が、千曲川のに合流する付近。
未踏の地に探検するには、勇気が要った。
河口付近は、千曲川が身近でなかったせいか、「恐怖感」があり、
近寄りがたかった。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
2008年04月23日
北信濃の火除けの信仰のご開扉
以前お話した平和観音がある「宝蔵院」で「火防大日如来」のご開扉が行なわれました。
毎年、4月22日に行なわれ、地元浅野地区を始め、各地から「講」を組み、この小さなお寺の「火除けの如来」の年に一度のご開扉に参詣し、
宝蔵院の檀家の女性たちが作る、手作りの味を櫻の花をみつつ、年に1度のこの行事が執り行われる。
冬の閑散期に、宝蔵院の和尚さんに聞いた話によると、江戸末期の善光寺地震の火災の頃から、講での参詣が始まったそうである。
以後、先の15年戦争中も途絶えることなく、遠くは群馬県や、長野市安茂里地区、山ノ内町など新酒の北信を中心に各地から、「火除け」のお寺として、4月22日のご開扉には、多数の参詣がある。
往時は、臨時列車まで出て、境内では、その「おもてなし」が出来ず、近所の蚕室を借りて、行なったとか・・・。
お寺が、講や各地からの参詣に訪れた方々に振舞う、お酒も4斗樽が、16個にもなったそうであるから、凄かったのであろう。
江戸の町ほど、密集はしていなかったが、今のように「ガス」でなく、直接釜戸で「火」を扱い、冬場は、炭火のコタツで過ごしていたわけであるから、「火」に対する恐怖心というか、考え方は今とは違ったものであったと思う。
最近は、「講」の一団の方々も高齢化してきたという。
しかしながら、こうした伝統は、既に一つの「風土・地域文化」である。
何が出来るかわからないが、こうした
信州の、信州の中の北信の、北信の中の豊野町のといった具合に
地域の行事を受け継ぎ、伝えていきたいと思う。
宝蔵院の境内に、特設の「おもてなし会場」が作られ、午前中は、「講」の方々が、午後は地元の方々が中心に、女性部の振る舞いの料理を味わう。

櫻の花が咲く下で、屋台が出ての賑わい。
今の時季「苗」を定植する時季であるから、
「苗」も結構売られている。

桜が満開の中での、小さなお寺の「火除け」の信仰は、
今年も大勢の「講」の信者を迎えた。

女性部の方々が、かまどを使って、もてなし料理を作る。

「火除け」のお札。
参拝者には、このお札を受ける。
お札は、台所など「火」を扱う場所に張り、
今年1年、火の事故を起こさないように、守ってもらう。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
毎年、4月22日に行なわれ、地元浅野地区を始め、各地から「講」を組み、この小さなお寺の「火除けの如来」の年に一度のご開扉に参詣し、
宝蔵院の檀家の女性たちが作る、手作りの味を櫻の花をみつつ、年に1度のこの行事が執り行われる。
冬の閑散期に、宝蔵院の和尚さんに聞いた話によると、江戸末期の善光寺地震の火災の頃から、講での参詣が始まったそうである。
以後、先の15年戦争中も途絶えることなく、遠くは群馬県や、長野市安茂里地区、山ノ内町など新酒の北信を中心に各地から、「火除け」のお寺として、4月22日のご開扉には、多数の参詣がある。
往時は、臨時列車まで出て、境内では、その「おもてなし」が出来ず、近所の蚕室を借りて、行なったとか・・・。
お寺が、講や各地からの参詣に訪れた方々に振舞う、お酒も4斗樽が、16個にもなったそうであるから、凄かったのであろう。
江戸の町ほど、密集はしていなかったが、今のように「ガス」でなく、直接釜戸で「火」を扱い、冬場は、炭火のコタツで過ごしていたわけであるから、「火」に対する恐怖心というか、考え方は今とは違ったものであったと思う。
最近は、「講」の一団の方々も高齢化してきたという。
しかしながら、こうした伝統は、既に一つの「風土・地域文化」である。
何が出来るかわからないが、こうした
信州の、信州の中の北信の、北信の中の豊野町のといった具合に
地域の行事を受け継ぎ、伝えていきたいと思う。
宝蔵院の境内に、特設の「おもてなし会場」が作られ、午前中は、「講」の方々が、午後は地元の方々が中心に、女性部の振る舞いの料理を味わう。

櫻の花が咲く下で、屋台が出ての賑わい。
今の時季「苗」を定植する時季であるから、
「苗」も結構売られている。

桜が満開の中での、小さなお寺の「火除け」の信仰は、
今年も大勢の「講」の信者を迎えた。

女性部の方々が、かまどを使って、もてなし料理を作る。

「火除け」のお札。
参拝者には、このお札を受ける。
お札は、台所など「火」を扱う場所に張り、
今年1年、火の事故を起こさないように、守ってもらう。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
滴る果汁と濃厚な甘さ・・・・信州の銘桃「川中島シリーズ」
安心安全な無農薬の新鮮野菜の美味しさ・・・・お野菜セット
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト