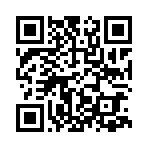2008年01月16日
蔵の町 須坂
ここ1~2週間、畑仕事の合間を縫って、小布施・須坂方面に出かけています。今日は「蔵の町 須坂」
須坂というと、「臥龍公園」くらいしか知らない私でした。
高校卒業後、都内で学生となり、19のときに須坂の自動車学校に行って以来でしょうか?随分とご無沙汰でした。
「蔵の町」というのは前々から聞いてはいたのですが、なぜ「蔵の街」かもよくわからずに、ずっと過ごしていました。ここへきて、重い腰をようやく上げて、なぜ蔵の街か?」ようやく判明しました。
千曲川沿岸部 河岸沿いは「黄金島」と呼ばれたように、夏は綿花、その裏作として秋から春に掛けては「菜種」という具合に、江戸の頃から盛んだったということは前にも書きました。もちろん、「稲作」がメインですから、農家の本業は稲作なわけですが、江戸も半ば以降は、「貨幣経済」が発達し、農家でも「貨幣」が必要となり、換金作物としての「綿花」や「菜種」が重宝されたわけです。
その「菜種」を大いに利用して商いをし、繁盛したのが「田中本家」です。
その後、明治期になり、「生糸」が重要な日本の輸出品として注目され、国策として、生糸生産が盛んになります。
江戸の頃から桑の栽培は既にあり、生糸の生産はされていたようですが、日本の基幹産業とならんと注目し、須坂に製糸工場を旗揚げして言ったのが、若き須坂の若者だったようです。
その若者たちが、率先して富岡製糸場の技術を導入し、須坂の製糸産業を盛り立てていきます。
こうして、「製糸の町 須坂」は成立し、その後様々な紆余曲折を経て、遂には昭和恐慌を迎えてしまいます。詳しくはまたご紹介するとして、こうした製糸産業と蔵が大きく関係しています。
蔵の街を歩くと、3階建ての建物や倉庫のような建物が目立ちますが、これは、「繭」を乾燥させるための部屋であったり、蔵は蔵でも、埼玉の川越の街のような「蔵」とはまた違い、要所要所に「製紙産業」の面影を見ることが出来ます。須坂の蔵は、製糸産業によってもたらされた蔵だったようです。
須坂は岡谷や諏訪よりも早く本格的な製糸産業をスタートさせました。当時、生糸は「山師的」な産業として、殖産興業政策により、推進はされたものの、みな二の足を踏んでいたようです。
須坂の「若き精鋭」たちの先見の明と普段の努力が、「製糸の町 須坂」を盛りてていきます。
なお、長野県は、国策として、「農家は桑の栽培と繭の生産を」を「企業は製糸産業を」といった具合に、戦前の日本の基幹産業である「製糸」のに大きく携わりますが、昭和恐慌により、一気にこの基幹産業は、閉塞し、壊滅的な打撃を蒙ります。
そして、更にこうした不況の打開策として、こちらも国策として進められたのが「満洲移民」で、長野県は、満洲移民移出日本一の県となりますが、それは大きな悲劇を生むこととなります。
満洲の移民と桑関係のことはまた次回に譲りますが、桜の咲く「須坂」もいいですが、冬景色の須坂も必見です。車でも簡単にいけますし、入場無料の施設も結構たくさんあります。
ぜひ「蔵の街 製糸の町 須坂」に足を運んでみたらいかがでしょう。
3階が繭の乾燥のために使われた蔵屋敷。

立派な門構えが、当時の繁栄を物語ります。

繭玉。繭玉の習慣は、桑を栽培していた北信地方には結構あるようで、我が豊野町でもありますが、ここまで「リアル」な繭玉は珍しいのでは?製糸産業の面影を伝えてくれます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
「完熟」&「完熟」の 「完熟サンふじ」
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
須坂というと、「臥龍公園」くらいしか知らない私でした。
高校卒業後、都内で学生となり、19のときに須坂の自動車学校に行って以来でしょうか?随分とご無沙汰でした。
「蔵の町」というのは前々から聞いてはいたのですが、なぜ「蔵の街」かもよくわからずに、ずっと過ごしていました。ここへきて、重い腰をようやく上げて、なぜ蔵の街か?」ようやく判明しました。
千曲川沿岸部 河岸沿いは「黄金島」と呼ばれたように、夏は綿花、その裏作として秋から春に掛けては「菜種」という具合に、江戸の頃から盛んだったということは前にも書きました。もちろん、「稲作」がメインですから、農家の本業は稲作なわけですが、江戸も半ば以降は、「貨幣経済」が発達し、農家でも「貨幣」が必要となり、換金作物としての「綿花」や「菜種」が重宝されたわけです。
その「菜種」を大いに利用して商いをし、繁盛したのが「田中本家」です。
その後、明治期になり、「生糸」が重要な日本の輸出品として注目され、国策として、生糸生産が盛んになります。
江戸の頃から桑の栽培は既にあり、生糸の生産はされていたようですが、日本の基幹産業とならんと注目し、須坂に製糸工場を旗揚げして言ったのが、若き須坂の若者だったようです。
その若者たちが、率先して富岡製糸場の技術を導入し、須坂の製糸産業を盛り立てていきます。
こうして、「製糸の町 須坂」は成立し、その後様々な紆余曲折を経て、遂には昭和恐慌を迎えてしまいます。詳しくはまたご紹介するとして、こうした製糸産業と蔵が大きく関係しています。
蔵の街を歩くと、3階建ての建物や倉庫のような建物が目立ちますが、これは、「繭」を乾燥させるための部屋であったり、蔵は蔵でも、埼玉の川越の街のような「蔵」とはまた違い、要所要所に「製紙産業」の面影を見ることが出来ます。須坂の蔵は、製糸産業によってもたらされた蔵だったようです。
須坂は岡谷や諏訪よりも早く本格的な製糸産業をスタートさせました。当時、生糸は「山師的」な産業として、殖産興業政策により、推進はされたものの、みな二の足を踏んでいたようです。
須坂の「若き精鋭」たちの先見の明と普段の努力が、「製糸の町 須坂」を盛りてていきます。
なお、長野県は、国策として、「農家は桑の栽培と繭の生産を」を「企業は製糸産業を」といった具合に、戦前の日本の基幹産業である「製糸」のに大きく携わりますが、昭和恐慌により、一気にこの基幹産業は、閉塞し、壊滅的な打撃を蒙ります。
そして、更にこうした不況の打開策として、こちらも国策として進められたのが「満洲移民」で、長野県は、満洲移民移出日本一の県となりますが、それは大きな悲劇を生むこととなります。
満洲の移民と桑関係のことはまた次回に譲りますが、桜の咲く「須坂」もいいですが、冬景色の須坂も必見です。車でも簡単にいけますし、入場無料の施設も結構たくさんあります。
ぜひ「蔵の街 製糸の町 須坂」に足を運んでみたらいかがでしょう。
3階が繭の乾燥のために使われた蔵屋敷。

立派な門構えが、当時の繁栄を物語ります。

繭玉。繭玉の習慣は、桑を栽培していた北信地方には結構あるようで、我が豊野町でもありますが、ここまで「リアル」な繭玉は珍しいのでは?製糸産業の面影を伝えてくれます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
「完熟」&「完熟」の 「完熟サンふじ」
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
Posted by ドジヒコ at
09:47
│Comments(0)