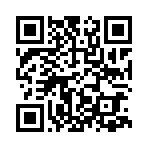2013年04月24日
火を防ぐ信仰に思う。
4月22日豊野町浅野の宝蔵院で
「火防大日如来」のご開扉が行われました。
宝蔵院は、曹洞宗のお寺でありますが
「火防」(火を防ぐ信仰)に関しても有名で
北信地域一帯からお参りに、お札を授かりに
毎年人々が見えます。
また、宝蔵院には
「火」とは逆の「水」に関しても
旱魃のときには、降雨を祈願すると
雨を降らすと言われる「牛石」と呼ばれる「神石」も
あるそうです。
今でこそ、農家が少なくはなりましたが
その昔は、大半が農家。
農家にとって、夏の降雨は死活問題となります。
豊野町は、鳥居川が東部に流れ
そこから水を引く「用水」や「堰」が多数あり
比較的、水に関しては恵まれてはいますが
旱魃のときは、その鳥居川の水量も減り
江戸時代には、鳥居川から堰に水を引く際に
水量に関して、各村で揉めた形跡が伺えます。
水に関しては、宝蔵院の「牛石」と並び
北信地域では、
戸隠神社のお種池の「種水」の信仰も有名です。
戸隠神社の「種水」に関しては
後日に譲りますが
「火」や「水」は身近な存在でもありますが
一歩間違えると恐ろしい存在ともなり
こうした「火」や「水」に対して
人々は遠い昔から、畏敬の念を抱いていたのでしょう。
同じ長野市でも権堂イトーヨーカ堂前の「秋葉神社」の
火防信仰も有名ですし、
秋葉信仰は全国的にも知られています。
火を防ぐ・火を伏せると言うことは
かつては今まで以上に注意深く行なわれていたでしょう。
「火事を未然に予防する」ということは
消火活動が未発達の時代にあっては至上命題であり
「火防」に対する信仰・人々の心持は
並々ならぬはずであったと思います
かつてと比べると
この宝蔵院の「火防信仰」による
火防大日如来の年に1度のご開扉、
かなり動員の数こそ減ったようではありますが
こうした信仰と言うより「地域の文化」は、
いつまでも続いて欲しいと願います。
なお、宝蔵院の火防信仰に関しては
お隣小布施町の「日本の明かり博物館」から
出版された「燈火・民俗見聞」に詳しく書かれています。
いずれも故人となられてしましましたが
山崎ます美さんと金箱正美さんの
お二人の学芸員さんが
北信地域一帯の「火」や「明かり」に関して
フィールドワークを元に詳しく調べておられ
信州の地域文化・民俗として
非常に面白い書物となっています。
ぜひ、ご一読をお勧めいたします。
日曜日には大雪、
そして月曜日・火曜日と2日間にわたる強烈な遅霜・・・、
今回、ここ数日で「これでもか!!」と言うほど
寒の戻りによる強烈な自然災害に見舞われました。
IPS細胞の研究に依る再生医療が現実化してきましたが
今回のような強烈な自然災害は、
未然に防ぐことはまだ出来ませんし
未然に防ぐ技術の開発の見通しもありません。
あらためて、火防信仰に見られるような
遠い昔からの「信仰」は
単に伝統でも過去の歴史でもなく
今に、これからも生き続ける
人々の拠り所だと痛感しました。
偉大なる自然を敬い、
そして自然がもたらす災害を恐れる
昔からの人々の信仰は
現代の世の中にあっても
そしてこれからもずっと続くでしょう。
火防信仰のある「宝蔵院」

4月22日、開催された
火防大日如来のご開扉
町域から北信地域一帯から
「火」に感謝し畏敬の念を持って
「火防」の祈願

各地から集まった方々に
お茶を飲んでいただき
北信の春の名物「菜の花の辛し和え」を
召し上がっていただくのが
恒例となっているようです。

当日参拝に訪れた信者には
「火防のお札」が配られ
今年一年間「火」に関して
無事なことを祈ります。

寺院下の空き地では
恒例の苗市が開催されました。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。

にほんブログ村
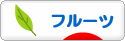
にほんブログ村
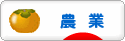
にほんブログ村


「火防大日如来」のご開扉が行われました。
宝蔵院は、曹洞宗のお寺でありますが
「火防」(火を防ぐ信仰)に関しても有名で
北信地域一帯からお参りに、お札を授かりに
毎年人々が見えます。
また、宝蔵院には
「火」とは逆の「水」に関しても
旱魃のときには、降雨を祈願すると
雨を降らすと言われる「牛石」と呼ばれる「神石」も
あるそうです。
今でこそ、農家が少なくはなりましたが
その昔は、大半が農家。
農家にとって、夏の降雨は死活問題となります。
豊野町は、鳥居川が東部に流れ
そこから水を引く「用水」や「堰」が多数あり
比較的、水に関しては恵まれてはいますが
旱魃のときは、その鳥居川の水量も減り
江戸時代には、鳥居川から堰に水を引く際に
水量に関して、各村で揉めた形跡が伺えます。
水に関しては、宝蔵院の「牛石」と並び
北信地域では、
戸隠神社のお種池の「種水」の信仰も有名です。
戸隠神社の「種水」に関しては
後日に譲りますが
「火」や「水」は身近な存在でもありますが
一歩間違えると恐ろしい存在ともなり
こうした「火」や「水」に対して
人々は遠い昔から、畏敬の念を抱いていたのでしょう。
同じ長野市でも権堂イトーヨーカ堂前の「秋葉神社」の
火防信仰も有名ですし、
秋葉信仰は全国的にも知られています。
火を防ぐ・火を伏せると言うことは
かつては今まで以上に注意深く行なわれていたでしょう。
「火事を未然に予防する」ということは
消火活動が未発達の時代にあっては至上命題であり
「火防」に対する信仰・人々の心持は
並々ならぬはずであったと思います
かつてと比べると
この宝蔵院の「火防信仰」による
火防大日如来の年に1度のご開扉、
かなり動員の数こそ減ったようではありますが
こうした信仰と言うより「地域の文化」は、
いつまでも続いて欲しいと願います。
なお、宝蔵院の火防信仰に関しては
お隣小布施町の「日本の明かり博物館」から
出版された「燈火・民俗見聞」に詳しく書かれています。
いずれも故人となられてしましましたが
山崎ます美さんと金箱正美さんの
お二人の学芸員さんが
北信地域一帯の「火」や「明かり」に関して
フィールドワークを元に詳しく調べておられ
信州の地域文化・民俗として
非常に面白い書物となっています。
ぜひ、ご一読をお勧めいたします。
日曜日には大雪、
そして月曜日・火曜日と2日間にわたる強烈な遅霜・・・、
今回、ここ数日で「これでもか!!」と言うほど
寒の戻りによる強烈な自然災害に見舞われました。
IPS細胞の研究に依る再生医療が現実化してきましたが
今回のような強烈な自然災害は、
未然に防ぐことはまだ出来ませんし
未然に防ぐ技術の開発の見通しもありません。
あらためて、火防信仰に見られるような
遠い昔からの「信仰」は
単に伝統でも過去の歴史でもなく
今に、これからも生き続ける
人々の拠り所だと痛感しました。
偉大なる自然を敬い、
そして自然がもたらす災害を恐れる
昔からの人々の信仰は
現代の世の中にあっても
そしてこれからもずっと続くでしょう。
火防信仰のある「宝蔵院」
4月22日、開催された
火防大日如来のご開扉
町域から北信地域一帯から
「火」に感謝し畏敬の念を持って
「火防」の祈願
各地から集まった方々に
お茶を飲んでいただき
北信の春の名物「菜の花の辛し和え」を
召し上がっていただくのが
恒例となっているようです。
当日参拝に訪れた信者には
「火防のお札」が配られ
今年一年間「火」に関して
無事なことを祈ります。
寺院下の空き地では
恒例の苗市が開催されました。
善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
信州のくだもののある生活をご一緒に
地球に優しい、環境にやさしい農業を目指して・・・・・・・・長野県環境にやさしい農産物認証を取得しました。
美味しい信州ならではの産直サイト
長野の桃 梨 りんごの産直 信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
ランキングに参加しています。
クリックしていただけると幸いです。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村