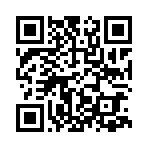2008年01月08日
千曲川 その1
昨日は、小布施の北斎館に行ってきました。北斎のことはまた書くとして、北斎を江戸から招いて、小布施の地で北斎館にある祭り屋台の天井画や岩松院の鳳凰の天井画を描いてもらったのが、豪商「高井鴻山」です。鴻山は、江戸末期から明治期に掛けて活躍した人で、塩屋とも呼ばれたことからその地域の塩の扱いを一手に担っていたようです。
もともとは、「市村」姓でしたから、現在の「枡一酒造」や栗菓子の「小布施堂」は、市村氏の経営ですから、今でも豪商の名残は伺えます。子供の頃は、高井鴻山の末裔の市村郁夫という方は、確か県議会議員もしていたような記憶があります。
さて、その市村鴻山こと「高井鴻山」は、千曲川の水運を利用して、新潟から千曲川を使って小布施の地まで海運業(水運業)を営もうとした節があるようです。
当時、小布施やここ豊野町は、リンゴなどまだ無く、明治初頭ですから、はたまた「蚕」もまだ本格的に始まっていなかったようで、綿を栽培していたようです。今でも、小布施や豊野の千曲川沿岸に無数の「菜の花」が春になると咲き誇るのはその名残でしょう。油は、絞って、油にし、須坂から峠を越え、群馬県に運ばれ、江戸に移出されたようです。その油は、行灯等に使われたようです。そうした油などを千曲川を使って、新潟まで運び、新潟からまた山国長野に無い物資を運び、販売する方法が考えられたのでしょう。
明治20年代に入り、信越線が開業し、長野新潟間が、鉄道で結ばれるようになると、千曲川の水運業の話は、一気にその力を失っていったようです。
その当時もし、千曲川の水運業が盛んになり、新潟長野間の通運の一大勢力になっていれば、今の千曲川にも、東京の隅田川や江戸井川のように、ポンポン船が行き来し、もう少し華やかな光景が今でも見られたのかもしれません。
現在、千曲川は、昔のような「サケ漁」もなく、船の行き交うことも無く、ゆったりと流れていますが明治の初頭には、交易の担い手たらんとしようとしたことはなかなか奥が深い川だと改めて痛感いたします。
小布施の街の北斎館。
北斎館を中心に、栗菓子の老舗が立ち並ぶ。


善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
「完熟」&「完熟」の 「完熟サンふじ」
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
もともとは、「市村」姓でしたから、現在の「枡一酒造」や栗菓子の「小布施堂」は、市村氏の経営ですから、今でも豪商の名残は伺えます。子供の頃は、高井鴻山の末裔の市村郁夫という方は、確か県議会議員もしていたような記憶があります。
さて、その市村鴻山こと「高井鴻山」は、千曲川の水運を利用して、新潟から千曲川を使って小布施の地まで海運業(水運業)を営もうとした節があるようです。
当時、小布施やここ豊野町は、リンゴなどまだ無く、明治初頭ですから、はたまた「蚕」もまだ本格的に始まっていなかったようで、綿を栽培していたようです。今でも、小布施や豊野の千曲川沿岸に無数の「菜の花」が春になると咲き誇るのはその名残でしょう。油は、絞って、油にし、須坂から峠を越え、群馬県に運ばれ、江戸に移出されたようです。その油は、行灯等に使われたようです。そうした油などを千曲川を使って、新潟まで運び、新潟からまた山国長野に無い物資を運び、販売する方法が考えられたのでしょう。
明治20年代に入り、信越線が開業し、長野新潟間が、鉄道で結ばれるようになると、千曲川の水運業の話は、一気にその力を失っていったようです。
その当時もし、千曲川の水運業が盛んになり、新潟長野間の通運の一大勢力になっていれば、今の千曲川にも、東京の隅田川や江戸井川のように、ポンポン船が行き来し、もう少し華やかな光景が今でも見られたのかもしれません。
現在、千曲川は、昔のような「サケ漁」もなく、船の行き交うことも無く、ゆったりと流れていますが明治の初頭には、交易の担い手たらんとしようとしたことはなかなか奥が深い川だと改めて痛感いたします。
小布施の街の北斎館。
北斎館を中心に、栗菓子の老舗が立ち並ぶ。


善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨
「完熟」&「完熟」の 「完熟サンふじ」
信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト
Posted by ドジヒコ at 10:04│Comments(0)